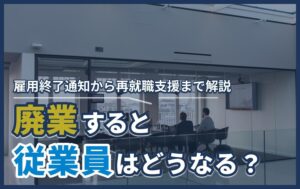廃業届の正しい書き方:提出先と必要書類のチェックリスト
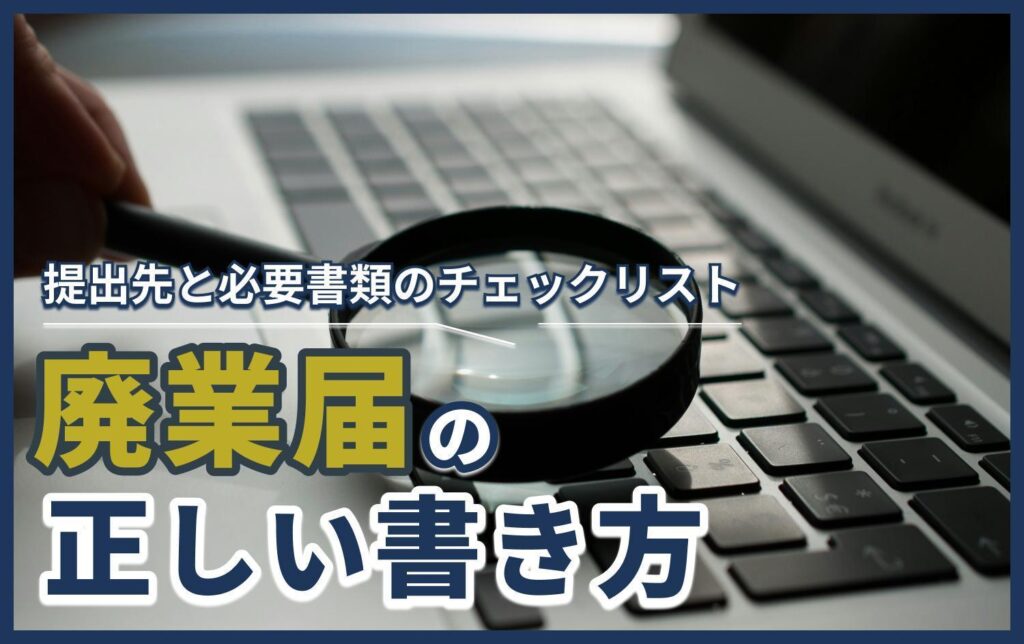
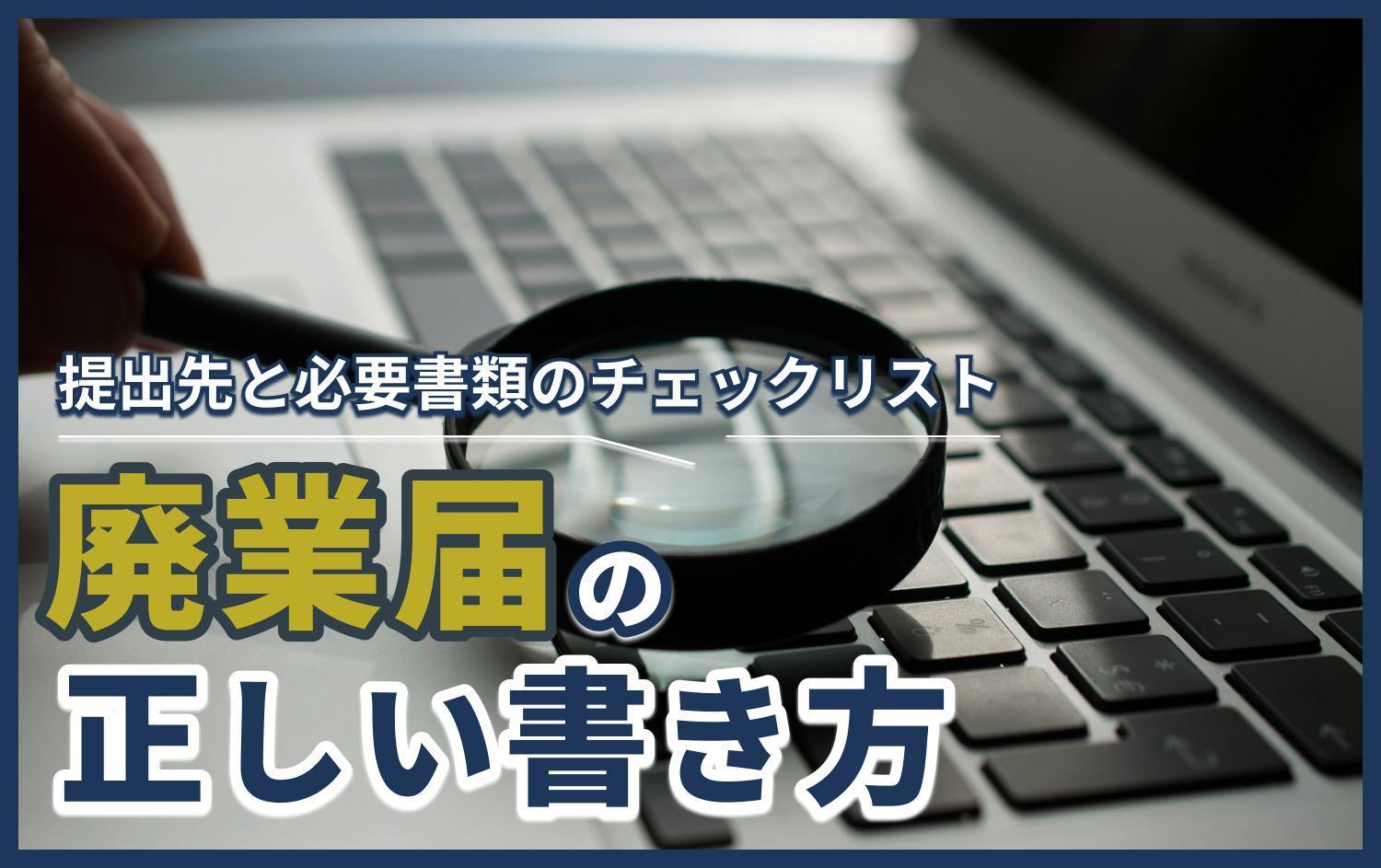
「廃業しようかな…」そんな風に考え始めたあなた。長年続けてきた事業に終止符を打つのは、誰にとっても簡単な決断ではありません。廃業の手続きは複雑で、何から手をつけていいのかわからない。そんな不安を抱えているのではないでしょうか。
特に、廃業届の書き方や提出先、必要書類の準備には、頭を悩ませている方も多いはず。でも、大丈夫です。正しい知識と段取りさえ押さえておけば、難しいことは多くないです。
本記事では、廃業届の書き方から提出のポイントまで、個人事業主の視点でわかりやすく解説します。
目次
廃業届とは何か
廃業届とは、個人事業主が事業をやめる際に、税務署に提出する届出書類のことを指します。事業の終了を税務当局に知らせ、納税義務や社会保険の加入を解除するための重要な手続きの一つです。
廃業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称の書類に該当します。この届出書に事業主の情報や廃業年月日などを記入し、決められた期限内に管轄の税務署へ提出する必要があるのです。
廃業を検討するときの相談先は?具体的な相談の進め方について解説
廃業届の提出が必要な理由
(1) 個人事業主の納税義務と徴収義務の終了
なぜ、廃業届の提出が必要なのでしょうか。大きな理由の一つが、個人事業主としての納税義務と徴収義務を終了させるためです。
事業を行っている間は、所得税や消費税、住民税など様々な税金の納付が求められます。また、従業員を雇用している場合は、源泉所得税の徴収・納付義務も生じます。
廃業届を提出することで、こうした義務が解除され、事業主は新たな一歩を踏み出す準備ができるのです。
(2) 税務上のトラブル防止
廃業届の提出は、将来的な税務トラブルを防ぐ意味でも重要です。
もし届出を怠ると、税務署から事業を継続しているものとみなされ、申告書の提出を求められたり、予期せぬ税務調査を受けたりするリスクがあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、廃業の意思を正式に届け出ておく必要があるのです。
廃業届の提出方法
(1) 管轄の税務署への提出
では、廃業届はどこに提出すればよいのでしょうか。原則として、事業の所在地を管轄する税務署が提出先となります。
例えば、東京都内で事業を行っていた場合は、事業所の所在地を管轄する都内の税務署に届け出ます。提出先に迷ったら、国税庁のホームページで確認するのがおすすめです。
(2) 提出方法:窓口持参、郵送、e-Tax
廃業届の提出方法は、大きく3つあります。
まず一つ目が、税務署の窓口に直接持参する方法。記載内容に不安がある場合は、担当者に相談しながら提出できるメリットがあります。
二つ目は、郵送での提出。遠方の税務署へわざわざ足を運ぶ必要がなく、手軽に手続きを完了できます。書類の到着確認ができるよう、簡易書留など記録の残る方法で送付しましょう。
三つ目は、電子申告システム「e-Tax」の利用です。事前の利用者登録が必要ですが、オンラインで24時間いつでも提出が可能。書類の郵送コストも削減できるのが魅力です。
廃業届の必要書類チェックリスト

廃業届の提出には、様々な書類の準備が欠かせません。以下のチェックリストを参考に、もれなく揃えておきましょう。
-
- 個人事業の開業・廃業等届出書(必須)
- 事業廃止届出手続(個人事業税の納税者)
- 青色申告の取りやめ届出書(青色申告者)
- 消費税の事業廃止届出書(消費税課税事業者)
- 所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請書(予定納税者)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(給与支払事業者)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
状況に応じて必要な書類は異なります。かかりつけの税理士や、最寄りの税務署に相談して、具体的な必要書類を確認するのがおすすめです。
廃業届の記入方法と注意点
(1) 届出書の各項目の記入方法
肝心の廃業届、どのように記入すればよいのでしょうか。
届出書には、事業主の氏名や住所、個人番号(マイナンバー)、廃業年月日など、事業の概要を記載する欄があります。それぞれの項目について、以下の点に注意しながら記入します。
-
- 届出年月日:提出する日付を記入
- 税務署名:事業所の所在地を管轄する税務署名を記入
- 氏名、生年月日、個人番号:事業主本人の情報を漏れなく正確に記入
- 住所、電話番号:事業主の現住所と連絡先を記入。別の住所に事業所がある場合は「上記以外の住所」欄にも記入
- 届出の区分:「廃業」を○で囲む
- 廃業の年月日:事業を廃業した正式な年月日を記入
(2) よくある記入ミスと注意点
記入にあたり、以下のような点に気をつけましょう。
-
- 字が読みづらい、記入漏れがある
- 住所や名前の誤記、個人番号の記入ミス
- 廃業の理由が書かれていない
- 本人確認書類の添付忘れ
記入ミスは書類の不受理や再提出につながりかねません。提出前にしっかりと確認し、必要に応じて専門家のチェックを受けるのも一案です。
廃業届の提出期限と注意点
(1) 廃業日から1ヶ月以内の提出
廃業届の提出期限は、原則として廃業日から1ヶ月以内です。期限までに税務署に届けることが義務付けられているので、忘れずに手続きを進めましょう。
期限が近づいてきたら、提出スケジュールを立てるのがおすすめ。余裕を持って書類を準備し、万が一の郵送トラブルも考慮に入れておくと安心です。
(2) 期限を過ぎた場合の対応
万が一、提出期限を過ぎてしまったらどうすればよいのでしょうか。
結論からいえば、できるだけ早く提出することが肝心です。法律上、廃業届の提出期限に罰則はありません。しかし、あまりに遅れると税務署から事情を尋ねられる可能性があります。
期限を大幅に過ぎてしまった場合は、税務署へ相談の上、指示に従って速やかに手続きを済ませましょう。
(3) 提出時の注意点(書類の不備、再提出など)
廃業届を提出する際は、書類の不備がないか十分に確認が必要です。記入漏れや添付書類の不足など、ささいなミスで受理されないことも。
もし書類が受理されなかった場合は、指摘された箇所を修正し、速やかに再提出します。スムーズに手続きを完了するためにも、提出前の確認作業は念入りに行いましょう。
廃業届を提出しない場合のリスク

(1) 事業継続とみなされる可能性
廃業届の提出を怠ると、どのようなリスクがあるのでしょうか。
まず懸念されるのが、税務署から事業を継続しているとみなされてしまうこと。廃業の意思を正式に伝えていない以上、税務署としては事業が続いているものと判断せざるを得ません。
その結果、本来不要になったはずの確定申告の案内が届いたり、予告なしの税務調査を受けたりする恐れがあるのです。
(2) 確定申告の催促や追徴課税のリスク
事業継続とみなされれば、当然ながら確定申告の義務も生じます。廃業届を出していない状態で申告をしない場合、無申告と判断され、催促や指導の対象になります。
さらに、過去の申告内容に不備があった場合は、追徴課税を受けるリスクも。仮に不正な申告をしていなくても、書類上は事業を継続しているのですから、突然の税務調査を受ける可能性は否定できません。
廃業届の提出は、こうした無用なトラブルを避けるためにも欠かせない手続きなのです。
休業の場合の届出について
(1) 所得税法上の休業届の不要性
「廃業ではなく、一時的に事業を休止したい」という方もいるかもしれません。その場合、休業届の提出は必要なのでしょうか。
所得税法上は、事業の休止を届け出る義務はありません。あくまでも事業をやめる場合にのみ、廃業届の提出が求められます。
ただし、後述するように、一部の自治体では独自のルールを設けている場合があります。事業を休止する際は、管轄の税務当局に確認を取っておくのが賢明です。
(2) 自治体による事業休止届の取り扱い
所得税とは別に、住民税の観点から、事業休止届の提出を求める自治体もあります。
たとえば、東京都では個人事業税の納税者に「個人事業の休止・再開・廃止申告書」の提出を義務付けています。休業中は課税が免除される一方、休業届の提出を怠ると、たとえ事業を行っていなくても税金が課されてしまうのです。
事業を休止する際は、所轄の自治体の取り決めを確認し、必要な手続きを遺漏なく行いましょう。
廃業手続きに伴う、その他の手続き
廃業届の提出は、廃業手続きの一部に過ぎません。届出と並行して、以下のような手続きにも気を配る必要があります。
(1) 「青色申告の取りやめ届出書」とは
青色申告を行っている事業主は、廃業に伴い「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。この届出がないと、青色申告の承認が自動的に継続されてしまうので注意が必要です。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」とは、個人事業主が青色申告を取りやめる際に提出する届出書です。個人事業主が廃業する場合、青色申告を取りやめる必要があります。その際、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出することになるのです。この届出書を提出することで、税務署に青色申告の取りやめを通知し、廃業後の手続きをスムーズに進められます。
提出時期
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は、廃業日の属する年分の翌年3月15日までに提出する必要があります。例えば、2023年6月30日に廃業する場合、2024年3月15日までに提出することになります。ただし、なるべく早めに提出することをおすすめします。届出書提出が遅れると、青色申告のメリットを受けられなくなる可能性があるためです。
提出方法
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は、原則として個人事業主の所轄税務署に提出します。届出書は、直接税務署の窓口に持参するか、郵送で提出することができます。郵送の場合は、届出控えを保管しておくことをおすすめします。また、e-Taxを利用すれば、オンラインでの提出も可能です。e-Taxは、国税に関する各種手続きをインターネット上で行うことができるシステムです。事前の利用者登録が必要ですが、24時間365日利用できる便利なサービスです。
手数料
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出時には、手数料は発生しません。窓口持参、郵送、e-Taxのいずれの方法でも、無料で提出することができます。
ただし、郵送の場合は切手代が必要となります。また、e-Taxを利用する場合は、インターネット接続料金などの通信費用が発生します。
記入方法
-
- 「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の記入方法は、以下の通りです。
- 氏名や住所、個人番号(マイナンバー)など、個人事業主の基本情報を記入します。
- 青色申告の取りやめ年月日(廃業日)を記入します。
- 取りやめの理由を記入します。廃業の場合は、「廃業のため」などと記入します。
- 届出書提出日と個人事業主の署名・押印を行います。
- 記入の際は、誤りがないよう十分に確認することが大切です。不明な点がある場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
(2) 消費税の納税義務の有無の確認
消費税の課税事業者であれば、「消費税の納税義務の免除事由に該当することとなった旨の届出書」の提出が必要です。課税事業者の条件を満たさなくなった場合は、税務署への届出をお忘れなく。
(3) 個人事業税の清算手続き
地方税である個人事業税は、都道府県によって手続きが異なります。廃業に伴う清算方法や必要書類について、管轄の税務当局に確認し、適切に対応しましょう。
廃業届に関してよくある質問
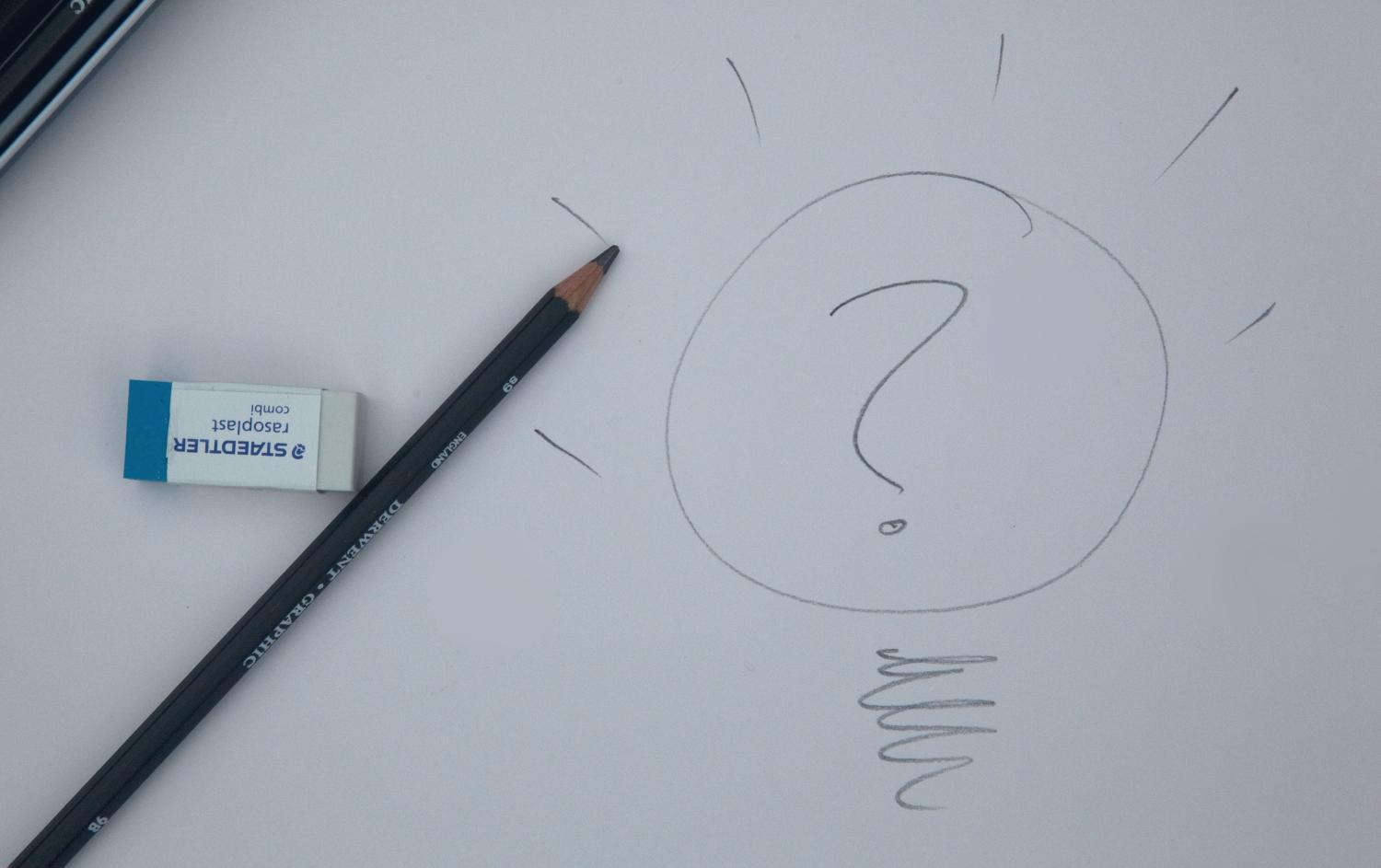
個人事業主と法人の廃業手続きは違う?
まず、法人の廃業手続きと個人事業主の廃業手続きの違いについて見ていきましょう。個人事業主の場合、税務署への届出のみで廃業手続きが完了します。一方、法人の場合は、税務署への届出だけでなく、法務局への登記も必要となります。
具体的には、法人の廃業手続きでは、以下の2つの手続きが必要です。
-
- 税務署への「法人設立届出書」と「法人異動届出書」の提出
- 法務局への「解散登記」と「清算結了登記」の申請
税務署への届出は、法人設立届出書と法人異動届出書を提出することで完了します。一方、法務局への登記は、解散登記と清算結了登記の2段階に分かれます。解散登記は、解散事由が発生した日から2週間以内に行う必要があります。清算結了登記は、清算が結了した日から2週間以内に行います。
このように、法人の廃業手続きは、個人事業主よりも複雑で、手間と時間がかかるのが特徴です。専門家のアドバイスを参考にしながら、無理のないスケジュールを立てて着実に進めることが大切です。
廃業を検討するときの相談先は?具体的な相談の進め方について解説
廃業手続きにかかる費用はいくらか?
廃業手続きにかかる費用も、経営者にとって気になるポイントの一つでしょう。個人事業主の場合、廃業届の提出自体に費用はかかりません。ただし、税理士に依頼する場合は、別途報酬が必要となります。
一方、法人の場合は、登記申請に印紙代がかかります。解散登記と清算結了登記の申請には、それぞれ3万円の収入印紙が必要です。また、税理士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
廃業手続きにかかる費用は、事業の規模や内容によって異なります。事前に専門家に相談し、必要な費用を見積もっておくことが大切です。廃業に伴う資金繰りにも影響するため、十分な準備が求められます。
廃業ではなく休業したい場合も届出は必要か?
最後に、廃業ではなく休業したい場合の届出について見ていきましょう。休業とは、一定期間事業を休止することを指します。休業の場合も、税務署への届出が必要となります。
休業届の提出は、休業開始日から1ヶ月以内に行う必要があります。届出先は、法人の場合は法人税の所轄税務署、個人事業主の場合は所得税の所轄税務署となります。
休業期間中も、税務署への届出や申告は必要です。法人の場合は、休業中も法人税の確定申告を行わなければなりません。個人事業主の場合は、休業中の所得がなければ、確定申告は不要です。
休業から事業を再開する際は、再開届を提出する必要があります。休業期間が長期にわたる場合は、税務署への相談が必要となるでしょう。
事業承継という手段も検討しましたか?
最後に、廃業とは異なる選択肢についても触れておきます。それが「事業承継」です。
個人事業は、株式会社などの法人と異なり、誰かに引き継ぐことが可能です。たとえ親族内に後継者がいなくても、従業員や外部の第三者に事業を譲渡することで、会社の資産や雇用を守ることができるのです。
「廃業」は、事業主にとって人生の一大決断。でも、本当にそれが最善の選択なのか。一度立ち止まって、事業をさらに発展させる道を検討してみてもいいかもしれません。
事業承継についての意思決定は慎重に。でも、可能性を模索してみる価値は十分にあるのではないでしょうか。
事業承継の進め方を解説!成功させるためのポイントも紹介します
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。