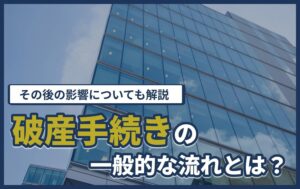小規模企業共済制度とは?活用法やデメリットについて解説
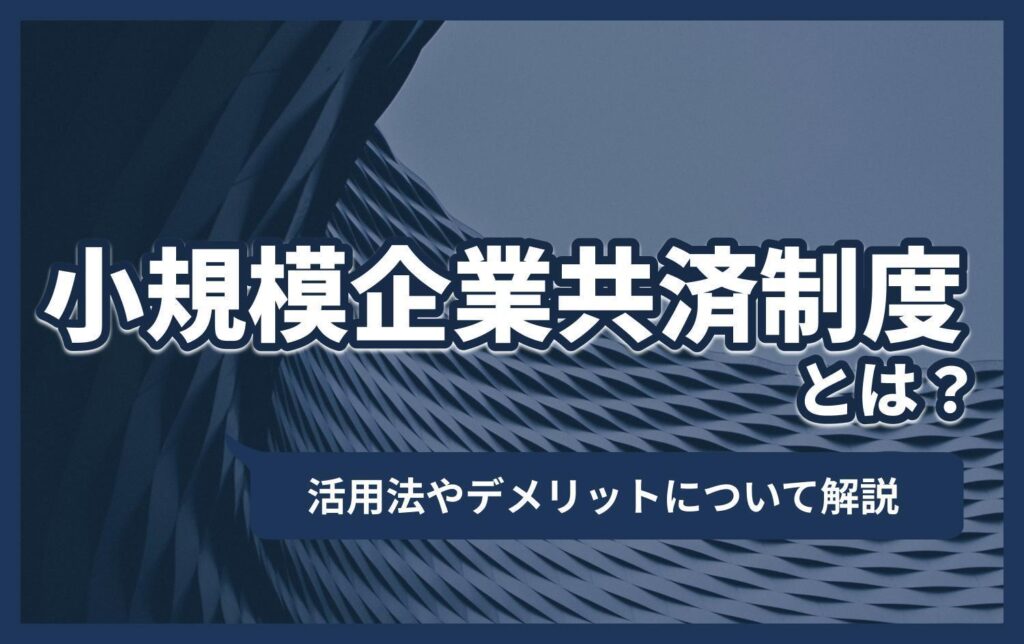
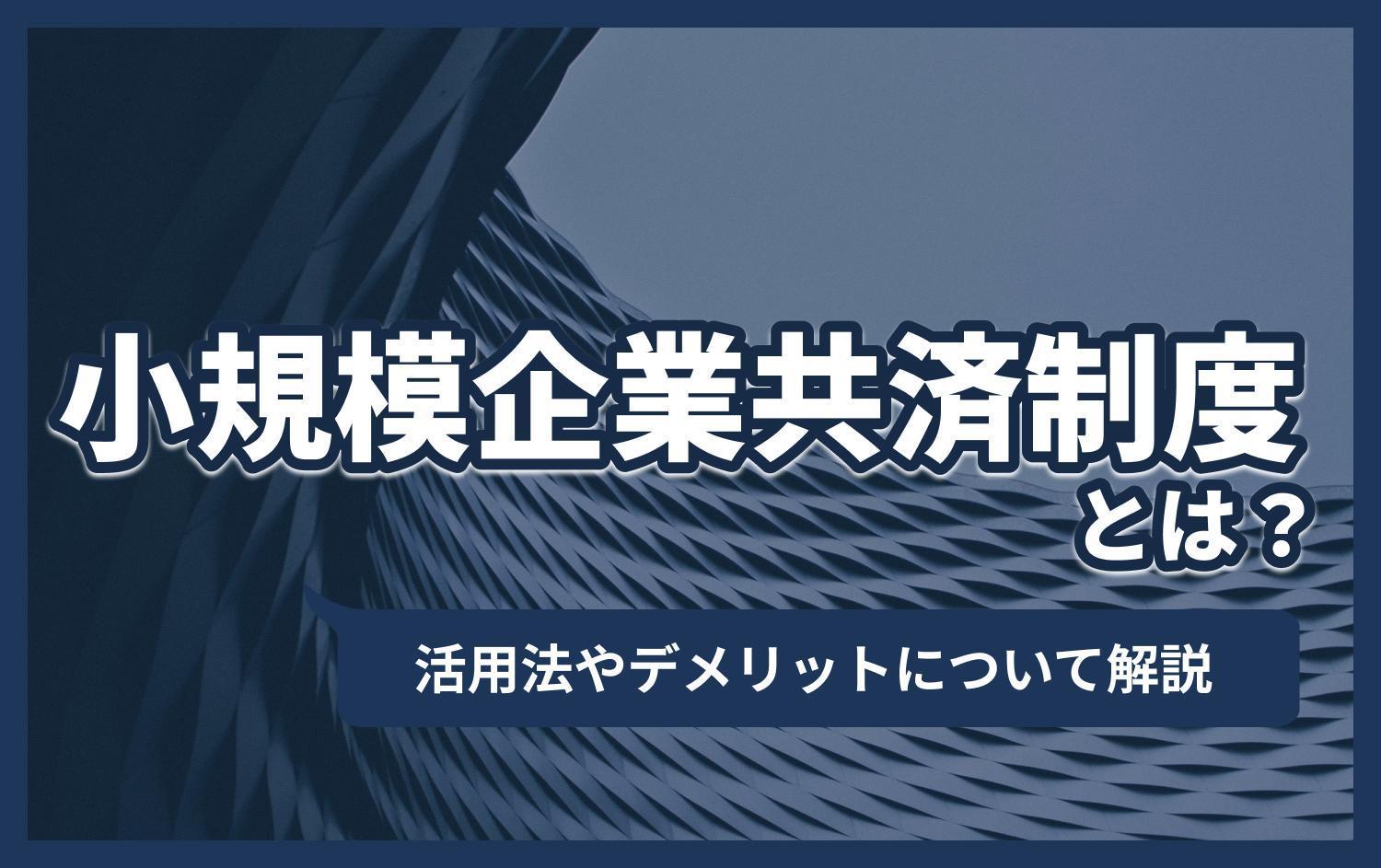
中小企業経営者の皆様、日々の経営の中で将来への不安を感じることはありませんか?「事業が軌道に乗ったら、そろそろ引退を考えないと…」「でも、退職金の準備が全然できていない…」。こうしたお悩みを抱えている経営者の方は少なくないのではないでしょうか。
実は、そんな中小企業経営者の味方になる制度があります。それが、「小規模企業共済制度」です。この制度は、個人事業主や会社等の役員の方々が、将来に備えて資金を準備できる仕組みとなっています。
小規模企業共済とは
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方々のための共済制度です。掛金は全額所得控除の対象となり、事業をやめたり役員を退職したときには、共済金を受け取ることができます。いわば、経営者の方のための国が作った退職金制度といえるでしょう。
掛金の税法上の扱い
小規模企業共済の掛金は、支払った年の課税対象となる所得から控除されます。全額が必要経費または所得控除の対象となるため、所得税と住民税が軽減されるというメリットがあります。
経営者の皆様にとって、節税対策は重要な経営課題の一つですよね。小規模企業共済の掛金は、税金面でお得な制度設計になっているのです。将来の備えを着実に行いつつ、合法的に税負担を抑えることができる、一石二鳥の制度と言えます。
とりわけ、個人事業主の方にとっては、掛金の全額を所得から控除できるのは大きなメリットでしょう。会社等の役員の方であれば、所得控除の対象となります。所得税の課税対象となる所得が減れば、税負担も自ずと下がります。
小規模企業共済の掛金はどのくらい?
掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲で、500円刻みで自由に選ぶことができます。自分の収入や生活スタイルに合わせて、無理のない掛金額を設定できるのも魅力の一つです。
例えば、月々5万円の掛金を20年間積み立てた場合、総積立額は1,200万円になります。仮に運用利回りが年1%だとすると、受け取る共済金は約1,330万円。退職金の原資として、十分な金額を準備できるでしょう。
掛金の設定に迷ったら、加入後の生活設計をシミュレーションしてみるのもおすすめです。公的年金や他の収入源も考慮しつつ、老後の生活に必要な資金を試算。その金額を達成できる掛金を逆算すれば、目安が見えてくるはずです。
ただし、掛金の設定は慎重に行うことが大切です。将来的な収入の変化にも対応できる、無理のない掛金月額を選びましょう。経営環境の変化に備えて、柔軟に対応できる余裕を持つことが賢明です。
小規模企業共済の仕組みとは
小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。加入者は、毎月一定額の掛金を納付します。掛金は、加入者が自由に選択した金額を、毎月同じ金額で納めます。
そして、加入者が事業をやめたり役員を退職したときに、共済金を受け取れる仕組みになっています。受け取る共済金の額は、掛金納付月数と掛金月額に応じて計算されます。
共済契約は、原則65歳まで継続します。掛金の納付は、経営者の状況に合わせて一時的に休止することも可能です。ただし、共済金を受け取るためには、12ヵ月以上の掛金納付が必要です。
制度への加入は任意ですが、「経営者の退職金制度」としての性格上、できるだけ長く継続することが望ましいでしょう。時間をかけてコツコツと積み立てていくことで、十分な共済金を受け取ることができます。
経営者の皆様には、小規模企業共済の仕組みをしっかりと理解し、自社の状況を見据えた計画的な活用をおすすめします。
小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済に加入できるのは、以下のいずれかに該当する方です。
-
- 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下の個人事業主
- 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下の会社等の役員
ここでいう「常時使用する従業員」には、パートタイマーや臨時員は含まれません。あくまでも、労働の対価として賃金を支払っている人数が基準となります。
例えば、従業員が20人以下の個人事業主が、別に5人のパートタイマーを雇用しているケース。この場合、パートタイマーの5人はカウントされないため、合計25人の従業員を抱えていても加入資格があることになります。
また、加入にあたっては、事業実態が必要です。副業の方は、本業の常時使用する従業員数が加入対象となります。
1つの事業に専念している方は問題ありませんが、副業をお持ちの方は注意が必要ですね。本業と副業のどちらを基準に判断するのか、加入前によく確認しておきましょう。
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済には、以下のようなメリットがあります。
退職金代わりになる
共済金は、事業をやめたり会社等の役員を退職したときに受け取れます。第一線を退くときの生活資金の備えとなり、老後の安心につながります。
「老後資金が心配」というのは、多くの経営者の方が抱える悩みの一つ。社会保険料の負担が重く、なかなか思うように蓄えができないという声をよく耳にします。
小規模企業共済の掛金は、毎月コツコツと積み立てていく仕組み。加入期間が長ければ長いほど、受け取れる共済金も大きくなります。時間をかけた着実な準備が、将来への大きな安心につながるのです。
掛金が全額所得控除される
前述の通り、掛金は全額が所得控除の対象になります。所得税や住民税の負担が軽減されるため、実質的な掛金負担が少なくなります。
所得控除とは、課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことで、税負担を軽減する制度です。所得控除が適用されると、課税所得が減るため、所得税と住民税が安くなるわけです。
小規模企業共済の掛金控除は、支払った掛金の全額が対象。他の所得控除と比べても、控除額が大きいことが特徴と言えます。
共済制度への月々の拠出金が、そのまま節税効果につながるイメージですね。将来に向けた資産形成と節税対策が同時にできるメリットは、経営者の皆様にとって見逃せないポイントではないでしょうか。
低金利の貸付制度を利用できる
一定の条件を満たせば、納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付を受けられます。金利は低く設定されており、事業資金の調達手段の一つとして活用できます。
小規模企業共済の貸付制度は、加入者が事業資金などを低利で借り入れできる仕組みです。貸付限度額は、原則として掛金納付総額の7~9割程度。金利は年1.5%と、民間金融機関の水準よりかなり低めに設定されています。
運転資金や設備資金など、事業に必要な資金需要に幅広く対応できるのがポイント。融資審査も簡略化されているため、スピーディーに資金を調達できる点が魅力です。
通常の金融機関からの借り入れと比べて金利負担が軽いことから、返済負担を大幅に抑えられます。借入額の設定次第では、利子の支払いを掛金の運用益で十分賄えるケースも。実質的な金利負担がほとんどなくなるわけです。
とはいえ、小規模企業共済の貸付制度は、あくまでも経営者の資金繰りを支援する制度。むやみに借金をするのは賢明とは言えません。
事業計画をしっかり立てた上で、資金需要を見極めることが大切。返済計画を綿密に練り、確実に返済できる見通しを立ててから利用するようにしましょう。上手に活用すれば、経営の安定化に役立つこと間違いなしです。
解約手当金制度がある
小規模企業共済には、解約手当金制度があります。これは、共済契約を解約したときに、掛金納付月数に応じて一定の金額が支給される制度です。
掛金納付月数が12ヵ月以上あれば、解約手当金を受け取れます。ただし、解約手当金の額は共済金に比べると低く設定されています。できるだけ長く掛金を納め続け、共済金をもらうことを目指すのが賢明でしょう。
とはいえ、解約手当金制度があるおかげで、万一の時の安心感は高まります。経営環境の変化によって、やむを得ず共済契約を解約するときにも、掛金が全く無駄にならずに済むのは心強いポイントです。
例えば、思いがけない病気やケガで事業の継続が難しくなったケース。あるいは、業績不振に陥り、掛金の負担が厳しくなったケース。こうした予期せぬ事態に直面しても、解約手当金を受け取れる可能性があるわけです。
ただし、この点は二つの解釈があるので注意が必要です。解約手当金の存在を「いざとなったら解約すればいい」と安易に考えるのは禁物。あくまでも、長く掛金を納め続けることを前提に、もしものときの備えとして捉えるべきでしょう。
小規模企業共済のデメリット
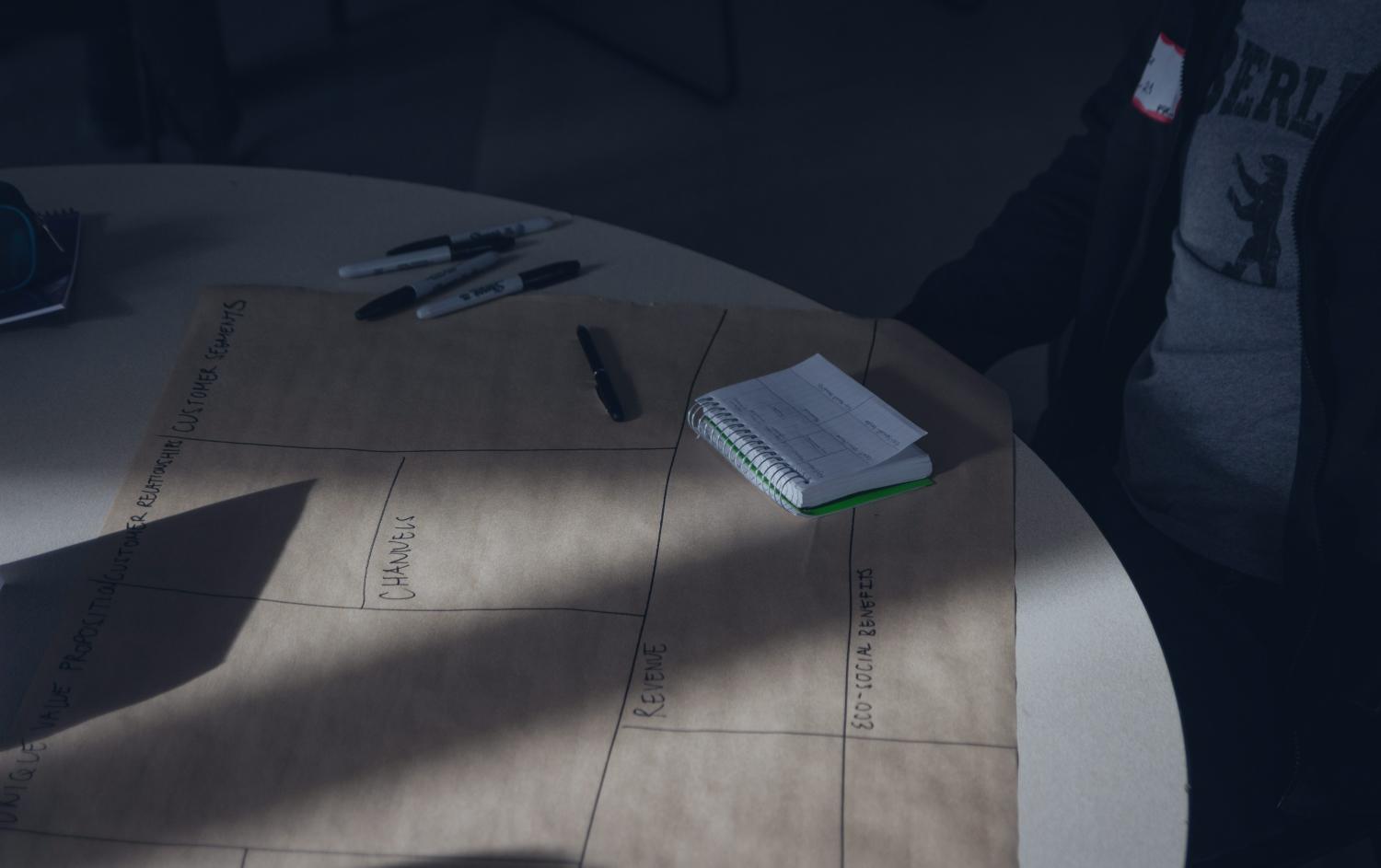
メリットの多い制度ですが、一方でデメリットも存在します。以下の点には注意が必要です。
掛金納付月数が12ヵ月未満だと掛け捨てのリスクがある
共済金を受け取るには、掛金納付月数が12ヵ月以上必要です。12ヵ月未満で脱退すると、掛金は掛け捨てになってしまいます。
これは、制度の仕組み上やむを得ない面があります。掛金納付月数が短いと、運用益があまり見込めないため、共済金の原資が不足してしまうのです。
一定の掛金納付月数を条件とすることで、制度の健全性を保つ狙いがあると思われます。しかし、掛金を納めたのに何ももらえないというのは、加入者にとって痛手であることに変わりはありません。
できる限り長く加入を継続し、掛金納付月数を重ねることが得策。12ヵ月未満での脱退は、本当にやむを得ない場合を除いて避けるべきでしょう。
元本割れのリスクがある
運用利回りによっては、受け取る共済金が納付した掛金の元本を下回る可能性もあります。掛金納付月数が短いと、特にそのリスクが高くなります。
小規模企業共済の掛金は、安全性の高い金融資産で運用されています。預貯金や国債など、元本が保証された商品が中心です。
しかし、金利の低下傾向が続く昨今、運用利回りも低水準で推移しています。物価上昇なども考慮すると、実質的には元本割れのリスクがあると言わざるを得ません。
掛金納付月数が短ければ、その傾向に拍車がかかります。運用益が積み上がる前に共済金を受け取るわけですから、元本割れは避けられないというわけです。
こうしたリスクを防ぐには、少しでも長く掛金を納め続けることが重要。時間をかけて着実に運用益を積み上げていくことで、元本割れの危険性を最小限に抑えることができるはずです。
個人事業税の課税対象になる
共済金を一括で受け取った場合、個人事業税の課税対象になる点には注意が必要です。個人事業税は、事業から生じる所得に対してかかる地方税です。
共済金は、一時所得として所得税と住民税が課税されますが、一括受け取りの場合は事業所得とみなされ、個人事業税も課税されるのです。税負担を軽減するには、共済金を分割で受け取ることを検討しましょう。
分割受け取りであれば、個人事業税の課税は回避できます。一括受取りによる税負担の増加を避けたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
ただし、分割受取りの方が総合課税の対象になるなど、所得税の負担が重くなるケースもあります。加入者の状況に応じて、一括受け取りと分割受取りのメリット・デメリットをよく比較した上で選択する必要があります。
在職中は共済金を受け取れない
小規模企業共済の共済金は、あくまでも事業をやめたり役員を退職したときに受け取れます。在職中は共済金を受け取ることができないので注意しましょう。
一時的な資金需要に対応するには、別の手段を考える必要があります。小規模企業共済の掛金を担保にした貸付制度の利用や、日頃から計画的な資金管理を心がけることが大切です。
事業資金の調達手段としては、前述の貸付制度の他にも、民間金融機関からの借り入れや公的機関の融資制度などを検討してみるとよいでしょう。自社の資金ニーズに合わせて、適切な方法を選択することが重要です。
在職中の共済金受取りができない点は、制度の性質上やむを得ない面があります。小規模企業共済は、あくまでも経営者の退職金の準備を目的とした制度。在職中の資金需要に対応するためのものではないのです。
この点を正しく理解した上で制度を活用し、計画的な資金管理を心がけることが大切だと言えるでしょう。
小規模企業共済への加入方法

小規模企業共済に加入するには、以下の手順を踏みます。
加入に必要な書類
加入に必要な書類は、加入申込書と必要事項が記載された本人確認書類です。
本人確認書類としては、運転免許証やパスポート、住民票などが該当します。記載された住所・氏名・生年月日等によって、申込者の本人確認を行う狙いがあります。
一方、加入申込書には、掛金月額や共済金受取りの方法など、共済契約に関する重要な事項を記入します。内容に誤りがないよう、よく確認しながら記入することが大切です。
また、個人事業主の場合は、事業の実態を確認するための書類の提出を求められることがあります。例えば、開業届や税務署の受付印が押された青色申告決算書などが該当します。
こうした必要書類は、遺漏なく準備しておくことが肝心。不備があると、加入手続きが進まなくなるおそれがあります。
加入手続きの流れ
-
- 地域の商工会・商工会議所や中小企業団体中央会の窓口で、加入相談や手続きを行います。
- 中小企業基盤整備機構から、掛金払込用紙が送付されてきます。
- 掛金を納付し、共済契約が成立します。
窓口での相談の際は、経営状況や将来設計など、できるだけ詳しく情報を伝えるのがポイント。担当者から、加入者に最適なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
掛金の納付は、口座振替かコンビニエンスストアでの支払いから選べます。加入者の利便性を考慮した仕組みになっていますね。
以上の流れを経て、晴れて小規模企業共済の加入者となります。あとは、毎月コツコツと掛金を納めながら、将来に備えていくだけ。気負う必要は全くありません。
事業を継続する傍らで、老後の資金づくりを着実に進めていきましょう。簡単な手続きから、経営者の方の安定した未来への第一歩が始まります。
小規模企業共済と中小企業倒産防止共済の違い
小規模企業共済と似た制度に、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)があります。両者は、ともに中小企業経営者のための共済制度ですが、加入対象や目的が異なります。
中小企業倒産防止共済は、取引先の倒産などの際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための共済制度です。小規模企業共済が経営者の退職金の準備を目的とするのに対し、中小企業倒産防止共済は、あくまでも事業の継続を目的としています。
このように、両制度の性格は大きく異なります。中小企業倒産防止共済への加入は、取引先の倒産リスクへの備えという位置づけ。対して、小規模企業共済はあくまでも経営者個人の老後資金づくりが目的です。
両方の共済に加入することで、退職金の準備と事業の継続の備えを同時に行うことができます。ただし、掛金負担は重くなるので、自社の状況をよく見極めて判断することが肝心です。
小規模企業共済と中小企業倒産防止共済、両者の特性をよく理解した上で上手に活用していきたいものですね。
まとめ
今回は、「小規模企業共済制度」について、詳しく解説してきました。
簡単にポイントを振り返っておきましょう。
-
- 低金利の貸付制度を利用できる
- 小規模企業共済は、個人事業主や会社等の役員を対象にした、経営者の退職金制度
- 掛金は全額所得控除の対象になり、節税メリットがある
- 共済金は退職時に受け取れるが、一括と分割の選択肢がある
- 契約の解約時にも、一定の条件を満たせば解約手当金が受け取れる
- 掛金納付月数が12ヵ月未満だと掛け捨てになるなど、デメリットにも注意が必要
以上のような特徴を持つ小規模企業共済制度。うまく活用することで、経営者の皆様の退職金づくりに大いに役立つことでしょう。
もちろん、加入の判断に当たっては、メリット・デメリットをよく検討することが大切です。自社の経営状況を見極めつつ、長期的な視点を持って検討を進めましょう。
老後資金の確保は、経営者にとって重要な課題です。小規模企業共済制度を上手に活用しながら、着実な準備を進めていただければと思います。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。