非上場株式の売却に必要な基礎知識|手続きの流れ・注意点・税金などを解説
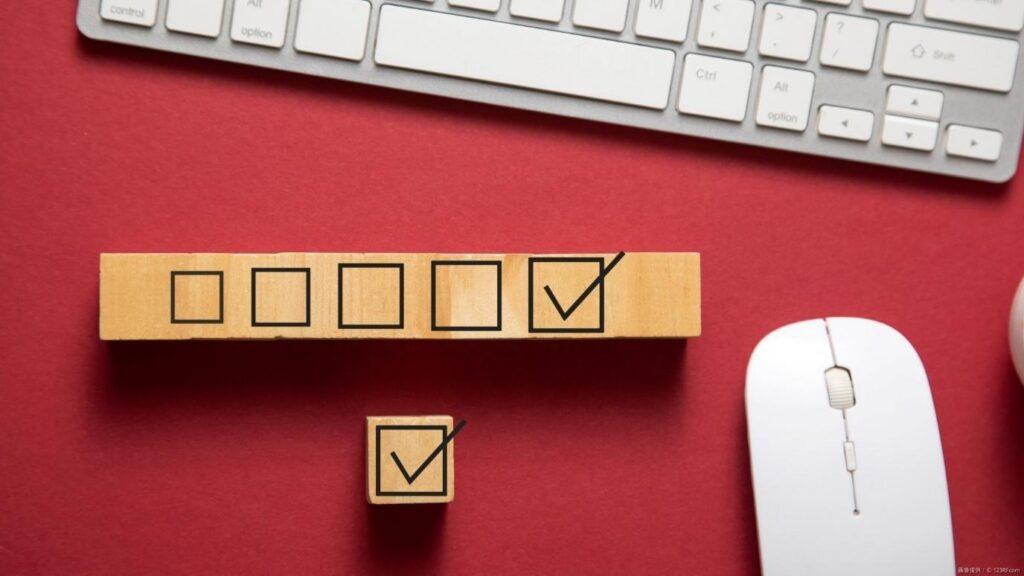
非上場株式の売却(譲渡)は、中小企業の事業承継などで行われます。ご自身の持つ非上場株式を売却する際に、どのような知識が必要なのか、またデメリットや注意点はないのか気になっている方もいるでしょう。
そのため今回こちらの記事では、非上場株式の売却に必要な基礎知識として、手続きの流れや注意点、発生する税金などをわかりやすく解説します。
目次
非上場株式とは?
非上場株式とは、東証やナスダックといった証券取引所で公開していない株式のことです。JPX日本取引所グループによると、2024年3月25日時点の上場会社数は3,932社となっています。総務省統計局の「我が国の事業所・企業の経済活動の状況~令和3年経済センサス-活動調査の結果から〜」によると、2022年6月1日時点の企業等の数は368万企業です。また、中小機構によると、中小企業の数は約336万社となっています。
中小企業が多い日本では、ほとんどの企業の株式が非上場株式にあたります。一方、他人に譲渡されると困るなどの理由から、会社の許可なく譲渡できない譲渡制限を設けている株式のことを未公開株と言います。本来は「未公開株=非上場株式」ではありませんが、日本国内では中小企業が多いことから「未公開株=非上場株式」が成り立つとも言われています。
出典:JPX日本取引所グループ「上場会社数・上場株式数」
中小機構「日本を支える中小企業」
総務省統計局「我が国の事業所・企業の経済活動の状況 令和3年経済センサス〜活動調査の結果から〜」
非上場株式と上場株式の違い
非上場株式とは証券取引所で公開されていない株式のことです。一方、上場株式は証券取引所で公開している株式を指します。つまり非上場株式と上場株式の違いは、市場で取引されているか、いないかです。
上場株式は、証券取引所で誰でも自由に売買することができる一方、非上場株式は上場していないため自由に売買することはできません。ただし売買できないわけではなく、自分で買主を見つけることができれば可能です。
非上場株式を売却するメリット
非上場株式を売却する際の主なメリットは、以下の4つが考えられます。
- 資金調達ができる
- 相続より税金を低く抑えられる
- 後継ぎ問題の解消
- 創業者利益の獲得
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
資金調達ができる
非上場株式を売却することで、資金を獲得することができます。例えば、経営者が保有する株式を売却し、その資金をもとに新しい事業を始めたり、既存の事業のさらなる成長のために使ったりできます。株式を新たに発行して、投資家に出資してもらう「増資」も一つの方法です。
特に、成長が期待できる事業を行っていたり、経営状態が良好な企業は市場で取引するよりも高い評価を受ける可能性があります。そのため、将来性のある成長企業の非上場株式は高値で取引されることもあります。
相続より税金を低く抑えられる
非上場株式を相続するよりも売却した方が税率が低いケースがあり、節税になる可能性があります。相続税は、以下のように取得金額(評価額)に応じて税率が上がる累進課税方式が採用されています。
| 法定相続の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように、相続した非上場株式の取得金額によって最大で55%の税率がかかります。一方、株式を譲渡(売却)した際に利益が出た場合は所得税が発生し、税率は以下の通りです。
- 個人の場合:20.315%(所得税15%+復興特別税0.315%+住民税5%)
- 法人の場合:29~42%(法人税等)
最大税率を比較すると相続税の方が高く、相続するよりも売却した方が節税になると考えられます。例えば、5億円の非上場株式を相続した場合の税率は50%ですが、個人として株式を売却した場合の税率は20.315%であり、節税になります。
ただし、取得金額によっては相続税の方が税率が低くなるケースがあるので注意が必要です。一般的には、非上場株式の評価額が1億円超の場合に、相続するよりも売却した方が税金が低くなると考えられます。また、非上場株式を売却した後の現金を相続すると相続税が発生するため、ケースバイケースで状況に合った節税方法を見つけるようにしましょう。
出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」
国税庁「No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
後継ぎ問題の解消
国内の中小企業では、経営者の高齢化により、後継者がいないという問題に直面しているケースがあります。帝国データバンクが2023年11月に公表した「全国『後継者不在率』動向調査(2023年)」によると、後継者の不在率は53.9%(前年比3.3%減)です。親族以外への承継が増えているため過去最低の数値となりましたが、それでも半数以上の企業は後継者が不在の状態となっています。
会社の経営権に法律上の定めはありませんが、議決権の割合で判断することが一般的です。つまり、議決権のある株式の1/2以上を保持している場合に、経営権を保持していると見なされます。そのため全株式の1/2以上を譲渡することで経営権が移り、企業や事業の承継ができます。
出典:帝国データバンク「全国『後継者不在率』動向調査(2023年)」
創業者利益の獲得
創業者利益とは、非上場株式の譲渡などに伴って得られる創業者の利益のことです。創業者利得とも言われます。創業時の資本金との差額にあたり、会社を創業した経営者における大きなメリットとされます。非上場株式の場合は、主にM&Aなどで株式譲渡(会社売却)をすることで得られます。当然、創業時よりも会社規模が大きくなっていたり、事業が拡大していると創業者利益はより高額になります。
創業者利益は、起業のリスクを抱えながら事業を成功させた創業者への見返りという捉え方もあります。そのため、創業者利益の獲得を目指して起業を繰り返す連続起業家(シリアルアントレプレナー)も存在します。
非上場株式を売却するデメリット
非上場株式を売却することにはメリットがある一方、デメリットもあります。
- 債務など全ての資産を継承する必要がある
- 簿外債務などリスクがある可能性
- 非上場株式売却時の税金
- 譲渡制限株式への対応
以上の主な4つのデメリットについて、詳しく解説します。
債務など全ての資産を継承する必要がある
非上場株式を譲渡(売却)する場合、譲渡を受けた側の株式保有率が50%以上になると会社の経営権が移ることになります。この場合、資産や負債に変動はありませんが、発行済みの全株式を譲渡する場合は資産はもちろん、債務といった負債など会社の全てが譲渡を受けた側に承継されます。
そのため特定の資産や権利、事業を残したい場合は、株式譲渡ではなく事業譲渡や会社分割などの他の手法を選ぶ必要があります。株式譲渡をした後に、資産買い戻しをするといった方法もあります。
簿外債務などリスクがある可能性
非上場株式の譲渡を受けた側には、発行済みの全株式を譲り受けることによって資産だけではなく負債や賠償なども譲渡されるため、リスクを抱える恐れがあります。
また、簿外債務のほか、不採算事業などを抱えている場合は株式譲渡が成立しない、譲受希望者が見つかりにくい、譲渡価額が下がるといった可能性もあります。
非上場株式売却時の税金
前述の通り、非上場株式の譲渡(売却)には税金が発生し、売却後に納税する必要があります。ただし発生する税金は個人間の譲渡、個人と法人の間による譲渡などケースによって異なり、これについては後述します。
個人間による譲渡の場合、税率は一律で20.315%(所得税:15%、復興特別税:0.315%、住民税:5%)です。ただし、譲渡価額が著しく低い場合(時価の1/2未満)、贈与とみなされて買主には贈与税がかかります。これが「みなし贈与課税」です。
一方、個人が保有している非上場株式を法人に売却する場合、譲渡価額が著しく低いとみなし譲渡があったものとして、譲渡した個人には税務上の時価をベースに所得税が課せられます。これを「みなし譲渡課税」と言います。
なお、法人が保有する非上場株式を第三者に譲渡した場合は法人税等(法人税、法人住民税、事業税)が発生します。
譲渡制限株式への対応
非上場株式には譲渡制限が設けられているものが多く、制限への対応がなければ譲渡することはできません。一般的には、意図しない第三者に経営参画させないように「株主総会において承認を得ないと譲渡できない」といった制限が設けられています。この場合、譲渡先を見つけたとしても株主総会で承認手続きを経なければ譲渡は実行できません。
譲渡制限株式の譲渡を進めるためには、譲渡希望者が株式譲渡承認請求を提出し、受け取った企業が取締役会(あるいは株主総会)を開催します。その際、否決される可能性もあります。
非上場株式を売却する流れ
非上場株式を売却するには基本的な流れがありますが、ここでは非上場株式の株式譲渡によってM&Aを進める場合について解説します。一般的には以下のような流れで進めます。
- 1.株主が保有している非上場株式の集約
- 2.譲渡制限の有無の確認
- 3.非上場株式の買い手候補を探す
- 4.非上場株式の買い手との交渉と合意
- 5.非上場株式の譲渡承認の請求
- 6.株主総会・取締役会などでの決議
- 7.非上場株式の譲渡契約を結ぶ
- 8.非上場株式の売却にかかる代金の決済
- 9.株主名簿の書き換え
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1.株主が保有している非上場株式の集約
売り手企業の非上場株式は、経営者が100%保有しているケースや家族で分散して保有しているケースばかりではなく、少数株主が複数いるケースもあります。この場合、株主が保有している株式を事前に集約しておくことが重要です。一般的に株主譲渡によるM&Aでは、100%の株式を譲渡することが多いためです。
集約がうまくいかない場合、M&Aの成立が遅れることになり、場合によっては失敗することも考えられます。
2.譲渡制限の有無の確認
次に行うのは、譲渡制限が設けられているかどうかの確認です。前述したように、非上場株式には、譲渡に条件がついている譲渡制限が設定されているケースがあります。
会社法では「譲渡に株式会社の承認を要する際は、定款にその旨を記載しなければならない」と規定しており、定款に「株式を譲渡する場合は、株主総会の承認が必要」といった記載がある場合は株主総会での承認が必要になります。また、株式譲渡制限は登記事項です。そのため、登記簿謄本か登記簿にある「株式の譲渡制限に関する規定」の項目でも確認することができます。
3.非上場株式の買い手候補を探す
非上場株式を売却するには買い手企業が必要です。このタイミングで買い手候補を探すのではなく、「1.株主が保有している非上場株式の集約」よりも前に始まっていることもあります。中には、買い手候補企業からのアプローチがあった後に、1.を始めることもあります。
この段階で買い手候補が見つかっていなければ、身の回りの個人投資家やM&A仲介会社、マッチングサービスなどを通じて買い手候補企業を探します。条件がある場合は仲介会社などに伝え、ロングリストやショートリストなどで候補の絞り込みを行います。
4.非上場株式の買い手との交渉と合意
買い手候補企業が見つかった後は交渉に入り、売却に関する条件を調整していきます。具体的な交渉内容は、売却金額や従業員や役員の待遇、取引先の取り扱いなどです。条件面での折り合いがある程度ついた段階でトップ面談を行い、基本合意の締結を行います。
基本合意書には、譲渡日や取引価格、M&Aの取引形態などの内容が盛り込まれます。締結後は、最終契約に向けてデューデリジェンスを実施して詳細に条件を詰めていきます。最終契約に合意した後、クロージング→経営統合(PMI)と進んでいきます。
5.非上場株式の譲渡承認の請求
非上場株式に譲渡制限が設けられている場合は、株式譲渡の承認を請求します。譲渡承認の請求手続きは、株式を譲渡しようとする株主が会社に対して「株式譲渡承認請求書」を提出することで行います。
株式譲渡承認請求書には「譲渡しようとしている譲渡制限株式の数」と「譲り受ける者の氏名または名称」などを記載する必要があり、一般的には株主と譲受人が協力して作成します。また、会社が譲渡を承認しない場合に、会社や指定買取人が株式を買い取ることを請求する場合はその旨も記載しておきます。
6.株主総会・取締役会などでの決議
株式譲渡承認請求書の提出を受けた会社は、取締役会(取締役会を設置していない会社は株主総会)を開催します。この際の決議は、普通決議で決定します。以下が必要な定足数と決議要件です。
- 議決権総数の過半数の株式を有する株主が出席する
- 出席株主の議決権の過半数を獲得する
株式譲渡承認請求書の提出を受けた会社は、承認請求者への結果通知を2週間以内に行う必要があります。2週間以内に結果の通知を行わなかった場合は、譲渡は承認されたとみなされます。
なお、承認されなかった場合は、株式譲渡承認請求書の記載に則って会社または指定買取人が非上場株式を買い取ります。
7.非上場株式の譲渡契約を結ぶ
非上場株式の譲渡が承認された場合は、株主と譲受人との間で株主譲渡契約書の締結を行います。契約書には以下の内容を記載するのが一般的です。
- 株式の種類と数
- 取引価額
- 譲渡日
- 誓約事項
- 表明保証
- クロージング条項、など
なお、譲渡代金の決済方法についても事前に話し合っておくことが大切です。
8.非上場株式の売却にかかる代金の決済
株式譲渡契約書に則って、買い手企業が譲渡日までに取引価額の決済を行います。銀行振込で行われるのが一般的です。
一方、売り手企業からは株式の引き渡しを行います。ただし、多くの非上場企業では株券を発行せず、株主の管理は株主名簿で行っています。この場合、代金の決済をした時点で株式譲渡は成立します。
9.株主名簿の書き換え
代金の決済によって株式譲渡は成立しますが、第三者に対応するために行うのが株主名簿の書き換えです。名簿の書き換えが行われないと、配当金の受領や株主総会での議決権行使といった株主権を行使することができません。
株主名簿の書き換えは、決済を確認した後に株主と譲受人が共同で「株主名簿書換請求書」を作成し、会社に提出する流れが一般的です。
非上場株式を売却する際の評価方法
非上場株式は市場で取引をしていないため、取引価額を決める際には基準となるものが必要です。国税庁は以下3つの方式を定めています。
- 類似業種比準方式
- 純資産価額方式
- 配当還元方式
類似業種比準方式と純資産価額方式は原則的評価方式、配当還元方式は特例的評価方式と呼ばれます。原則として、同族株主等が株式を取得した場合は原則的評価方式、それ以外の株主が取得した場合は特例的評価方式が採用されます。それぞれの方式について、詳しく解説します。
類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、評価対象会社と類似した業務を行う上場企業の株価を参考に、株式の価格を決定する方式です。従業員が70人以上の企業において、原則として同族株主等が株式を取得する場合に用いられます。
具体的には、評価対象会社に類似する上場企業における1株あたりの配当金額、利益金額、純資産価額を参考にして評価対象会社の株価を計算します。ただし、純資産価額方式で算出した株価が、類似業種比準方式で算出した株価より低い場合は、純資産価額方式で算出した株価が採用されることになります。
純資産価額方式
純資産価額方式とは「現時点で会社を解散した場合、総資産を売却するといくら利益が出るのか」という考えのもとで評価対象会社を評価する方式です。具体的には、評価対象会社の総資産と総負債を財産評価基本通達に基づいて評価した上で算出した純資産価額を発行済み株式数で割り、1株あたりの価値を算出します。
例えば、今すぐ会社を解散した場合、発行済み株式が100株・総資産が100万円だったとすると、1株あたりの評価額は1万円になります。主に中小企業の株式取引で、原則として同族株主等が株式を取得する場合に用いられます。
配当還元方式
配当還元方式とは「非上場株式を保有していることで1年間の配当金はどれくらいになるか」という考え方で評価対象会社の評価を行います。計算する際は「1株あたりの資本金等を50円としたときの株式数」を用います。計算式は以下の通りです。
配当還元価格=1株あたりの年間配当金÷10%×1株あたりの資本金等の額÷50円
1株あたりの年間配当金は、直近決算期2期分で行った配当の平均を算出します。主に中小企業の株式取引で、原則として同族株主等以外の株主が株式を取得する場合に用いられる評価方式です。
非上場株式を売却する際にかかる税金
非上場株式を売却する際は、前述した通り税金が発生します。発生する税金の種類は、取引の形態によって異なります。取引の形態は、大きく分けると以下の4通りがあります。
- 個人が個人に売却するケース
- 個人が法人に売却するケース
- 法人が法人に売却するケース
- 法人が個人に売却するケース
詳しく解説していきます。
税金の種類
非上場株式を譲渡(売却)する際にかかる主な税金の種類は以下の通りです。
| 税金の種類 | 概要 |
| 譲渡所得税 | 個人が株式を譲渡した際に得られる所得に課せられる税金です。所得税、復興特別所得税、住民税の3つに分類されます。 |
| 法人税 | 法人が利益を上げた際に課せられる税金です。法人税、法人住民税、法人事業税を合わせて法人税等と表記されるのが一般的です。 |
| 相続税・贈与税 | 個人が非上場株式を贈与するときには贈与税、相続するときには相続した人に相続税が課せられます。 |
なお、個人から法人に非上場株式を売却した際、著しく低額の場合はみなし譲渡所得税、個人間で非上場株式を著しく低額で売却した場合はみなし贈与税が課せられるのが一般的です。
個人が売却するケース
個人間による譲渡の場合、税率は一律で20.315%(所得税:15%、復興特別税:0.315%、住民税:5%)です。ただし、売却価格に対してかかるのではなく、譲渡所得にかかります。譲渡所得とは、取得費などを差し引いた金額です。計算式は以下の通りです。
譲渡所得=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+譲渡費用)
例えば、譲渡価額が500万円、売却手数料などの譲渡費用が100万円とした場合、譲渡所得は400万円となります。税金は400万円に20.315%を乗じた金額になります。ただし、譲渡価額が著しく低い場合(時価の1/2未満)、贈与と見なされて買主には贈与税がかかります。これが「みなし贈与課税」です。
また、個人が保有している非上場株式を法人に売却する場合、譲渡価額が著しく低いとみなし譲渡があったものとして、譲渡した個人には税務上の時価をベースに所得税が課せられます。これを「みなし譲渡課税」と言います。
法人が売却するケース
法人が保有する非上場株式を第三者に譲渡した場合、法人税等(法人税、法人住民税、法人事業税)が発生します。法人税の税額は、個人のケースと同様に売却した価額から取得費用を差し引いてから税率を乗じて求めます。以下が計算式です。
法人税=総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+譲渡費用)×税率
法人税は、利益額などによって変動する累進課税で税額が決まります。また、株式の売却の際には法人の規模、事業年度、年間法人所得によって税率が変動し、さらに法人事業税は地方税のため都道府県によって税率が異なります。そのため法人税等の税率は一律ではなく、29~42%と幅があります。
非上場株式を売却する際の注意点
非上場株式を売却する際の主な注意点は以下の通りです。
- 低額・無償で譲渡すると税金が課される
- 時価より高額で譲渡すると税金の扱いが変わる
- みなし配当の発生
詳しく解説します。
低額・無償で譲渡すると税金が課される
非上場株式の売却でまず注意すべき点は、無償あるいは低額で売却した際にも税金が課されることです。株式に関わらず、資産を無償または低額で譲渡した場合、時価で売却したとみなして課税されます。
具体的には以下のケースが考えられます。
- 個人が資産を無償で譲渡した場合…みなし贈与税
- 個人が法人に資産を著しく低額で譲渡した場合…みなし譲渡所得税
「著しく低額」とは時価の1/2未満とされていますので、非上場株式を売却する際には注意しましょう。
時価より高額で譲渡すると税金の扱いが変わる
非上場株式を時価より高額で譲渡する場合も、無償や低額で譲渡する際と同様に課税されることになります。この場合、課税の仕組みが複雑になるため、注意しましょう。
例えば、個人に対して非上場株式を譲渡する際に時価を上回る場合、時価に対して譲渡価格が上回る分に贈与税がかかります。さらに、時価から取得額を差し引いた金額には所得税が発生します。
また、法人に対して非上場株式を譲渡する際に時価を上回る場合も注意が必要です。譲渡価格から時価を差し引いた金額に対して贈与税はかからず、給与所得や課税所得扱いとなります。
みなし配当の発生
みなし配当とは、配当として受け取っていなくても、実質的に利益が発生したとして税務上は配当とみなして課税することです。合併、分割型分割、株式の分配、資本の払い戻し、資本剰余金による配当金、自己株式の取得、出資の消却や払い戻し、組織変更などさまざまなシーンでみなし配当課税が発生する可能性があります。
典型的なものは、非上場株式を発行会社に譲渡するケース(自己株式の取得)です。通常の株式譲渡とは異なり、一部配当金相当額が含まれていると解釈され、課税されることになります。
非上場株式を売却した際に確定申告は必要?
非上場株式を売却した際に譲渡益がある場合は、確定申告を行う必要があります。所得税は利子所得や給与所得などの所得を合算して申告する総合課税が原則ですが、個人が非上場株式を譲渡した場合は総合課税ではなく、他の所得と分離する申告分離課税になります。
個人の場合の確定申告は、原則として非上場株式の売却によって利益を得た翌年の2月16日〜3月15日の間に行います。申告は、収入金額や所得金額などを記した「確定申告書B第一表・第二表」、「確定申告書第三表(分離課税用)」を使用して行います。同時に譲渡所得の金額を「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を用いて計算し、提出します。
確定申告の方法は、国税電子申告・納税システム「e-Tax」の利用のほか、国税庁の確定申告作成コーナーでの提出、税務署への持参・郵送などがあります。申告方法によって、マイナンバーカード、身分証明書などの必要書類が異なるため、事前に調べましょう。
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
まとめ
保有する非上場株式を売却する際の基礎知識を詳しく解説しました。経営者がM&Aなどで自社の非上場株式を売却する場合、特に気をつけたい点が取引価格です。創業者利益を手にすることができますが、納税額が大きくなることも考えられます。
適切な知識を持ち、自社にとって不利にならないように非上場株式の売却を進めるようにしましょう。M&Aや非上場株式の売却などで不安や悩みがある場合は、専門家への相談も検討してください。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


