解散登記の手続き方法とは?必要書類について解説
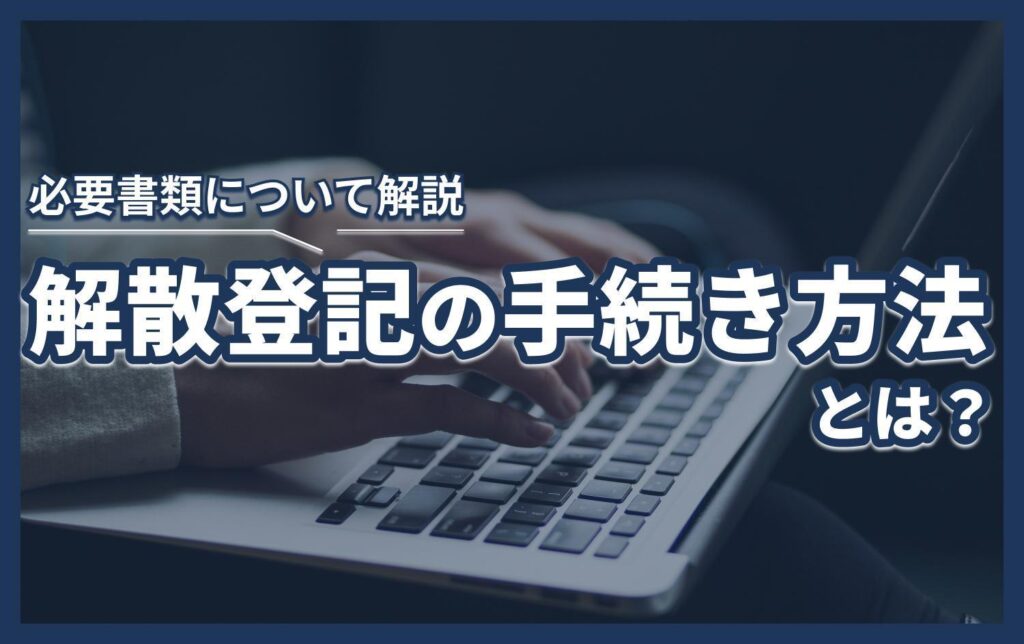
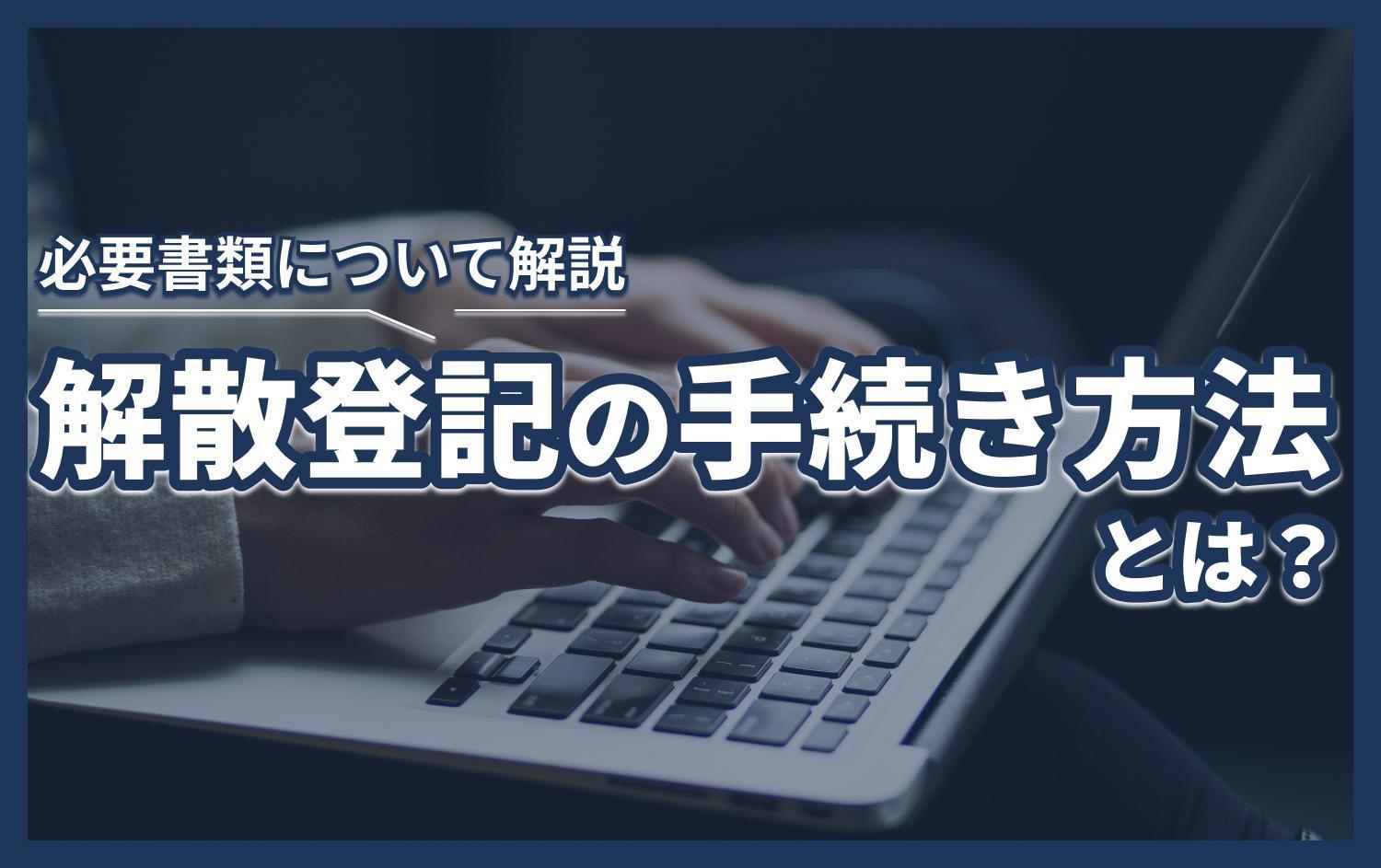
事業の行き詰まり、経営者の高齢化、後継者不在など、解散を検討せざるを得ない状況に直面することは珍しくありません。
そんな時、頭を悩ませるのが解散登記の手続きです。何から始めればよいのか、どんな書類が必要なのか、専門家に依頼するべきなのか…。
疑問や不安が尽きないのではないでしょうか。しかし、解散登記は会社の法的な消滅に関わる重要な手続きです。適切に進めなければ、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そこで本記事では、解散登記に関する基本的な知識から、具体的な手続きの流れ、かかる費用、注意すべきポイントまでを丁寧に解説いたします。解散登記の全体像を把握し、円滑に手続きを進めるためのヒントが得られるはずです。
解散登記とは何か?
解散登記とは、会社の法人格を消滅させるための登記手続きのことです。会社を清算し、債権者への支払いを完了した後、最終的に行う登記が解散登記にあたります。この登記が完了して初めて、会社は法律上の存在ではなくなるのです。
解散登記が必要となるケースはいくつかあります。事業の継続が困難になった場合、経営者の死亡や高齢化により後継者が不在の場合、株主総会で解散が決議された場合などです。自主的に解散を決定したケースでは、清算手続きを経て解散登記に至ります。
一方、倒産により破産手続きを行った場合は、破産手続きの完了をもって解散したとみなされ、清算を経ずに直ちに解散登記を行うことになります。
ここで注意したいのが、解散と清算結了の違いです。解散とは、会社の権利能力を失わせる原因となる事実が発生した状態を指します。一方、清算結了とは、清算手続きが全て完了した状態を意味します。つまり、解散後に清算手続きを行い、清算が結了した段階で解散登記を行うことになるのです。
解散登記の必要書類
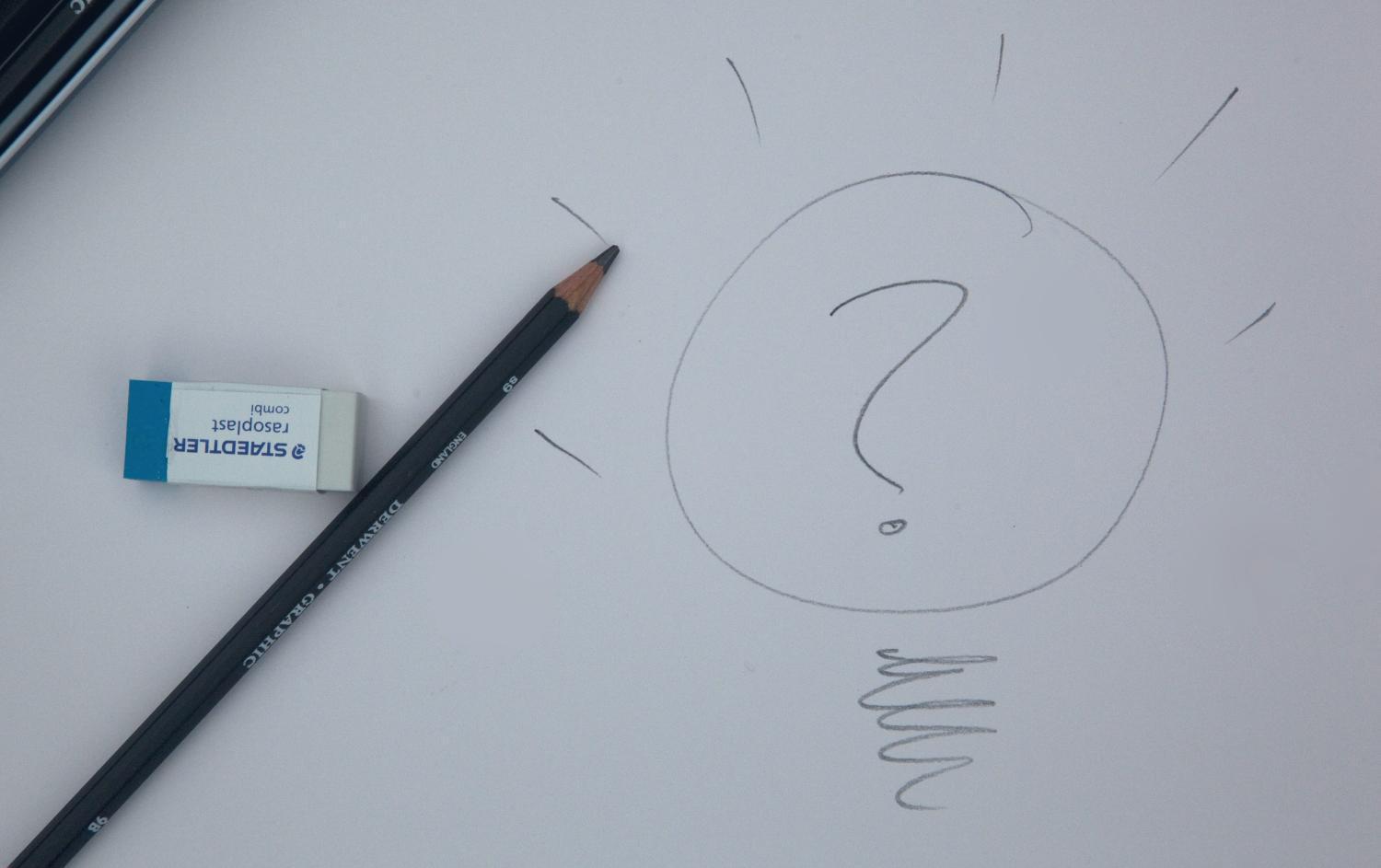
解散登記を行うには、以下の書類を登記所に提出する必要があります。
-
- 登記申請書:解散登記の申請書に必要事項を記入し、代表清算人が記名押印します。
- 解散事由を証する書面:株主総会の議事録、解散を決定した書面など、解散の事由を証明する書類が必要です。
- 清算人の就任を証する書面:清算人の選任を証する株主総会の議事録などが該当します。清算人の氏名、住所、就任日などを記載します。
- 官報公告に関する書面:解散と清算人に関する事項を官報に公告した際の官報紙面の写しを添付します。
- 債権者に対する異議申述の催告に関する書面:債権者に対して行った債権申述の催告について、個別通知の送付先リストや、債権者集会の開催を証明する書類などを準備します。
- 清算人の印鑑証明書:清算人の印鑑証明書を取得し、申請書に添付します。
- 登録免許税の領収証書:登録免許税を納付し、領収証書を申請書に添付します。
これらの書類を揃えるためには、事前の準備が欠かせません。株主総会の開催、債権者への通知など、一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
株主総会の開催に当たっては、解散の決議と清算人の選任を行います。定款の定めに従って招集通知を発送し、議事録を作成します。決議の際は、解散の時期や清算人の報酬なども合わせて決定しておくとスムーズです。
債権者への通知は、官報公告と個別通知の2つの方法で行います。官報公告は、官報掲載申込書に必要事項を記入し、掲載料を納付して行います。個別通知は、債権者に対し、債権申述の催告を行います。債権者リストを整理し、書面で通知を発送しましょう。
解散登記の費用と期限
解散登記にかかる費用は、主に登録免許税と印紙代です。登録免許税は3万円です。
印紙代は、申請書の種類によって異なります。その他、定款変更などに係る書類にも、それぞれ印紙代が発生します。
これらの費用の他にも、清算人の報酬、債権者集会の開催費用、弁護士や司法書士への報酬など、様々な費用が発生します。予め資金計画を立てておくことが大切です。
解散登記の申請期限は、解散が決まった日から2週間以内と定められています。期限を過ぎると、過料の対象となる可能性があります。過料の金額は、100万円以下と定められています。期限を守れないやむを得ない事情がある場合は、事前に登記所に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。
専門家への依頼と費用
解散登記の手続きは複雑で、ミスが許されません。一つの書類の不備や手続きの遅れが、大きなトラブルに発展する可能性があります。例えば、債権者への通知が不十分だった場合、債権者から異議を申し立てられ、清算が難航するリスクがあります。
このようなリスクを回避するためにも、専門知識を持った司法書士や弁護士に依頼するのも一つの方法です。解散登記の経験が豊富な専門家であれば、的確なアドバイスやサポートが得られるはずです。報酬は事務所によって異なりますが、一般的には20万円から50万円程度が相場と言えるでしょう。
解散・清算人の登記を自分で行うデメリット
手間と時間がかかる
登記申請に必要な書類の準備など、一連の手続きには時間と手間がかかります。登記申請の方法に不慣れな場合、書類の不備などで手戻りが発生する可能性もあります。
専門的な知識が必要
解散・清算人の登記は、会社法や登記に関する専門的な知識が必要となります。知識不足のまま登記申請を行うと、不備が生じるリスクがあります。
トラブル発生時の対応が困難
登記申請の際に問題が発生した場合や、登記所から補正を求められた場合など、トラブルが発生する可能性があります。
専門家に依頼していれば、そのようなトラブルにも適切に対応してもらえますが、自分で行う場合は、対応が難しいケースもあります。
解散・清算人の登記は、自分で行うことも可能ですが、専門的な知識と時間が必要となります。
費用を節約できるメリットがある一方で、手続きの不備やトラブル発生時の対応の難しさがデメリットとして挙げられます。
自力で手続きを進めるか、専門家に任せるかは、経営者の皆様の判断次第です。ただし、リスクを最小限に抑え、円滑に手続きを進めるには、専門家の力を借りるのが賢明と言えるでしょう。
債権者保護手続きの重要性

解散登記の前に、債権者保護手続きを適切に行うことが極めて重要です。具体的には、官報への公告、知っている債権者への個別通知、債権者集会の開催などが必要となります。
官報公告は、解散の事実と債権申述の催告に関する事項を官報に掲載する手続きです。個別通知は、知っている債権者に対し、債権申述の催告を書面で通知する方法です。債権者集会は、債権者に対し、債権の申述や清算人の選任などについて協議する場を設けるものです。
これらの手続きを怠ると、債権者から異議を申し立てられ、清算手続きが円滑に進まないリスクがあります。債権者から異議が出された場合、清算人は異議の内容を検討し、債権者との協議を行う必要があります。協議が整わない場合は、裁判所に判断を仰ぐこともあります。
債権者保護手続きは面倒に感じるかもしれませんが、トラブルを防ぐために必ず実施しなければならない重要な手続きです。漏れのないよう、丁寧に進めていきましょう。
解散登記後の手続き
解散登記が完了しても、その後に行うべき手続きがいくつかあります。主なものは、清算所得の申告と清算人の責任に関する手続きです。
清算所得の申告とは、清算中の各事業年度の所得と、清算所得に対する法人税の申告を行うことです。清算所得とは、解散した事業年度の翌日から清算結了の日までの期間における所得を指します。この申告は、清算結了の日から2ヶ月以内に行う必要があります。
清算人は、清算結了後も一定の責任を負います。具体的には、清算人の職務に関する帳簿や書類について、清算結了の日から10年間、保存する義務があります。この間、債権者や株主から閲覧の請求があった場合は、これに応じなければなりません。
また、清算結了後に新たな債権者が現れた場合、清算人は債権者に対し、弁済の責任を負います。ただし、その債権者が清算手続き中に債権の申述をしなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
事業承継の可能性も検討を
会社の解散を検討する際、事業承継やM&Aの可能性についても考えてみましょう。事業承継は、会社の事業を引き継ぐ後継者を見つけ、バトンタッチする方法です。M&Aは、会社の株式や事業を他社に売却し、経営資源を引き継いでもらう方法です。
事業承継の方法には、親族内承継、役員・従業員承継、第三者承継などがあります。親族内承継は、経営者の子供や親族に事業を引き継ぐ方法です。役員・従業員承継は、会社の役員や従業員が後継者となる方法です。第三者承継は、外部の第三者に事業を譲渡する方法です。
M&Aにも様々な種類があります。株式譲渡は、会社の株式を買主に譲渡する方法です。事業譲渡は、会社の事業を丸ごと買主に譲渡する方法です。会社分割は、会社の事業の一部を切り出し、新しい会社を設立する方法です。
事業承継やM&Aのメリットは、会社の事業を存続できる点です。会社の解散を選択すると、事業は消滅してしまいます。しかし、事業承継やM&Aであれば、事業を引き継ぐことができます。また、従業員の雇用を守ることもできます。
一方、デメリットもあります。事業承継の場合、後継者の育成に時間がかかることがあります。M&Aの場合、買主を見つけるのに時間と労力を要します。また、企業価値の評価や条件交渉など、専門的な知識が必要となります。
事業承継やM&Aを成功に導くには、綿密な計画と準備が欠かせません。早めに準備を始め、専門家のアドバイスを仰ぎながら、最良の選択を目指しましょう。
最後に
解散登記を行う際、経営者には大きな負担がかかります。多くの決断を迫られ、ストレスも溜まりがちです。そんな時こそ、心の健康に気を付けることが大切です。
周囲の支えを上手に活用することも重要です。一人で抱え込まずに、家族や友人、専門家など、信頼できる人に相談しましょう。客観的な意見を聞くことで、新しい視点が得られるかもしれません。
従業員とのコミュニケーションも欠かせません。解散の決定は従業員にとって大きな不安材料です。経営者は従業員の不安に耳を傾け、誠実に向き合う必要があります。
解散の理由や今後の見通しを丁寧に説明し、理解を求めましょう。
また、従業員の再就職支援にも力を尽くすことが大切です。解散後の従業員の行き先について、できる限りの支援を行いましょう。再就職先の紹介、推薦状の作成、求人情報の提供など、様々な方法があります。従業員の未来を思い、最後まで責任を持つ姿勢が求められます。
解散登記は、経営者にとって身を切るような辛い決断かもしれません。しかし、その先には新しい道が開けているはずです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


