キャッシュフローが悪い場合の対処法とは?M&Aも視野に入れよう
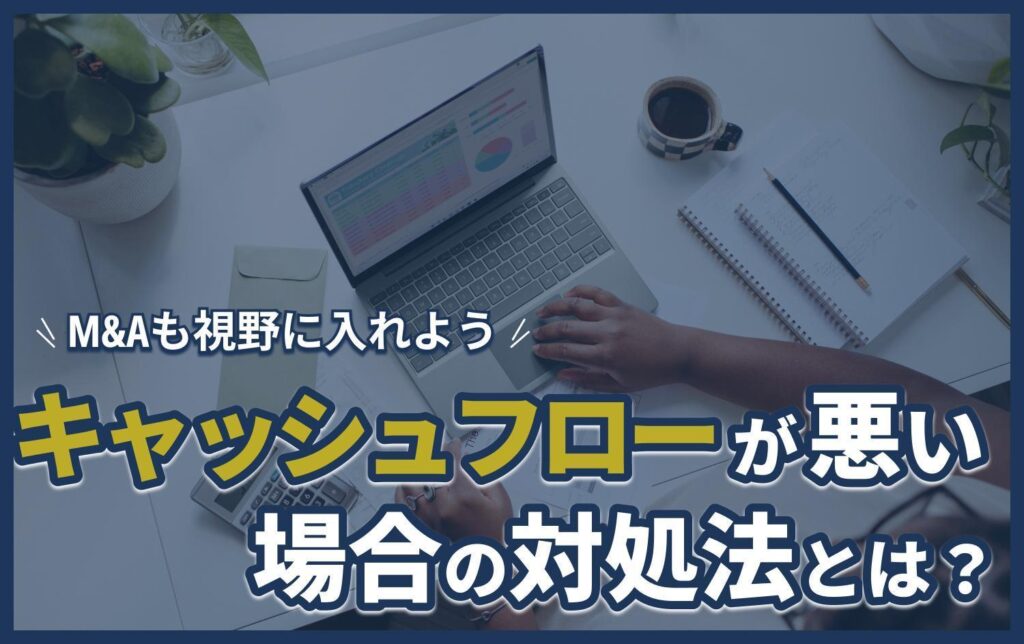
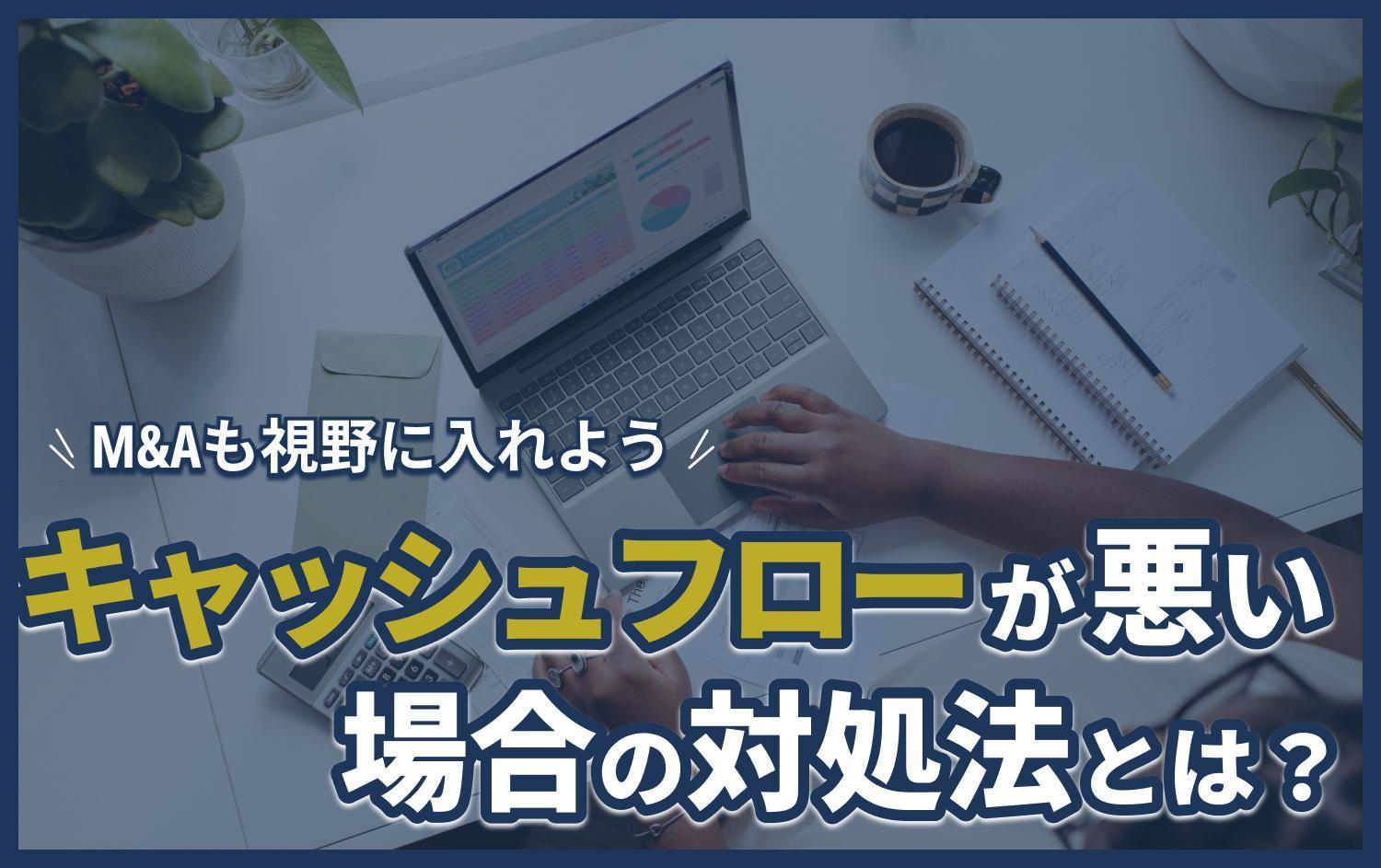
キャッシュフローが悪化していると感じていらっしゃいませんか。
キャッシュフローとは、簡単に言えば、会社に出入りするお金の流れのことです。売上から仕入れや経費を差し引いた残額が、手元に残るキャッシュになります。
このキャッシュが不足すると、日々の運転資金が回らなくなり、事業継続が困難になります。銀行からの借り入れが難しくなったり、支払いが遅れたりと、経営の自由度が失われていくのです。
事業を続けるには、安定したキャッシュフローの確保が不可欠です。
しかし、予期せぬ出来事によって、キャッシュフローが悪化するリスクは常につきまといます。
本記事では、キャッシュフローの悪化を防ぎ、改善するための具体的な方法について解説していきます。キャッシュフロー経営の重要性を再認識し、自社の体質強化につなげていきましょう。
そもそもキャッシュフローとは?
キャッシュフローとは、一定期間における企業の現金の収支を表す指標です。売上などで入ってくるお金(キャッシュイン)と、仕入れや経費などで出ていくお金(キャッシュアウト)の差額が、キャッシュフローになります。
キャッシュフローは、「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」の3つに分類されます。このうち、本業の売上や仕入れに関わるのが「営業活動によるキャッシュフロー」です。
営業活動でプラスのキャッシュフローが生み出せれば、設備投資や借入金の返済など、他の活動に必要な資金を賄えます。逆に、営業活動でキャッシュが不足すれば、手元資金が枯渇し、事業の継続が危ぶまれます。
キャッシュフロー経営とは、こうしたキャッシュの流れを重視し、収支のバランスを取る経営手法のことを指します。利益よりもキャッシュを大切にする考え方と言えるでしょう。
キャッシュフローが悪化する原因とは
キャッシュフローの悪化には、さまざまな原因が考えられます。大きく分けると、「キャッシュインの減少」と「キャッシュアウトの増加」の2つに分類できるでしょう。
キャッシュインの減少による悪化
キャッシュインの減少とは、売上高の減少や売掛金の回収遅延などによって、入金が減る状態を指します。例えば、景気の悪化により受注が減れば、当然、売上は減少します。
また、売掛金の回収が遅れがちになるのも、キャッシュインの減少につながります。取引先の支払いが遅れれば、いくら売上を上げても、手元にお金が入ってこないのです。
キャッシュアウトの増加による悪化
一方、キャッシュアウトの増加は、仕入れや経費の増加によって、支出が増える状態を意味します。例えば、原材料価格の高騰は、仕入れ額の増加を招きます。
また、人件費や家賃などの固定費が増えるのも、キャッシュアウトの増加につながります。売上に関係なく支出が膨らめば、キャッシュフローは悪化する一方です。
在庫の増加もキャッシュアウトの要因と言えます。売れ残りが増えれば、その分、仕入れに払ったお金が回収できなくなるのです。カネ余りの解消にも、気を配る必要があります。
このように、キャッシュフローの悪化は、キャッシュインとキャッシュアウトのバランスが崩れることによって起こります。崩れたバランスを取り戻すことが、キャッシュフロー改善の第一歩なのです。
キャッシュフローを改善するための8つの改善策

では、具体的にどのようにキャッシュフローを改善すればよいのでしょうか。ここからは、代表的な8つの改善方法について解説していきます。自社の状況に合わせて、できることから実践してみてください。
1.固定費を見直す
まずは、固定費の見直しから始めましょう。固定費とは、売上に関係なく発生する経費のことです。代表的なものとしては、人件費や家賃、設備のリース料などが挙げられます。
固定費は、削減の余地が大きい項目と言えます。例えば、人件費の削減であれば、業務の効率化や外注化が有効でしょう。社員には付加価値の高い業務に集中してもらい、単純作業は外部に委託する。これにより、人件費を抑えつつ、生産性を高めることができるのです。
ただし、安易な人員削減は避けるべきです。優秀な人材が流出しては、かえって経営が悪化しかねません。あくまでも、業務の質を落とさないことが大前提です。
家賃の見直しであれば、オフィスの移転や縮小が選択肢になります。立地や広さのグレードを下げることで、家賃負担を軽くするのです。ただし、従業員の通勤の便や取引先との関係性なども考慮に入れる必要があります。
固定費の削減は、一時的なコスト減にとどまりません。固定化した無駄を排除することで、経営体質そのものを改善する効果が期待できます。
2.資金繰り表を活用する
次に重要なのが、資金繰り表の活用です。
キャッシュフローを適切に管理するためには、資金繰り表は欠かせません。資金繰り表とは、一定期間の資金の出入りを予測し、資金不足の時期や金額を把握するための表です。
資金繰り表の作成にあたっては、売上予測や支出予定を詳細に把握することが重要です。過去の実績を基に、現実的な予測を立てることが求められます。また、資金繰り表は、定期的に更新し、実績と予測の乖離を確認することが大切です。
資金繰り表を活用することで、資金不足の時期を事前に把握し、対策を講じることができます。例えば、売掛金の回収を早めたり、支払いを遅らせたりすることで、一時的な資金不足を乗り越えることができるのです。
中小企業の経営者にとって、資金繰り表は、キャッシュフロー管理の強力なツールとなります。事業の規模や特性に応じた資金繰り表を作成し、定期的に見直すことが求められるでしょう。資金繰りの予測と実績の差異を分析し、キャッシュフロー改善につなげることが重要です。
3.売上の入金を早める
3つ目の方法は、売上の入金を早めることです。売掛金の回収サイトを短くすれば、それだけキャッシュインのタイミングを早められます。
例えば、「前払い」の比率を高めるのも一つの手です。サービス提供前や商品出荷前に代金を受け取れば、資金繰りは格段に楽になるでしょう。ただし、顧客の理解と協力が不可欠です。
「後払い」との組み合わせも効果的です。信用力の高い顧客には後払いを認め、リスクの高い顧客には前払いを求める。メリハリをつけることで、入金のバランスを取るのです。
また、売掛金の管理を徹底することも重要です。請求書の発行を早めたり、督促を欠かさなかったりと、コツコツと回収活動を行うことが求められます。
4.支払い期限を遅らせる
4つ目は、支払い期限を遅らせる方法です。仕入れや外注費など、キャッシュアウトのタイミングを少しでも後ろにずらせれば、その分、資金繰りが楽になります。
例えば、仕入れ先との交渉により、支払いサイトを延ばしてもらうのも一案です。1カ月から2カ月に伸ばせれば、1カ月分のキャッシュを浮かせることができるでしょう。
ただし、支払い条件の変更には、仕入れ先の理解が欠かせません。一方的な要求は控え、信頼関係を築くことが大切です。
また、支払いの優先順位をつけることも有効です。社会保険料や税金など、遅れると制裁を受ける支払いは最優先で行う。一方、猶予が利くものは、後回しにするなど、メリハリをつけるのです。
ただし、支払いの先延ばしは、あくまでも一時的な対症療法に過ぎません。根本的な改善のためには、キャッシュインを増やす努力が欠かせないことを忘れてはいけません。
5.ファクタリングを活用する
5つ目は、ファクタリングの活用です。ファクタリングとは、売掛債権を買い取ってもらう金融サービスのことです。売掛金を現金化できるため、資金繰りの改善に役立ちます。
ファクタリングのメリットは、審査が通れば、比較的短期間で資金を調達できる点です。売掛金という資産を担保にできるため、銀行融資に比べてハードルは低いと言えるでしょう。
ただし、手数料分のコストがかかることは覚えておく必要があります。ファクタリング会社は、売掛金の回収リスクを負う代わりに、一定の手数料を徴収します。
また、ファクタリングの利用が、取引先に知られるリスクもあります。「資金繰りに窮している」と見られ、信用を失う恐れもあるのです。
こうしたデメリットも踏まえつつ、自社にとってのメリットがデメリットを上回るかを冷静に判断することが大切です。
ファクタリングは安易に手を出さず、あくまでも最後の手段として考えるべきでしょう。
6.不良在庫を売却する
6つ目は、不良在庫の売却です。不良在庫とは、売れ残ってしまった商品在庫のことを指します。在庫は、仕入れた時点でキャッシュアウトが発生している以上、早期の資金回収が望まれます。
不良在庫を減らすには、思い切った値引き販売も一案です。定価の半額や3割引きなど、大幅な値下げで売り切ってしまう。売却額は少なくなりますが、現金を手にできる点がメリットです。
また、バーゲンセールの開催など、販売チャネルを工夫するのも有効でしょう。オークションやフリマアプリを活用するのも手です。
ただし、安売りの常習は避けるべきです。ブランドイメージを傷つけ、値崩れを招く恐れがあります。在庫の早期売却と、適正価格の維持。そのバランスを取ることが欠かせません。
7.融資等で資金調達を行う
7つ目は、融資等による資金調達です。キャッシュフロー改善の特効薬とも言える方法ですが、同時にリスクも伴います。
資金調達の選択肢としては、銀行融資が一般的です。しかし、キャッシュフローが悪化している企業にとって、銀行の審査を通過するのはハードルが高いのが実情です。
ここで重要になるのが、事業計画の策定です。キャッシュフロー改善のための具体的な施策を示し、将来の返済能力をアピールする必要があります。
また、融資以外の資金調達方法として、社債の発行や増資も検討に値します。社債は、不特定多数の投資家から資金を調達する方法です。金利負担は重くなりますが、返済期限を長く設定できるメリットがあります。
増資は、株主から資金を調達する方法です。金利負担がない点がメリットですが、株式の希薄化が進むデメリットもあります。
いずれの方法を選ぶにせよ、資金調達には慎重な判断が求められます。安易な借り入れは、かえって返済負担を増し、キャッシュフローの悪化を招きかねないのです。
8.M&Aを検討する
最後は、M&A(合併・買収)の検討です。自社単独でのキャッシュフロー改善が難しい場合、他社との統合によって打開を図る方法です。
例えば、競合他社と合併することで、スケールメリットを活かしたコスト削減が期待できます。重複する拠点の統廃合や、仕入れの一本化などにより、大幅なコストダウンが可能になるのです。
ただし、M&Aは非常にハードルの高い選択肢であることは認識しておく必要があります。相手企業の探索から交渉、デューデリジェンス、契約締結まで、一連のプロセスには多大な時間と労力を要します。
加えて、合併後の統合も重要な課題です。企業文化の融合や、従業員のモチベーション維持など、一朝一夕ではいかない難題が山積みなのです。
M&Aは、キャッシュフロー改善の切り札になり得る反面、安易な判断は禁物だと言えるでしょう。専門家のアドバイスを仰ぎつつ、慎重に検討を進めることが肝要です。
まとめ
キャッシュフローの改善は、どの企業にとっても避けて通れない課題です。売上を伸ばすことも大切ですが、そこで得た資金をいかに手元に残すかが、経営の真価が問われるのです。
本記事では、キャッシュフロー改善のための8つの具体策を紹介しました。固定費の見直しから、資金繰り表の活用、売上入金の早期化、不良在庫の売却まで、いずれも即効性のある方法です。
ただし、ここで紹介した方法はあくまでも一例に過ぎません。自社の状況に合わせて、何が最適かを意思決定することが大切だと言えるでしょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


