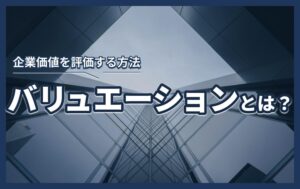廃業とM&Aではどちらが良い?メリット・デメリットを詳しく解説!
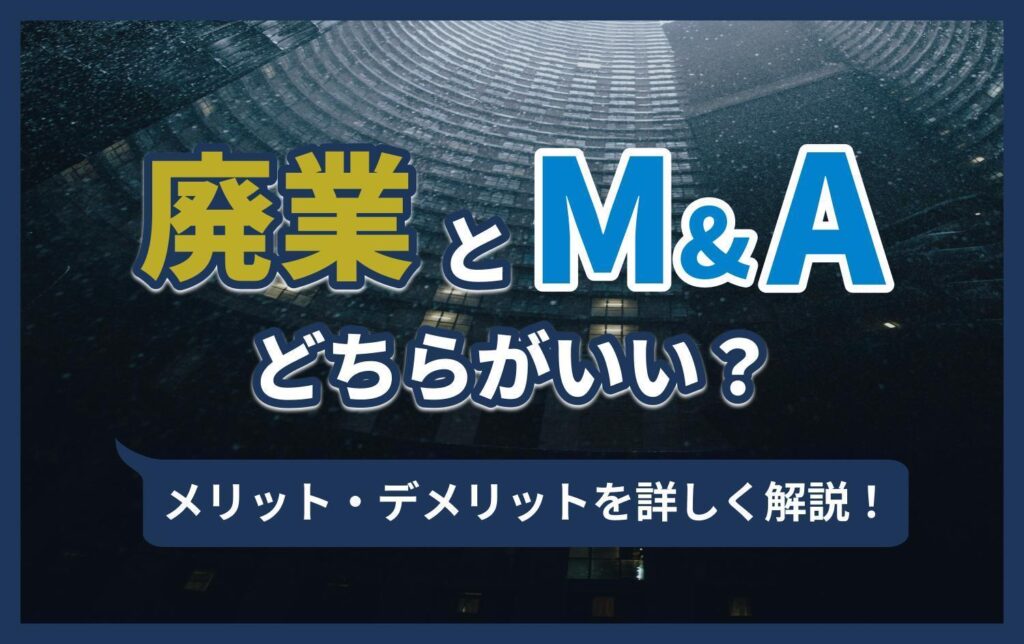

後継者不足により、自分が築いた会社を手放そうかと考えている経営者が増えてきています。会社を手放す方法としては、廃業とM&Aによる事業譲渡の2つがあります。
しかし、自分や自社の従業員にとって、どちらの方法を活用すればよいかなかなか分からないものです。そこで今回は、廃業とM&Aについてメリット・デメリット・注意点、および具体的な手続き方法について紹介します。
この記事をご覧になれば、自社にとって廃業・M&Aどちらが良いか明確になります。
廃業・M&Aの違い
まずは基礎知識として、廃業およびM&Aとはどのような行為であるか解説します。
廃業もM&Aも、現経営者が退くという点では同じです。しかし、廃業では会社の事業ごと消滅する一方で、M&Aでは会社を売却することにより、経営者が育ててきた事業を消滅させずに存続させることができます。
以下で、より詳しく「廃業」と「M&A」の違いについて見ていきましょう。あわせて、廃業・破産・倒産の違いについても解説します。
1.廃業とは
廃業とは、一般的に「会社の経営を経営者判断で清算して解散すること」を指します。
法律で定義が定められているわけではありませんが、廃業をする際には法律に則った2つの手続きが必要です。
-
- 株主総会における解散決議などによる解散手続
- 残余財産の分配などにより清算手続
廃業と破産・倒産の違い
廃業と似た言葉に「破産・倒産」がありますが、いずれも同じ意味ではありません。
それぞれの違いを以下の表にまとめました。
| 廃業 | 経営者判断で清算して解散 |
| 破産 | 債務超過に陥いるなどの経営が困難になったときに行う債務整理の手段 |
| 倒産 | 経営状況の悪化により事業の存続が困難な状態 |
破産・倒産は、経営状況の悪化によって行われるのに対して、廃業は経営状況に関わらず事業を廃止することであるため、黒字廃業のケースも少なくありません。
廃業が発生する理由
廃業が発生する理由は様々で、日本政策金融公庫の「経営者の事情を理由とする廃業の実態と必要な支援策」によると
-
- 体力・気力の衰え
- 自身の健康上の理由
- 売り上げの低迷
が主な廃業理由として多いとされています。上記の他にも、後継者不足やコロナ禍の影響で廃業している企業も多いです。
2.M&Aとは
M&A(Mergers and Acquisitions)は、会社の合併・買収を意味する言葉です。具体的には、企業の吸収合併、株式譲渡、事業譲渡、会社分割などを行います。
M&Aでは会社や事業の全部または一部を移転させるので、これまで育ててきた事業の引き継ぎができます。また、従業員を雇用している場合には、従業員との雇用契約もそのまま引き継がれます。
廃業とM&Aの比較

廃業とM&Aは、それぞれメリット・デメリットがあります。それぞれのメリット・デメリットを以下の表にまとめました。
| メリット | デメリット | |
| 廃業 | ・後継者不足の課題を解消できる ・買い手探しの手間がかからない ・業務引き継ぎの手間がかからない | ・従業員を解雇する必要がある ・取引先に迷惑がかかる ・資産売却で低く見積もられる可能性がある ・技術ノウハウの消滅 ・多額の費用がかかる |
| M&A | ・従業員の雇用確保ができる ・コストが廃業より少なく済む ・手続きが比較的簡便 ・株式や事業の売却益がある | ・買い手が見つからない可能性がある ・希望の譲渡額に満たない場合がある ・手続きに時間がかかる |
1.廃業のメリット
廃業のメリットは、経営者の手間がかからない点で、以下のような手間を省けます。
-
- 後継者を見つけるor育成する手間
- 買い手探しの手間
- 業務引き継ぎの手間
以下で、それぞれのメリットを享受できる理由について解説します。
後継者不足の課題解消
廃業を選択する最大のメリットは、後継者問題から解放されることです。会社を解散させることで、後継者を探し、育成する必要がなくなります。
事業を存続させる場合、特にM&Aを選択する際は、適切な後継者を見つけ出し、入念に育成していく必要があります。経営者の知識やノウハウ、経営理念などを継承していくには、一定の時間が必要不可欠です。
後継者の育成には5年から10年もの歳月を要すると言われています。この長い期間、後継者教育に注力し続けるのは、経営者にとって大きな負担となるでしょう。
一方、廃業はこうした後継者育成の手間と時間を省略できます。事業を清算することで、後継者問題に悩む必要がなくなるのです。
買い手探しの手間がかからない
廃業のもう一つの大きなメリットは、自社のペースで手続きを進められることです。M&Aとは異なり、買い手企業を探したり、条件交渉をしたりする必要がありません。
M&Aを選択する場合、自社の事業に興味を持ち、買収に応じてくれる企業を見つけ出すことが必要不可欠です。さらに、買収価格や条件について、双方が合意できるよう綿密な交渉を行わなければなりません。この過程には多大な時間と労力が必要とされます。
一方、廃業ではこうした他社とのやり取りが発生しません。自社の判断と都合で、スケジュールを組み、手続きを進めていくことができます。
業務引継ぎの手間がかからない
廃業のメリットとして、業務引継ぎの手間が省けることも挙げられます。
M&Aの場合、事業を引き継ぐために、業務内容や経営ノウハウ、取引先との関係性などを買い手企業に伝えていく必要があります。この業務引継ぎの期間は、通常3カ月から1年ほどかかると言われています。中には1年以上を要するケースもあるようです。
引退を控えた経営者にとって、この長い引継ぎ期間は大きな負担となるでしょう。新しい経営者に事業を任せられるまで、自らの責任で会社の舵取りを続けなければなりません。
一方、廃業を選択すれば、こうした業務引継ぎの手間が一切発生しません。事業を清算するだけなので、長期間にわたって買い手企業と関わり合う必要がないのです。
2.廃業のデメリット
主な廃業のデメリットは、以下の5つです。
-
- 従業員を解雇する必要がある
- 取引先に迷惑がかかる
- 資産売却で低く見積もられる可能性がある
- 技術ノウハウの消滅
- 多額の費用がかかる
取引先や従業員に迷惑をかけるだけではなく、最悪の場合は多額の費用がかかってマイナスになる可能性があります。以下で具体的に解説するので、メリット・デメリットを比較しながら廃業を検討してください。
従業員を解雇する必要がある
廃業は経営者にとってメリットがある一方で、従業員にとってはデメリットが大きいと言えます。廃業に伴い、従業員を解雇せざるを得なくなるからです。
特に、年齢や体力的な理由で転職が難しい従業員にとって、突然の解雇は大きな打撃となります。新たな職を見つけることが困難な場合、生活そのものが脅かされる可能性もあります。
取引先に迷惑がかかる
廃業を決定した場合、早い段階で取引先に連絡を入れ、事情を説明しておくことが重要です。急な廃業は、取引先の事業にも大きな影響を及ぼしかねません。
例えば、自社が素材を供給するメーカーだった場合、その素材を必要とする取引先は新たなサプライヤーを探さなければなりません。もし代替先が見つからなければ、取引先の生産ラインが止まってしまう恐れもあります。
最悪の場合、取引先の事業継続が困難になり、連鎖的な廃業を引き起こすリスクもはらんでいます。
資産売却で低く見積もられる可能性がある
廃業に伴う資産の売却では、期待通りの価格がつかない可能性が高いです。事業との関連性が高い資産は、事業を継続していることで価値が生まれている面があるからです。
事業が消滅してしまえば、資産の価値も大きく下がってしまうのは避けられません。中には、解体や処分にコストがかかる資産も存在します。
技術ノウハウの消滅
廃業は、長年培ってきた技術やノウハウの消滅も意味します。事業そのものがなくなるため、それらを次の世代に引き継ぐ機会が失われてしまうのです。
自社独自の貴重なノウハウを持っている場合、廃業はそれを永遠に失ってしまう選択になりかねません。
多額の費用がかかる
廃業には、手続きや資産の処分などで多額のコストがかかる場合があります。
登録免許税や清算人の登記で約3万9,000円、官報公告の費用で約4万円が必要です。加えて、事務所や店舗の解約、設備の処分などにも費用がかさみます。
黒字廃業であっても、これらのコストが利益を上回れば、手元に資金が残らないケースも十分考えられます。
3.M&Aのメリット
M&Aは、廃業よりも手間がかかる分、以下のメリットを享受できます。
-
- 従業員の雇用を確保できる
- コストが廃業より少なく済む
- 手続きが比較的簡便
- 株式や事業の売却益がある
従業員の雇用確保
M&Aの大きなメリットの一つは、従業員の雇用を維持できることです。M&Aでは、事業の譲渡と共に従業員も引き継いでもらえるため、解雇の必要がありません。
業務内容や社内体制に大きな変化がなければ、従業員はこれまでと同じように働き続けることができます。雇用の継続は、従業員の生活の安定につながります。
コストが廃業より少なく済む
M&Aは、廃業と比べてコストを抑えられる可能性があります。M&Aの場合、事業だけでなく、事務所や店舗などの資産も買い手企業に引き継がれます。
廃業時に発生するような資産の処分費用は、ほとんどかからないでしょう。
手続きが比較的簡便
M&Aは、廃業よりも手続きの負担が軽減される傾向にあります。多くの場合、M&A仲介会社やアドバイザーが手続きをサポートしてくれるからです。
専門家の助言を受けながら進められるので、煩雑な手続きに振り回されることなく、スムーズに進行できます。
株式や事業の売却益がある
引退後の資金を多く確保したい場合、M&Aは有力な選択肢となります。M&Aでは、棚卸資産、有形資産、無形資産まで含めて評価され、買い取られます。
一方、廃業の場合は資産を処分価格で現金化するだけなので、得られる資金は限定的です。M&Aなら、事業の価値を適正に評価してもらえる可能性が高いのです。
3.M&Aのデメリット
M&Aのデメリットは下記です。
-
- 買い手が見つからない可能性がある
- 希望の譲渡額に満たない場合がある
- 手続きに時間がかかる
買い手が見つからない可能性がある
M&Aは、必ずしも成功が約束されているわけではありません。買い手企業が見つからない可能性も考慮しておく必要があります。
自社の事業に魅力を感じ、買収に前向きな企業がいなければ、M&Aは成立しません。買い手探しは容易ではないため、M&A仲介会社などの専門家に依頼するのが賢明でしょう。
希望の譲渡額に満たない場合がある
M&Aでは、経営者が希望する譲渡額で売却できるとは限りません。買い手企業としても、できるだけ安価で買収したいと考えるのは自然な心理です。
また、市場ニーズの低い事業であれば、譲渡額が下がってしまうのは避けられません。ただし、会社の価値を高めたり、強みを効果的にアピールしたりすることで、売却額を引き上げる余地はあります。
手続きに時間がかかる
M&Aの手続き自体は比較的簡便ですが、完了までにはそれなりの時間を要します。事前準備、実施、統合完了の3つのステップを踏むためです。
ケースにもよりますが、通常は半年から1年ほどかかります。交渉が難航すれば、2年から3年に及ぶこともあるでしょう。
ただし、準備不足のまま進めてしまうと、売却額が下がるリスクがあります。早い段階から時間をかけて丁寧に進めていくことが、良い結果につながります。
廃業・M&Aの具体的な手続き方法

廃業・M&Aの手続きを比較してみましょう。
それぞれの手続き方法を以下にまとめました。
| 廃業手続き | M&A手続き |
|
|
それぞれの流れを以下で具体的に解説します。
1.廃業手続き
廃業手続きは、主に11項目の流れで行われますが、大きく以下の3つに分けられます。
-
- 解散・清算準備
- 清算
- 申告・登記
それぞれのフェーズで行う内容について、以下で解説します。
解散・清算準備
解散・清算準備は、
-
- 解散準備
- 解散決議・清算人の登記
- 税・社会保険関係の廃止届提出
の3つを指します。
具体的な内容は、以下のとおりです。
| 解散準備 | ・利害関係者へ事業終了の説明 ・各種契約の解約 |
| 解散決議・清算人の登記 | ・株主総会の特別決議を実施 ・解散と清算人の登記 |
| 税・社会保険関係の廃止届提出 | ・税務署に異動届出書、事業廃止届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出 ・都道府県税事務所に、解散に関する届出書を提出 ・日本年金機構に健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届を提出(※事業を廃止した日から5日以内) ・ハローワークに、雇用保険適用事業所廃止届、雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書を提出(※事業を廃止した日又は退職日から10日以内) ・労働基準監督署に、確定保険料申告書、労働保険料還付請求書を提出(※事業を廃止した日から50日以内) |
清算
清算のフェーズでは、以下の内容を実施します。
-
- 債権の取り立て・現務の完了
- 公告・個別催告
- 財産調査、財産目録等の作成・承認
- 解散・清算事業年度の確定申告
- 資産の現金化・債務弁済・残余財産分配
具体的な内容は、以下のとおりです。
| 債権の取り立て・現務の完了 | ・現務の完了、債権の取立て、債務の弁済を実施 |
| 公告・個別催告 | ・官報に債権申出に関する事項を公告 ・債権者に対しては債権申出に関する事項を個別に催告 |
| 財産調査、財産目録等の作成・承認 | ・財産目録と貸借対照表の作成 ・株主総会への提出・承認 |
| 解散・清算事業年度の確定申告 | 事業年度中に残余財産が確定していない場合は、各事業年度終了の日の翌日からカ月以内に確定申告を行う |
| 資産の現金化・債務弁済・残余財産分配 | ・資産を売却して現金化する ・債務の弁済を行う ・残余財産がある場合は清算人の決定に基づき株主に分配する |
申告・登記
清算のフェーズでは、以下の内容を実施します。
-
- 残余財産確定事業年度の確定申告
- 決算報告の作成
- 承認清算結了登記
具体的な内容は、以下のとおりです。
| 残余財産確定事業年度の確定申告 | 残余財産の確定の日の翌日から、1か月以内に確定申告を行う |
| 決算報告の作成 | ・決算報告の作成 ・決算報告を株主総会へ提出・承認 |
| 清算結了登記 | ・清算結了日から2週間以内に登記を行う |
2.M&A手続き
M&A手続きも、廃業と同様に大きく以下の3つに分けられます。
-
- 準備
- マッチング・交渉
- 最終契約
それぞれのフェーズで行う内容について、以下で解説します。
準備
M&Aは、一般的にM&A仲介業者と進めることが一般的なので、準備フェーズとしてM&A仲介業者の選定とアドバイザリー契約を行います。経営者や役員のみで行うことも考えられますが、法律や会計など専門性の高い手続きが多いため、現実的ではありません。
初めてM&Aを行う場合であれば、検討段階からクロージングまで一貫してサポートしてくれるM&A仲介会社を選ぶと良いでしょう。
マッチング・交渉
マッチング・交渉のフェーズでは、以下の内容を実施します。
-
- ノンネーム登録・買手への資料の準備
- 企業価値評価の実施
- スキーム選択
- パートナー企業との面談
- 基本合意
- デューディリジェンスと条件交渉
- 最終契約締結
具体的な内容は、以下のとおりです。
| ノンネーム登録・買手への資料の準備 | ・会社が特定されない範囲の情報をまとめたノンネームシートを作成、登録 ・譲受企業に提供する資料の準備(会社概要資料、決算資料、資金繰り表、月次資料、事業計画書、不動産登記謄本、組織図、など) |
| 企業価値評価の実施 | いずれかの方法で企業価値評価を行う ・インカム・アプローチ ・アセット・アプローチ ・マーケット・アプローチ (内部リンク) |
| スキーム選択 | 以下のなかから適切なスキームを選択 ・株式譲渡 ・会社分割 ・株式交換 ・合併 |
| パートナー企業との面談 | 経営ビジョン・譲渡後の運営方針・経営状況などの理解を深める(一般的に価格交渉は行われない) |
| 基本合意 | ・条件の整理 ・譲渡価格 ・スケジュール |
| デューディリジェンスと条件交渉 | ・不動産・金融商品などの資産の調査 ・法律面の調査 ・税務面の調査 ・デューディリジェンスの結果から譲渡対価の決定 |
契約
契約のフェーズでは、以下の内容を実施します。
-
- 最終契約締結
- クロージング
- M&A後の処理
具体的な内容は、以下のとおりです。
| 最終契約締結 | ・取引金額の決定 ・表明保証の決定 ・補償条項の決定 ・解除条件の決定 |
| クロージング | ・経営権の移転手続き |
| M&A後の処理 | ・臨時株主総会の開催 ・定款の変更(必要がある場合) ・取締役会(新たに代表取締役の任命をする場合) ・各登記の変更手続き(役員の変更や商号の変更が生じた場合) |
廃業・M&Aの選択は、専門家と相談しながら進めましょう
廃業の最大のデメリットは、従業員の雇用を守れないことです。長年共に働いてきた従業員を解雇せざるを得ず、彼らの生活に大きな影響を及ぼします。加えて、取引先にも突然の廃業は迷惑をかけてしまいます。
一方、M&Aの最大の課題は、適切な買い手企業を見つけることです。自社の事業に魅力を感じ、適正な価格で買収してくれる企業を探すのは容易ではありません。条件が合わなければ、交渉は難航し、M&Aは成立しない可能性もあります。
特に、M&Aを成功に導くには、専門的な知識とノウハウが不可欠です。M&A仲介会社や専門のアドバイザーなど、経験豊富な専門家に相談しながら進めることが賢明です。
彼らの知見を借りることで、買い手企業の探索、企業価値の適正な評価、円滑な交渉など、M&Aのプロセスを効果的に進められます。
廃業とM&Aのメリットとデメリットを慎重に比較検討し、自社の状況や将来の展望に最も適した選択を導き出しましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。