M&Aにおける失敗とは?主な理由や成功ポイントを解説
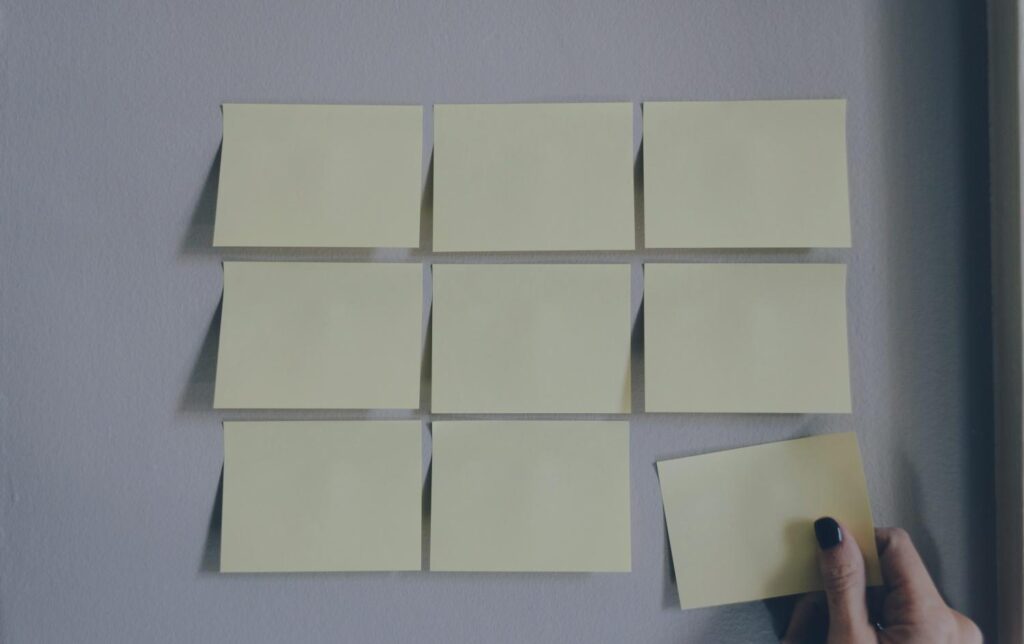
M&Aは、販路の拡大やシナジー効果(相乗効果)の獲得といった目的で実施されます。しかし、M&Aに成功する企業がある一方で、失敗してしまう企業も多くあるのが現状です。
そこで本記事では、M&Aで失敗した企業の事例や原因について紹介していきます。また、買収側・売却側の双方が把握しておきたい予防策もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
M&Aに失敗するとはどういう状況?
「M&Aに失敗してしまった」というのは、どのような状況を指すのでしょうか。一般的に、M&Aは当初設定していた目的が達成できていない状態や、達成率が80%未満の場合に失敗とみなされることが多いです。
たとえば、前者の当初設定した目的が達成できていないという状態は、M&Aに投資した金額に対して、十分な売上や利益拡大といった経営上のメリットが得られなかった場合を指します。また、経営上の問題だけでなくM&A後における不正会計や粉飾、コンプライアンス違反などの倫理的な要因によるイメージ低下もM&Aの失敗に含まれます。
とくに、近年ではグローバル化に伴う海外企業とのM&A実施に伴い、企業文化の相違やデューデリジェンス(対象企業の経営状況や財務状況などを詳細に調査すること)の不足を原因とした失敗事例も多くあります。このように「M&Aで失敗した」という状況は、経営的失敗から倫理的な問題まで多岐にわたります。
M&Aの失敗確率
実際にM&Aで失敗する確率は、70%ほどと言われています。これは、デロイトトーマツコンサルティング株式会社が2013年に実施した「M&A経験企業にみるM&A実態調査(2013年)」を由来とするものです。
M&Aで失敗する確率が70%にも及ぶ背景に、「相手企業に対するデューディリジェンスが不十分であった」、「M&A戦略が欠如していた」、「買収が目的となっていた」、「M&Aの統合プロセスに問題があった」といった理由が挙げられます。つまり、M&Aに向けて準備が不十分であったことが、失敗する原因になっていると考えられます。
M&Aの成功確率
一方で、M&Aの成功確率は、上記の70%を引いた30%ほどであると言われています。ただし、M&Aの失敗と成功確率は、何をもって失敗・成功とみなすかによって変わります。
具体的には、相手企業とのマッチングだけを成功とみなすこともあれば、M&A後に期待していた利益獲得や事業拡大につながったかなど、企業ごとに成功基準はさまざまです。そのため、30%という成功確率はあくまでも表面的な数字であり、実際にどれくらいの成功を収めているかを表すものではない点に注意が必要です。
大企業におけるM&Aの失敗事例10選
日本国内でのM&A失敗事例10選を紹介します。これらの事例は、大企業における失敗を中心に解説していますので、M&Aを検討する際の参考にしていただければ幸いです。
1.パナソニックと三洋電機
2009年、パナソニックは環境・エネルギー分野での競争力強化を目的に三洋電機を約8,000億円で買収しました。
しかし、買収後に三洋電機の太陽電池事業が中国メーカーとの価格競争に敗れ、リチウムイオン電池事業も期待通りの成長を見せませんでした。
2013年3月期には、三洋電機買収に伴うのれん代の減損処理などにより、7,542億円の最終赤字を計上しました。
この失敗の主な原因は、買収価格の過大評価と、買収後の統合戦略の不備にありました。
2.日本郵政とトール・ホールディングス
2015年、日本郵政はオーストラリアの物流大手トール・ホールディングスを約6,200億円で買収しました。しかし、買収後にトール・ホールディングスの業績が急激に悪化し、2017年3月期に約4,000億円の減損損失を計上しました。
買収前のデューデリジェンス(企業価値評価)が不十分だったこと、および買収後の経営統合が円滑に進まなかったことが本案件の主な失敗要因と言われてます。
3.ソフトバンクとスプリント
2013年、ソフトバンクは米国の通信事業者スプリントを約1.5兆円で買収しました。
しかし、買収後もスプリントの業績は低迷を続け、ソフトバンクの財務を圧迫しました。2020年にT-モバイルとの合併が完了するまで、多額の投資を続けることを余儀なくされました。
多額の投資が発生してしまった主な要因は、米国通信市場の競争激化と、スプリントのネットワーク品質改善に予想以上の時間とコストがかかったことです。
4.楽天とビットワレット
2010年、楽天は電子マネー事業「Edy」を運営するビットワレットを買収しました。しかし、その後のスマートフォンの普及や競合他社の台頭により、Edyの市場シェアは低下。2017年には約100億円の減損損失を計上しました。
これほど多額の損失が発生した主な要因は、市場環境の変化への対応の遅れと、他の決済サービスとの連携不足でした。
5.東芝とウェスチングハウス
2006年、東芝は米国の原子力発電事業会社ウェスチングハウスを約5,400億円で買収しました。
しかし、2011年の福島第一原発事故以降、原子力発電所の建設コストが急騰し、ウェスチングハウスは2017年に経営破綻しました。東芝は約7,000億円の損失を計上し、経営危機に陥りました。
失敗の主な要因は、原子力発電事業のリスク評価の甘さと、市場環境の急激な変化でした。
6.ディー・エヌ・エー(DeNA)とショウタイム
2015年、DeNAは動画配信サービス「ショウタイム」を運営するアビームコンサルティングから事業を買収しました。
しかし、競合他社との競争激化や、コンテンツ調達コストの上昇により、事業は期待通りの成果を上げられませんでした。2018年3月期には約38億円の減損損失を計上し、サービスを終了しました。
このM&Aが上手くいかなかった要因は、市場競争の激化と、コンテンツ調達戦略の不備でした。
7.セブン&アイ・ホールディングスとイトーヨーカ堂
セブン&アイ・ホールディングスは、傘下のイトーヨーカ堂の業績不振に長年悩まされてきました。
2016年には40店舗の閉鎖を決定し、約1,000億円の特別損失を計上しました。
この業績不振の要因は、消費者ニーズの変化への対応の遅れと、過剰な店舗展開でした。
8.キリンホールディングスとスキンカリオール
2011年、キリンホールディングスはブラジルのビール会社スキンカリオールの株式50%を約2,900億円で取得しました。
ただ、ブラジル経済の低迷や競争激化により、スキンカリオールの業績は悪化。2015年には約1,100億円の減損損失を計上しました。
ブラジル市場の見通しの甘さと、現地経営陣との意思疎通不足がまねいた結果となります。
9.NTTドコモとTata Teleservices
2009年、NTTドコモはインドの通信事業者Tata Teleservicesに約2,600億円を出資しました。しかし、インド通信市場の競争激化により、Tata Teleservicesの業績は低迷。2017年にNTTドコモは約1,200億円の減損損失を計上し、出資を引き揚げました。
失敗の主な要因は、インド通信市場の競争環境の読み誤りと、現地パートナーとの経営方針の不一致でした。
10.みずほフィナンシャルグループの3行統合
2000年代初頭、みずほフィナンシャルグループは第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行の3行を統合しました。
ただ、システム統合に多大な困難が生じ、2002年4月には大規模なシステム障害が発生。顧客の信頼を大きく損ねる結果となりました。
複雑なシステム統合の難しさと、3行の企業文化の違いを克服できなかったことがこの大規模なシステム障害の要因とされています。
これらの事例は、日本企業のM&Aにおける典型的な失敗パターンを示しており、適切なデューデリジェンス、市場環境の正確な分析、文化の統合、そして買収後の経営戦略の重要性を浮き彫りにしています。
中小企業におけるM&Aの失敗事例4選
こちらでは中小企業のM&A事例について詳細に解説しておりますので参考にしてください。
1.情報開示不足による不当評価
ある中小製造業者は、事業承継を目的としてM&Aを検討していました。
しかし、交渉過程で自社の技術力や顧客基盤に関する情報開示が不十分でした。
具体的には、主要取引先との長期契約の詳細や、特許出願中の新技術に関する情報が適切に買収側企業に提供されませんでした。
結果として、買収側企業は提供された限られた情報のみで企業価値を判断し、リスクを過大に見積もりました。これにより、買収価格が売り手の期待を大きく下回り、交渉は決裂しました。
この事例は、中小企業が自社の強みや将来性を適切に伝えることの重要性を示しています。特に、無形資産や将来の成長可能性に関する情報を効果的に開示することが、公正な企業価値評価につながります
2.デューデリジェンス不足
中小IT企業が事業拡大を目指して同業他社を買収しましたが、デューデリジェンスが十分に行われていなかったため、買収後にいくつかの重大な問題が明らかになりました。
まず、買収先企業の主要顧客との契約が更新時期に差し掛かっており、多くの契約が解約されるリスクが高いことが判明しました。また、重要な技術者が退職を検討しているという事実も把握できていませんでした。
さらに、買収対象企業には財務諸表に記載されていない多額の偶発債務が存在しており、これが後に発覚したことで、買収企業は予想外の財務的負担を強いられることとなりました。
本事案では、財務、法務、人事、技術、顧客関係など、さまざまな観点からの徹底したデューデリジェンスがいかに重要かを示しています。特に中小企業では、情報管理が不十分であることが多いため、より慎重で入念な調査が求められます。
3.買収後の統合失敗
地方の中堅物流会社A社は、事業拡大を目指して同業のB社を買収しましたが、買収後の統合プロセスがうまくいかず、期待した相乗効果が得られませんでした。
特に、両社の業務システムの統合が遅れ、効率化が進まなかったことが問題となりました。また、営業部門間の連携不足により、クロスセリングの機会を逃すことも多くありました。さらに、人事制度の違いから従業員のモチベーションが低下し、一部の優秀な人材が流出する事態も発生しました。
結果として、買収から2年経過しても、当初計画していた統合効果の半分も達成できない状況に陥りました。この事例は、中小企業のM&Aにおいて、買収後の統合プロセスが非常に重要であることを示しています。特に、専門チームを設置する余裕がない場合、外部専門家の活用を含めた緻密な統合計画が不可欠です。
4.文化の違いによる対立
中小の食品メーカーが製品ラインを拡充するため、異なる企業文化を持つ同業他社を買収しました。しかし、文化の違いが原因で深刻な対立が生じ、業績が悪化しました。
買収側は伝統的な家族経営で保守的な文化を持ち、買収された企業は若手中心のベンチャー精神旺盛な文化でした。この違いは、意思決定やリスクに対する姿勢、働き方に顕著に表れました。新製品開発では、買収側が慎重な市場調査を重視する一方、買収された側は迅速な意思決定を求め、意見が対立しました。また、人事評価の違いから不公平感も生まれました。
結果として社内の対立が顧客サービスの質の低下や新製品開発の遅れを引き起こし、市場シェアが減少しました。この事例は、中小企業のM&Aにおいて企業文化の違いを理解し、統合計画に反映させる重要性を示しています。文化の違いを尊重し、新たな共通文化を築く努力が必要です。
M&Aが失敗か判断するための評価基準
M&Aが失敗かを判断するために、各企業ではさまざまな評価基準を設けています。一般的に、M&Aを評価する基準には下記の5つの要素がありますが、どのような観点で評価を行っているのでしょうか。それぞれの基準について、丁寧に解説していきます。
利益水準
1つ目の判断軸は、利益水準です。M&Aでは、買い手側(譲受企業)・売り手側(譲渡企業)のいずれもが利益を最大化させるのが理想的です。
たとえば、M&Aで買い手側の企業は、既存事業との関連性が高い同業他社を買収することで、従業員やノウハウ、設備、取引先、ブランド力、開発能力といった資産を得られます。このような資産を活用し、事業領域のさらなる拡大や新規事業の開拓などで利益を狙えるかどうかが評価基準となります。
また、買い手側の企業にとっても、金銭や他社の株式という資産を得られる機会に加え、「グループ企業に属する」以下の文章は、売り手側のメリットかと存じますので、ご確認お願いします。グループ企業に属することで競争力を高めるチャンスもあります。親会社の潤沢な資金や独自ルート、経営ノウハウなどを活かして、利益を拡大できるかが評価基準になります。
事業計画の達成度合い
2つ目は、事業計画の達成度合いです。事業計画の達成度合いとは、主にM&A後における販路の拡大や事業の発展を指します。
また、達成度合いを可視化するためにも、さまざまな指標を用いることがあります。具体的には、M&A前と比較して、売上・利益がどれくらい増加したのか、販路の数、資産額といった数値が達成度合いとして用いられます。
投資効率
3つ目の評価基準は、投資効率です。M&Aにおける投資効率を数値化する際に「IRR」や「NPV」といった指標が用いられます。
IRR(Internal Rate of Return)とは「内部収益率」を意味し、将来の収益性を数値化した指標です。M&Aによる投資を行った結果、将来的に得られるキャッシュフローと投資額のそれぞれの現在価値が等しくなる割引率を指します。IRRの数値が高いほど、M&Aによる投資資金を早い段階で回収できる可能性があります。
NPV(Net Present Value)とは「正味現在価値」と呼ばれる指標です。収益額をもとに投資を評価する指標のことで、投資によって将来得られるキャッシュフローの現在価値の総和から投資額を引くことで算出します。投資を行う際の判断基準にもなり、利益を生む可能性を調べる際や、複数の投資案件を比較するときに用いられます。
減損の有無
4つ目の評価基準は、減損の有無についてです。減損とは、固定資産や株式の価値が当初の想定より大幅に低下した場合に行われる会計処理を意味します。
つまり、減損の有無は、M&Aで投資を行った結果、投資した固定資産から当初想定していた収益の回収が見込めなくなってしまう状況が発生しているかどうかで判断されます。なお、減損の対象となるのは土地・建物といった企業経営に必要な有形固定資産と、のれんや商標などの形を持たない無形固定資産に分けられます。
財務指標
ROA・ROE・EVAといった財務指標についても、M&Aが失敗したかどうかの評価基準となります。まず、ROA(Return On Assets)とは、日本語で総資産利益率と呼ばれており、総資本をどれだけ効率的に使い、利益を生み出しているかを示す指標です。M&Aで相手先企業の財務状況を調べる際に用いられ、重要指標といえます。
次に、ROE(Return on Equity)とは、自己資本利益率を意味し、企業経営の効率性や株主に対する還元効率を示す財務指標です。対象企業に投資した結果、どれくらい利益を効率よく得られるのかを数値化したもので、ROEの数値が高いほど期待度が高まります。
最後に、EVA(Economic Value Added)とは、経済付加価値と呼ばれ、企業が投下した資本に対して付加価値がどれくらい生み出されたかを把握するための指標です。EVAの数値がプラスになると、株主の期待以上に価値を生み出していると評価できます。
M&A失敗の理由|買い手企業側
M&Aにおける失敗は、さまざまな原因で発生します。とくに、買い手が原因となる失敗事例も多いため、十分に注意しなければなりません。ここでは、具体的な失敗理由を5つご紹介します。
投資費用対効果が得られない
1つ目に、投資費用対効果が得られないという理由が挙げられます。これは、M&Aに使った投資額に対してリターンが小さいことや、リターンがなくマイナスになっている状況です。
上記の事象が発生する要因としては、M&Aの買い手側が十分なリサーチを行っていない可能性が考えられます。勢いだけで相手企業を買収すると、譲受後に投資対効果がなかなか得られず失敗に終わってしまいます。
のれん代の損失計上
2つ目は、のれん代の損失計上です。のれん代とは、企業のブランド力や信用力、顧客とのつながりといった無形資産のことで、会社が将来的に得られるであろう収益価値を意味します。
M&Aで会社を買収したあと、買収価格を貸借対照表に記載する必要があります。このとき、のれん代は将来にわたる企業価値の減少が認められた際に一括償却しますが、買収した会社の企業価値が下がった場合には、減損を計上しなければなりません。「一括償却」と「減損」の違いが不明でした。両方とも減損のことを指しているように思われます。のれん代の損失計上が発生した結果、M&Aの失敗となってしまいます。のれん代は、日本基準では20年以内の効果の及ぶ期間で規則的に償却、IFRSでは非償却(減損テスト)という考え方です。どこまで当コラムで記載すべきか判断が付いておりませんので、補足させて頂きます。
買収後に粉飾決算が見つかる
3つ目は、M&Aで買収したあとに、粉飾決算が見つかってしまうことです。買収先である相手企業の財務状況や管理状況を把握していないままM&Aを実施したことで、粉飾決算を含む問題が浮き彫りになる可能性があります。
仮に粉飾決算が見つかってしまうと、自社にとっても大きなダメージになり、最悪の場合には倒産にもつながります。このような事態が起こらないようにするためにも、M&A前に相手の企業をしっかりと調べるようにしましょう。
買収後、企業のイメージが悪化する
M&Aで買収したあとに、自社の企業イメージが悪化してしまうことも失敗の原因に挙げられます。相手企業がコンプライアンスに違反していたり、環境問題を放置していたりするといった状況のなかで買収を進めてしまうと自社のイメージも悪化する恐れがあります。
また、とくに気をつけたいのが、海外企業を買収したあとです。日本国内の企業とは文化や習慣、考え方が異なることから、買収後にさまざまな理由で企業イメージが悪くなる場合も考えられます。
買収後、放置してしまう
最後に、買収したあとに買収前の経営陣のまま放置してしまう状況です。買収後に放置してしまった結果、企業の業績が手遅れな状況になってしまったり、従業員が離職してしまったりするなどの恐れがあります。
とくに、優秀な従業員は、先が見通しにくくなることでモチベーションが下がり、企業全体の生産性が低下することも考えられます。このようにM&Aでは、買い手側企業との関わり方が成功・失敗の大きな要因となり得ます。
M&A失敗の理由|売り手企業側
M&Aの失敗は、買い手側企業だけでなく売り手側の企業でも起こり得ます。買い手側と同様に、M&A前のチェックが甘かったり、買収されたあとに業績が悪化してしまったりといった形で失敗するケースがあります。具体的に、どのような失敗の理由があるのか5つご紹介します。
買い手側の情報を鵜呑みにする
1つ目は、買い手側の情報を鵜呑みにしてしまい失敗するケースです。たとえば、M&Aの話を持ちかけられたときに、自社にとって良いことだけ一方的に伝えてくる場合があります。
全てのケースに当てはまるわけではありませんが、M&Aを強引に進めてくる場合は注意が必要です。買い手側の情報を鵜呑みにした結果、自社に不利益な状況を作らないようにしましょう。
株主と役員の意見不一致
次に、株主と役員で意見が一致しなくなってしまった場合です。意見が一致しないまま交渉を続けることで、M&A自体が頓挫してしまう可能性だけでなく、M&Aを実施したあとも関係性が悪化する恐れがあります。
また、M&Aの時期を見誤ると、最悪の場合は経営破綻に追い込まれるケースも考えられます。株主と役員の間で積極的に意見を交わすようにしながら、両者で不一致が起こらないようにしましょう。
社内情報の整備が充分ではない
3つ目の失敗理由は、社内情報の整備が十分に行われていないことです。具体的には、株券や株主名簿の準備不足、議事録を取っていないことなどが挙げられます。
通常、M&Aにて株式を譲渡する際に、売り手側の企業では株券・株主名簿を整備する必要があります。仮に、M&Aを実施する際に株券・株主名簿を整備していない場合、M&Aが成約して株式を譲渡するときにトラブルが生じ、取引中断になりかねません。
また、議事録を残しておかないことが理由となり、相手企業の信用を大きく失い、M&Aが思うように進まなくなるリスクもあります。株主総会議事録・取締役会議事録の書類を整備し、議事録の調査で問題が起こらないようにしましょう。
自社の業績悪化
M&Aを実施している間に、自社の業績が悪化することで失敗になるケースもあります。一般的に、M&Aが完結するまでに半年〜1年ほどの時間がかかると言われています。
この期間において自社で資金繰りが悪くなったり、業績が著しく悪化してしまったりすると、M&A契約が中断されることがあります。M&Aが予定されているからといって安心するのではなく、完結するまでしっかりと経営に力を入れなければなりません。
トラブル・不祥事の発生
自社でトラブルや不祥事が発生した場合にM&Aが失敗することも考えられます。たとえば、顧客情報が漏洩していたことが明るみになった場合、社会的な信用を大きく下げてしまう可能性があります。
上記のような事態が発生すると、相手企業から調査が入り、M&Aの中断も起こり得ます。情報漏洩だけではなく、さまざまなトラブル・不祥事が発生しないように注意することが求められます。
M&Aに失敗しないためのポイント
M&Aは、買い手企業・売り手企業それぞれで失敗する可能性があります。それでは、M&Aで失敗しないためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。買い手企業・売り手企業がそれぞれ気を付けたいポイントをまとめていきます。
買収側のポイント
買収する側の企業が注意するべきポイントは以下のとおりです。
・M&Aの目的を明確にする
・自社の成長に貢献してくれる企業を選ぶ
・シナジー効果や財務健全性、実現可能性などの観点から分析する
・専門家に相談し、企業価値評価やデューデリジェンス(DD)を行う
まずは、M&Aを実施する目的を明確にすることが大切です。M&Aを実施するのかを明らかにしないまま進めると、従業員から不信に思われてしまったり、最終的な成果が出にくくなってしまったりします。目的を明らかにしたうえで、達成に向けた準備をすることが求められます。
また、自社の成長に貢献してくれる企業を買収先として選ぶことも大切です。買収することによるシナジー効果、成長性、財務の強化など、将来的な効果を考えましょう。
そして、買収先の企業価値評価やデューデリジェンスの実施も重要です。M&Aを実施する前に、簿外債務やトラブル・不祥事などのリスクを抱えていないかチェックし、自社が不利益にならないように進める必要があります。
売却側のポイント
売却側が注意するポイントは以下のとおりです。
・企業価値評価に備えて自社においてもどのくらいの価値となるかを把握する
・株券・株主名簿整備や簿外債務などがあれば明確にしておく
・人材の流出を防ぐため早めに根回しや協議を行う
買い手の企業だけでなく、売り手企業でも企業価値評価を実施する必要があります。自社の企業価値評価を把握しておくことで、適切な買収価格のすり合わせが可能となります。
また、株券・株主名簿整備や簿外債務などがあれば明確にしましょう。前述したとおり、株券・株主名簿が整備されていないことや、簿外債務も買い手企業の信用を落とす原因となり得ます。自社の人材流出も防ぎながら、丁寧に進めるようにしましょう。
M&Aの専門家に相談しよう
最後に、買い手側・売り手側に共通して、M&Aの専門家に相談することが大切です。上記で挙げたポイントを把握しながら、専門家に相談することでリスクを最小限に抑えられます。
まとめ
M&Aは失敗するリスクも高いため、丁寧に進めていかなければなりません。買い手側・売り手側双方にとってリスクがあるため、M&Aを実施する前に自社で綿密に調査することが求められます。
また、M&Aを失敗しないためにも、各企業が対策を考える必要があります。利益水準や達成度合いといった指標を具体的に設定し、M&Aで目的を実現していきましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


