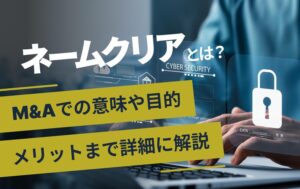病院やクリニックを廃業・閉院する際の手続きの流れと存続のための対策

目次
はじめに
後継者不足や経営悪化などを理由に廃業・閉院する病院やクリニックが増えています。この記事では、病院もしくはクリニックの廃業・閉院を検討中の方へ向けて、一般的な廃業手続きの流れと、廃業・閉院しないための対策について紹介します。
病院・クリニックにおける廃業手続きの流れ
1.閉院までのスケジュールを立てる
まずは閉院までの計画をきちんと立てることが大切です。病院やクリニックを閉じるとなると、さまざまな機関への書類の提出や、スタッフや患者への対応など、やらなければならないことが数多くあります。無計画のまま進めると混乱をきたし、期日までに手続きを終えられない可能性が高まります。また、スタッフや患者にも迷惑をかける恐れがあります。無理なくスムーズに病院やクリニックを閉められるよう、いつまでに何をするのか余裕をもったスケジュールを立てましょう。
2.各種申請・必要書類を提出する
次に、廃業に関する各種申請、必要書類の提出を行います。廃業の手続きは届出ごとに提出先や提出期限が異なります。廃業に伴う主な手続きは以下のとおりです。
【保健医療機関廃止届】
提出先:地方厚生局
提出期限:廃業時に遅滞なく
【生活保護法指定医療機関廃止届】
提出先:福祉事務所
提出期限:廃業後10日以内
【医師会への退会届】
提出先:所属する医師会
提出期限:廃業時に遅滞なく
【個人事業廃止届】
提出先:税務署/都道府県税事務所
提出期限:(税務署)廃業後1カ月以内
(都道府県税事務所)都道府県税事務所ごとに異なる
【適用事業所全喪届・被保険者資格喪失届】
提出先:年金事務所
提出期限:廃業後5日以内
【診療所廃止届または開設者死亡(失踪)届】
提出先:保健所
提出期限:廃業後10日以内
【診療用エックス線装置廃止届】
提出先:保健所
提出期限:廃業後10日以内
【麻薬取扱者業務廃止届】
提出先:保健所
提出期限:麻薬業務廃止後15日以内
【確定保険料申告書】
提出先:労働基準監督署、都道府県労働局など
提出期限:廃業後50日以内
保険医療機関廃止届
「保険医療機関廃止届」は、「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令」の第8条により、病院が廃業する際に、病院が所在する都道府県を管轄する地方厚生局の事務所などに提出することが義務付けられています。提出方法は窓口に直接持参するほか郵送での提出も可能で、手数料は発生しません。窓口の受付時間や届出に関して相談があれば、提出先の地方厚生局に問い合わせましょう。
生活保護法指定医療機関廃止届
生活保護法、中国残留邦人等支援法※で指定を受けた病院は、廃業から10日以内に病院の所在地を所管する福祉事務所に「生活保護法指定医療機関廃止届」を提出する必要があります。疑問点や相談がある場合は、福祉事務所に問い合わせましょう。なお、手数料は発生しません。窓口の受付時間は福祉事務所ごとに異なるため、こちらも事前に確認しておくと安心です。
※正式名称:中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
医師会への退会届
廃業に伴って医師会を退会する場合は、所属している医師会に「退会届」を提出します。退会に関する手続きは医師会ごとに異なるため、所属の医師会に問い合わせのうえ、手続きを行ってください。
なお、通常会費が未納の場合には退会できません。また、提出が遅延した場合、時期によっては会費が発生することがあります。そのため、未納分がないかを所属の医師会に確認し、遅延なく退会届を提出しましょう。
個人事業廃止届
個人医院を閉院する際は管轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しなければなりません。提出期限は廃業後1カ月以内ですが、期限当日が土日祝日に該当する場合は、その翌日が期限とみなされます。受付時間は、税務署の開庁時間である8時30分〜17時で、「e-Tax」による提出も可能です。なお、e-Taxで申請する場合は、本人確認書類の写しの添付は必要ありませんが、書類で提出する場合には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
さらに事業税を納めていたり、開業届を都道府県税事務所に提出していたりした場合には、所管の都道府県税事務所にも「個人事業廃止届」の提出が必要です。ただし、提出方法や提出期限は都道府県税事務所ごとに異なるため、必ず事前確認をしてください。
適用事業所全喪届・被保険者資格喪失届
「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」は、廃業から5日以内に病院の所在地を管轄する年金事務所に提出します。提出方法は電子申請、郵送、窓口の3つから選べます。添付書類として「解散登記がある法人登記簿謄本のコピー」もしくは「雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー」が必要です。
なお、適用事業所全喪届を提出するとその病院やクリニックで社会保険に加入していたスタッフの資格もなくなります。そのため、一般的に適用事業所全喪届を提出する際に「被保険者資格喪失届」も一緒に提出します。
診療所廃止届または開設者死亡(失踪)届
病院やクリニックを廃止する場合、廃業後10日以内に所管の保健所に「診療所廃止届」または「開設者死亡(失踪)届」を提出します。診療所廃止届を提出する際、開設許可証や変更許可証、使用許可証を提出する場合があるため、事前に確認しておくと安心です。また、「開設者死亡(失踪)届」はその名のとおり、開設者が死亡または失踪して診療所を廃止する場合に提出します。どちらの届出も手数料は発生しません。受付時間や提出書類は保健所ごとに異なるため、必ず事前に所管の保健所に確認してください。
診療用エックス線装置廃止届
医療法第15条3項及び医療法施行規則第29条第1項の規定により、診療用エックス線装置がある場合には「診療用エックス線装置廃止届」を提出する必要があります。期限は廃業後10日以内、提出先は病院の所在地を管轄する保健所です。受付時間や提出書類は保健所ごとに異なるため、必ず事前確認をしてください。なお、手数料は発生しません。
麻薬取扱者業務廃止届
「麻薬取扱者業務廃止届」は、麻薬に関する業務を停止した際に必要となります。業務を廃止してから15日以内に、麻薬取扱者免許証を添えて保健所に提出します。また、麻薬の在庫が残っているときは「免許失効による麻薬譲渡届」の提出及び麻薬の譲渡、もしくは「麻薬廃棄届」の提出と麻薬の廃棄などの手続きも必要です。申請手数料は発生しません。受付時間は保健所ごとに異なるため、事前に確認してください。
確定保険料申告書
廃業によって労働保険が不要になるため、「確定保険料申告書」を提出し、年度当初に見込み額として申告・納付した概算保険料を精算します。提出先は、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局などです。事業を廃止した日から50日以内に提出します。なお、確定保険料の額が概算保険料より多いときは、届出と同時に差額を納める必要があります。
3.スタッフ・患者への対応や社会保険の手続きを進める
廃業・閉院に伴う各種届出とともに、スタッフや患者への対応も欠かせません。スタッフに対しては退職金の支払いと社会保険の手続きを進めます。一方で患者に対しては、ほかの病院への転院や紹介といった引き継ぎ対応を行います。また、医療費の未収金がある患者に対しては、回収作業を行わなければなりません。
こうしたスタッフや患者への対応は、廃業・閉院に伴う手続きと同時に行うと手一杯になる可能性があります。さらにスタッフは転職活動のため、患者はほかの医療機関を探すために、十分な時間が必要です。したがって遅くとも3カ月前にはスタッフや患者に廃業・閉院の旨を通知し、必要な対応を行えるように計画を立てましょう。
病院・クリニックの廃業・閉院に関する現状
近年では、患者数の減少や後継者不足など、さまざまな要因から廃業・閉院する病院・クリニックが増えています。ここでは病院・クリニックの廃業率と廃業・閉院する主な理由について解説します。
病院・クリニックの廃業率
帝国データバンクが2022年に公表した「医療機関の休廃業・解散動向調査」によると、2021年の医療機関の休廃業・解散は過去最高の567件で、2019年以降3年連続で500件を超えています。
なかでもクリニック(診療所)の休廃業・解散・倒産は多く、厚生労働省が公表している「医療施設動態調査(2021年10月)」をもとに計算すると、クリニックの廃業・倒産率は約0.47%になります。一般企業と比較するとかなり低いものの、それでも増加傾向にあります。
クリニックの廃業・倒産率が増加傾向である原因として、患者数の減少が挙げられます。特に2019年からは新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛や、院内感染リスクを警戒しての「受診控え」が広がったことで患者数が減少しています。また、人々が新型コロナウイルス感染症対策を徹底したことで、インフルエンザや風邪などの患者数が減り、閉院するクリニックが増えたと考えられます。
(参照元:医療機関の休廃業・解散動向調査|帝国データバンク
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220111.pdf p.1,2)
(参照元:「医療施設動態調査」(2021年10月)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/m21/dl/is2110_01.pdf p.1)
病院・クリニックが廃業する主な理由
2021年に帝国データバンクが公表した調査によれば、病院やクリニックが廃業する主な原因は、院長や代表者の高齢化と後継者不足であるとされています。同調査によると、病院における代表者の年齢は40代が3.3%、50代が14.5%、60代が31.6%、70代が50.4%で、60代以上が82.0%と高齢化が進んでおり、後継者不足であることもわかります。実際、厚生労働省が公表している「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計」によると、開設者または法人の代表者の平均年齢は64.7歳で年々平均年齢が上がっています。
(参照元:医療機関の休廃業・解散、倒産の17倍超|帝国データバンク
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220111.pdf p.3)
(参照元:令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_1gaikyo.pdf p.38)
病院・クリニックを廃業した後の注意点
病院やクリニックを廃業する際は、レントゲン撮影のデータ(もしくはレントゲンフィルム)とカルテの取り扱いに注意が必要です。具体的には、レントゲン撮影のデータは3年間、カルテは5年間保管することが法律で定められていますが、患者から損害賠償請求を受けたときのことを考えて10年間保管しておくとより安心です。
保管期限を越えたレントゲン撮影のデータやカルテは、信頼できる廃棄処理業者に廃棄を依頼しましょう。どちらのデータも重大な個人情報に該当するため、廃棄方法を誤るとトラブルにつながる恐れがあります。
病院・クリニックの廃業に必要なコスト
病院やクリニックの廃業には多額の費用が発生します。まず、医療機器や医療用品、薬剤の処分を専門業者に委託しなければならず、コストがかかります。放射線治療装置やレントゲン装置、超音波診断装置などの医療機器は専門業者に買い取ってもらえる可能性がありますが、機器が古いと処分対象となり、処分費がかかります。また、医療機器をリース契約している場合には、残債や違約金を支払わないといけないため、事前に契約内容を確認しておくことが重要です。ほかにも法的手続きの諸費用や建物の退去時に費用が必要なケースもあるので、事前に必要なコストを計算しておきましょう。
病院・クリニックを廃業・閉院しないための対策
病院・クリニックを廃業・閉院させるとなると、時間と労力、そしてコストがかかります。また、病院やクリニックがなくなると地域医療の崩壊を招くかもしれません。病院やクリニックの廃業・閉院を避けるには、以下のような対策を検討してみましょう。
M&Aを検討する
病院やクリニックのM&Aは、後継者不足や経営悪化などを原因とした廃業・閉院を防ぎ、スタッフの雇用維持に寄与します。ただし、病院のM&Aには企業のM&Aと異なる点が多くあります。例えば、病院のM&Aは一般企業と違って株式を発行しないため、基本的に事業譲渡、合併、出資持分譲渡の3つの手法で行われます。また、病院のM&Aは医療法などの専門的な知識が必要とされるため、信頼できる専門家への依頼が欠かせません。
病院経営を安定させる
経営悪化が原因であれば、収益と費用を見直して、病院経営の安定化を図りましょう。例えば、チラシや広告、公式ホームページ、SNSなどを使って病院の情報を発信する、予約システムを導入するなど、今までとは違う方法で患者を集めることで収益アップにつながります。同時に無駄な出費を防ぐことも、経営を安定させるために必要です。ただし、やみくもなコストカットはスタッフや患者の満足度低下につながる恐れがあるため、細かく精査して不必要な費用のみをカットしましょう。
まとめ
病院やクリニックを廃業・閉院するには、さまざまな申請や必要書類の提出が必要です。加えて、スタッフや患者への対応など、時間、労力、費用がかかります。
病院やクリニックを廃業・閉院させないためには、経営の安定化を図るほかにM&Aを活用するのもひとつの方法です。M&Aであれば後継者の確保や地域医療の継続など、医療業界が抱える課題の解決にも役立ちます。ただし、医療機関のM&Aは専門的な知識が必要とされるため、まずは信頼できる専門家に相談しましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。