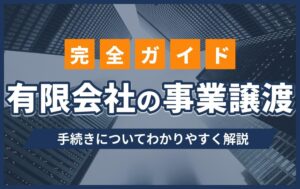廃業のメリット・デメリットとは?経営者が取るべきアクションとは
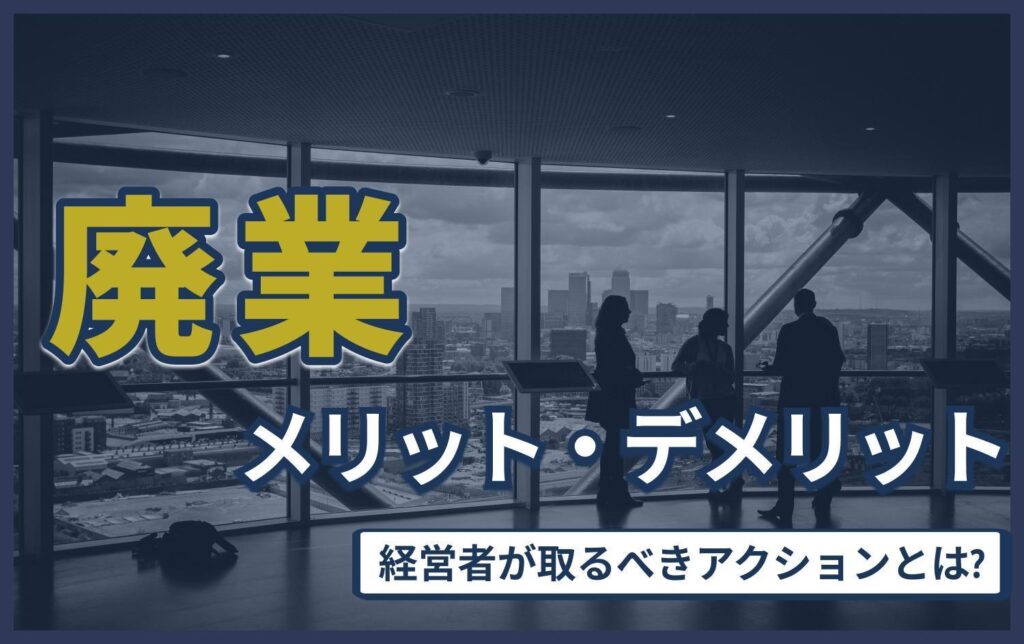

『後継者がいない…』『事業を続けるのは厳しい』。こんな悩みを抱える中小企業の経営者は少なくありません。一生懸命に築き上げた事業を手放すのは辛い選択ですが、時には「廃業」という決断が、経営者にとってベストな選択肢になることもあります。
この記事では、廃業のメリットとデメリット、そして廃業後の新たな人生設計について考えていきます。
目次
廃業とは
廃業とは、事業をやめて法人または個人事業主としての活動を終了することを指します。会社の場合は清算手続きを経て法人格が消滅し、個人事業主の場合は事業をやめることを税務署に届け出ます。
国税庁の統計によると、近年、毎年一定数の企業が廃業しています。全企業に占める廃業の割合は、決して無視できない数字となっています。
業種別に見ると、飲食業、小売業、建設業などのサービス業や、人手不足に悩む業種での廃業が目立つ傾向にあります。特に、経営者の高齢化や後継者不足が深刻化している中小企業において、事業の継続が困難となり、廃業を選択するケースが増加傾向にあるようです。
帝国データバンクの「休廃業・解散」動向調査によると、廃業した経営者の平均年齢は70歳前後です。その多くが「適当な後継者がいない」ことを廃業の理由に挙げています。少子高齢化が進む中、今後もこの傾向は続くと予想されます。
廃業のメリット
廃業にはメリットとデメリットがあります。メリットとしては、以下のような点が挙げられます。
① 赤字続きからの脱却
事業を継続することで赤字が拡大し、経営状況が悪化していく一方であれば、廃業を選択することで、これ以上の損失を防ぐことができます。
赤字が継続する事業を無理に続けることは、経営者の個人資産を蝕み、債務を増加させるだけでなく、従業員の雇用や取引先にも悪影響を及ぼします。
早めの決断で廃業に踏み切ることで、損失を最小限に抑え、新たな事業や就職に向けた準備を始められます。
② 債務の整理
事業継続中に借金を抱えている場合、廃業を機に債権者と協議し、債務を整理することが可能です。
事業が継続する見込みがない状況で、返済計画の見直しを行うことで、債務の一部免除や返済期間の延長などの条件変更を引き出せる可能性があります。
法的手続きを活用すれば、債権者との交渉がスムーズに進められ、債務の整理がしやすくなります。廃業後の個人の再スタートを切る上でも、債務の整理は重要な意味を持ちます。
③ 健康リスクの回避
事業の継続に伴う過度なストレスやプレッシャーは、経営者の心身の健康を損なうリスクがあります。無理に事業を続けることで、睡眠不足や食生活の乱れ、運動不足などを招き健康が脅かされる可能性も高くなります。
廃業を選択することで、こうした健康被害を避け、落ち着いてゆとりのある生活を送ることができます。心身ともに健康な状態で、新たなチャレンジや人生設計を考えられるのです。
廃業のデメリット
①信用がなくなってしまう
廃業は、事業の失敗を意味します。長年築き上げてきた取引先との信頼関係が、廃業によって大きく損なわれる可能性があるのです。
取引先からは、「あの会社は結局、事業をたたんでしまった」と否定的に評価されるかもしれません。廃業後に新たな事業を始める際には、この評価が足かせとなる恐れがあります。
②従業員の雇用を守れない
廃業は、従業員の雇用を奪ってしまいます。長年会社を支えてくれた従業員を、路頭に迷わせることにもなりかねません。
経営者にとって、従業員の雇用を守ることは重大な責務です。
③手続きが大変
廃業には、煩雑な手続きが伴います。債権者との調整、税務処理、従業員への説明など、やるべきことは山積みです。
特に、債権者との交渉は難航することが予想されます。円満な廃業を目指すためには、誠意を持って対応していく必要があります。
④のれんが消滅してしまう
廃業は、長年かけて積み上げてきた無形の資産を失ってしまうことを意味します。ブランドの知名度や、顧客との信頼関係など、目に見えない価値が消滅してしまうのです。
のれんは、事業の継続によって初めて意味を持つ資産です。廃業によってのれんが失われてしまえば、二度と取り戻すことはできません。
廃業のパターンは3種類

①自主的清算
自社の資産を売却して借金を返済し、残った資産を出資者に分配する方法です。債務超過でない場合に選択できます。
手順としては、まず株主総会で解散を決議し、清算人を選任します。その後、官報に解散公告を掲載し、債権者に個別の催告を行います。債権の申出期間が過ぎたら、債務の弁済や残余財産の分配を行います。最後に、清算結了の登記を行って法人格が消滅します。
自主清算は、裁判所を介さない点で比較的シンプルな手続きですが、債務の弁済原資を自力で確保する必要があります。弁護士や税理士などの専門家と連携しながら進めるのが賢明です。
②特別清算
裁判所に申し立てて行う法的手続きです。弁済の見込みがない場合に利用されます。
手順としては、債権者または株主から裁判所に特別清算開始の申立てを行います。裁判所が申立てを認めると、清算人が選任され、裁判所の監督下で清算手続きが進められます。清算人は財産の換価や債権の調査を行い、債権者集会を経て、裁判所の許可を得て弁済を実施します。その後、残余財産を株主に分配し、特別清算が終結します。
自主清算に比べ、手続きが複雑で時間もかかります。ただ、裁判所が関与する分、手続きの透明性や公平性は高いといえます。
③破産
債務超過で返済不能に陥った場合、裁判所に申し立てて免責を得る方法です。
手順としては、裁判所に破産手続開始の申立てを行います。裁判所が申立てを認めると、破産管財人が選任され、破産債権の調査や財産の換価・配当などを行います。そして、免責が決定され、残余財産が破産管財人に引き渡されれば手続き完了です。
破産すると、信用情報に傷がつき、その後の経済活動に大きな制約を受けます。再起を図る際のハードルは高くなりますが、債務から解放されるメリットもあります。状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
廃業を考える理由 – 経営難から高齢による引退まで
廃業を検討する理由は、経営者によってさまざまです。
業績の悪化
まずは、業績の悪化が挙げられます。売上の減少や利益率の低下で資金繰りが悪化し、赤字が続けば、廃業を選択せざるを得なくなります。コロナ禍のような予期せぬ事態で売上が激減するケースもあります。
また、借入金の返済が滞ったり、親会社や大口取引先の倒産に巻き込まれたりして、資金ショートに陥ることもあります。返済の目途が立たない場合は、廃業もやむなしでしょう。
市場環境の変化
一方、経営環境の変化に適応できず、事業の先行きに不安を感じて廃業を決断するケースもあります。
新技術の台頭や消費者ニーズの変化、競合他社の攻勢など、外部環境の変化は中小企業にとって脅威となり得ます。
高齢化
加えて、経営者の高齢化も大きな要因です。体力の衰えから事業の継続が難しくなったり、健康上の理由から引退を決意したりするのです。特に、跡継ぎ難民と呼ばれる後継者不在の中小企業では、廃業に追い込まれるリスクが高まります。
さらに、ここ数年は新型コロナウイルスの影響で、多くの中小企業が厳しい局面に直面しました。売上減少や営業自粛による資金繰りの悪化で、廃業に至るケースが相次ぎました。アフターコロナの現在でも、中小企業を取り巻く環境の厳しさは続いているのではないでしょうか。
廃業前に試したい経営改善策
とはいえ、安易に廃業を選ぶのは得策ではありません。事業の将来性を見極め、でき得る限りの経営改善策に取り組むことが大切です。
例えば、コスト削減や業務効率化による収益力の向上、新商品・新サービスの開発や新規顧客の開拓による売上アップ、金融機関との交渉による借入金の圧縮や返済条件の見直しなどが考えられます。事業計画の練り直しや組織体制の刷新で、業績を立て直すこともできるかもしれません。
また、M&Aによる事業売却も選択肢のひとつです。事業の全部または一部を他社に譲渡することで、債務を整理しつつ、従業員の雇用を承継してもらえます。M&Aの相手先を見つけるには、金融機関や事業引継ぎ支援センターを活用するのがよいでしょう。
このように、廃業の前にはさまざまな手を打つことが可能です。専門家のアドバイスを受けながら、できる限りの対策を行うことが重要と言えます。
廃業後は新たな人生のスタート
廃業は事業の終わりであると同時に、経営者の新たな人生のスタートでもあります。再起を期して別の事業に挑戦する人もいれば、趣味に生きがいを見出す人もいます。
とはいえ、廃業後の生活設計は簡単ではありません。生活費をどう工面するか、頭を悩ませる経営者も多いはずです。そこで活用したいのが、小規模企業共済制度です。
これは、小規模企業の経営者を対象とした公的な共済制度で、廃業後の生活資金を確保するためのセーフティーネットとして機能します。
掛金は全額所得控除の対象となり、共済金は退職所得扱いとなるなど、税制面でのメリットもあります。
また、国民年金の第1号被保険者であれば、国民年金基金に加入することで、より手厚い老後保障を得ることができます。将来設計を描く上で、こうした制度を上手に活用していくことが求められます。
廃業手続きの流れとポイント

最後に、廃業手続きの具体的な流れとポイントを確認しておきましょう。
会社を解散するプロセスは以下のように進められます。
- 株主総会の開催
- 解散の決議を行う
- 清算人の選任を行う
- 通常、代表取締役が清算人に就任する
- 清算人の役割
-
- 債権者に対する債務の支払い
- 残余財産の分配
- その他、清算に関する重要な業務の遂行
清算人は会社の清算において中心的な役割を担います。
債権者への適切な支払いや、残余財産の株主への公平な分配を確実に行うことで、会社の解散手続きを円滑に進めていく責任があります。清算人の選任は慎重に行われる必要があり、通常は会社の業務に精通している代表取締役が選ばれることが多いです。
次に、解散登記を行います。登記事項は、解散の事由、清算人の氏名・住所などです。同時に、官報に解散公告を掲載し、判明している債権者に対して個別の催告を発します。債権者から債権の申出があれば、順次弁済していきます。債務超過の場合は、債権者集会を開催し、債務の弁済方法などを協議します。
債権の弁済が終わったら、残余財産を株主に分配します。分配方法は定款の定めや株主総会の決議に従います。
清算事務が完了したら、清算結了の登記を行います。これで法人格が消滅し、会社の全ての活動が終了します。
ここで押さえておきたいのが、債務の弁済と残余財産の分配を、会社法の規定に則って適切に行うことの重要性です。清算人には、債権者や株主の利益を守るための善管注意義務が課されています。
例えば、債権者への弁済が不十分なまま、株主に残余財産を分配してしまうと、清算人の責任が問われる可能性があります。債権の調査を尽くし、適正な弁済を心がける必要があるのです。
また、清算の過程では、会計帳簿や重要な契約書類を整理し、法人税の清算申告を行うことも求められます。公認会計士や税理士などの専門家に依頼し、適切な事務処理を心がけることが大切です。
まとめ
廃業は、事業の継続が困難な状況に直面した際の選択肢の一つです。
赤字からの脱却、債務の整理、健康リスクの回避といったメリットがある一方で、信用の低下、従業員の雇用喪失、手続きの煩雑さ、のれんの消滅といったデメリットも伴います。
廃業を検討する際は、経営改善策をまずは実行してみてください。コスト削減、資金繰り改善など、あらゆる手を尽くした上で、やむを得ず廃業を選択するようにしましょう。
また、廃業手続きに際しては、会社法の規定に則り、債権者への適切な弁済と株主への公平な残余財産の分配を確実に行うことが求められます。
廃業は経営者にとって、重大な岐路となる意思決定です。
メリットとデメリットを慎重に検討し、専門家のアドバイスを参考にして、適切な判断を下していくことが重要です。
たとえ廃業を選択する場合でも、それは新たなスタートでもあります。前を向いて、再起に向けて一歩を踏み出していきましょう。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。