個人事業主の廃業に必要な手続きや書類とは?費用や確定申告の方法も解説
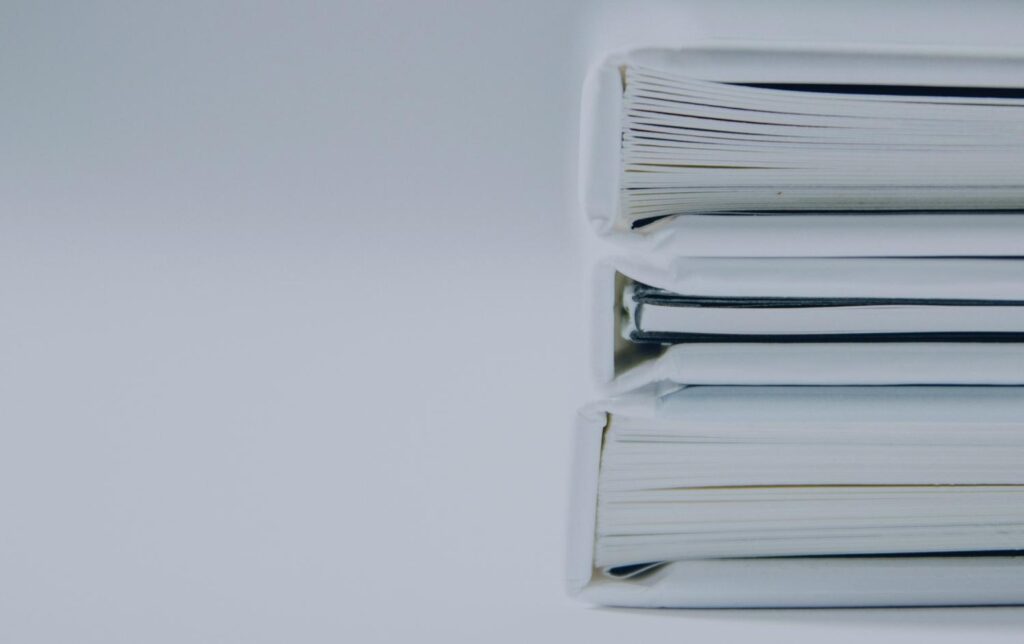
個人事業主の中には「個人事業主として事業を営んでいたが、廃業を検討している」
「廃業の際の手続きについて、詳しく知りたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。
個人事業主の廃業の際は、廃業届の提出が必要です。同時に、確定申告などの手続きが必要になるケースも多いため、適切な対応が求められます。
本記事では、個人事業主が廃業する際に必要になる手続きや書類について詳しく解説しています。また、廃業するデメリットや廃業以外の選択肢についても紹介しているので、廃業を検討している個人事業主の方は、ぜひ参考にしてみてください。廃業を決めた際には、正確な情報を得てスムーズに手続きを進めましょう。
目次
個人事業主における廃業とは?
法人における廃業と同じように、個人事業主が事業を終える場合も廃業と呼びます。個人事業主は、事業を始める際に「開業届」を、終える際に「廃業届」を税務署や地方自治体へ提出します。
廃業届を提出せずに事業を終えてしまうと、税務署から予定納税などで税金の支払いを求められる可能性があるため注意が必要です。個人事業主は、廃業届を提出することにより、事業を完全に停止したとみなされます。
また、個人事業主が株式会社などの法人に転換する「法人成り」のケースでも、廃業届の提出が必要です。
個人事業主が廃業するデメリット
個人事業主が廃業を選択することにより、以下のようなデメリットも発生するため注意が必要です。
- 事業を残すことができない
- 従業員を解雇しなければならない
- 資産売却による利益が減ってしまう
廃業の手続きを始める前に、デメリットも把握しておきましょう。以上の3項目について、詳しく解説します。
事業を残すことができない
個人事業主が廃業を選択すると、これまで築いてきた事業が完全に消滅し、継続できなくなります。
事業がうまくいかない、後継者がいないという場合は、廃業が頭をよぎるかもしませんが、廃業以外の選択肢もあります。例えば、M&Aを実施すれば事業を引き継いでもらえるだけでなく、売却益が得られる場合もあるため、廃業を避ける有効な手段です。。
自身が情熱を注いで育てた事業が消滅してしまうのは、個人事業主が廃業するデメリットの一つです。
従業員を解雇しなければならない
従業員を雇って事業を運営している場合は、廃業に伴い、彼らの解雇手続きを行う必要が生じます。
長年にわたり苦楽を共にしてきた従業員の解雇は、個人事業主にとっても大きな精神的負担となります。また、従業員側も次の就職先を探さなければいけなくなるなど、人生設計が大きく狂う可能性も出てくるでしょう。しかし、事業譲渡による廃業のケースでは、従業員にとってメリットがある場合もあります。
資産売却による利益が減ってしまう
個人事業主が廃業を選択すると、保有している設備や不動産などは売却が必要となります。その際、予想していた価格で資産を売却できずに利益が減るケースも少なくありません。
廃業に伴う資産売却では、処分を急いだり需要が低くなる傾向があるため、利益が期待通りに得られない場合があります。しかし、M&Aなどを活用した事業譲渡ならば、より高い金額で売却できる可能性もあるため、選択肢の一つとして検討してみましょう。
希望価格で資産を売却できずに利益が減るのは、個人事業主が廃業するデメリットとして挙げられます。
個人事業主が廃業する際の手続き方法
個人事業主が廃業する場合は、廃業届の提出が必要です。通常、廃業を決定してから1カ月以内の提出が目安とされ、受理されると廃業決定です。
廃業の手続きは、納税義務がなくなったことを国や都道府県に通知するために行います。また、従業員を雇用していた場合は、税金の徴収義務もなくなります。廃業時に廃業届を提出していない場合、国や都道府県は事業の停止を認識できないため、引き続き納税を求められる可能性があるので注意が必要です。
個人事業主は、廃業届を提出することで税金面でのデメリットを回避できるため、届出を忘れないようにしましょう。
個人事業主の廃業に必要な書類
| 必要書類 | 対象者 | 提出期限 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | すべての個人事業主 | 廃業日から1カ月以内 |
| 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告をしている個人事業主 | 廃業した翌年の3月15日 |
| 消費税の事業廃止届出書 | 消費税納税事業者 | 都道府県により異なる |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員を雇用している個人事業主 | 廃業日から1カ月以内 |
| 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減税申請書 | 予定納税をしている個人事業主 | 廃業した年の7月1日〜7月15日か11月1日〜11月15日 |
個人事業主が廃業する際は、いくつかの書類を提出しなければなりません。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 消費税の事業廃止届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減税申請書
廃業で提出する書類はさまざまな種類があるので、個人事業主の方は1つ1つ確認しましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業主が廃業する場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、廃業届)の提出が必要です。廃業届の提出期限は廃業日から1カ月以内と決められており、締切日が土日祝日に該当する場合は、翌営業日が期限となります。
廃業届の提出後は、事業のために使った費用が経費として認められなくなるため、廃業日の決定は慎重に行わなければなりません。また、廃業年度に税金が発生している場合、その年は確定申告が必要になるため注意が必要です。
廃業届は、提出が義務付けられているわけではありませんが、税法上必要な手続きです。廃業届を提出せずに放置していると、確定申告書や納税書が毎年送られてくる可能性があるため、忘れずに提出することが重要です。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
個人事業主が青色申告を行っていた場合、廃業に伴って「所得税の青色申告の取りやめ届出書」(以下、取りやめ届)の提出が必要です。
取りやめ届の提出期限は、青色申告を取りやめる年の翌年3月15日となります。例えば、令和5年の9月に廃業したケースでは、翌年の令和6年3月15日が取りやめ届の提出期限です。
取りやめ届は「個人事業の開業・廃業等届出書」と同時に提出するのが一般的です。取りやめ届には、青色申告書提出の承認を受けていた年分の期間や取りやめの理由などが詳細に記載される必要があります。期限日が近づいて慌てないように、余裕を持った対応が必要です。
確定申告時に青色申告を行っていた場合は、取りやめ届の提出を忘れずに行うよう注意してください。
消費税の事業廃止届出書
個人事業主の中で、消費税を支払っている課税事業者のみが提出する書類が「事業廃止届出書」です。事業廃止届出書の提出期限は都道府県により異なり、例として、東京都では廃業日から10日以内が期限日となっています。また、土日祝日は税務署の窓口では受け付けていませんが、時間外収受箱への投函や送付は可能です。
事業廃止届出書に記載する内容は多くなく、比較的容易に記入できるため早急に提出できるでしょう。事業廃止届出書も個人事業主の廃業時に必要な提出書類であるため、課税事業者の方はしっかり確認してください。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
個人事業主が従業員や専従者を雇って給与支払いを行っていた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」(以下、事務所廃止届)の提出が必要です。事務所廃止届の提出は、廃業日から1カ月以内が期限とされています。提出が遅れた場合、源泉所得税の納付も遅れが生じ、通常よりも税金の支払いが増えてしまいます。
また、従業員の給与から徴収している源泉所得税は、廃業日の翌月10日までの納付が義務付けられています。事業を行っていたときは半年に1度支払っていたというケースでも、廃業時には翌月10日までの納付が必要になるため、注意が必要です。
事務所廃止届は、従業員を雇っていた個人事業主にとって重要な提出書類です。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減税申請書
個人事業主が予定納税をしている場合は、廃業により見積額が減少する可能性があるため「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減税申請書」(以下、減税申請書)を提出して納税額の減額を申請できます。
予定納税の減額を申請する場合は、減税申請書だけではなく、申告納税見積額を計算するための基礎となる事実が記載された書類が必要になります。減税申請書を提出できる期間は決まっており、第1期分および第2期分はその年の7月1日〜7月15日まで、第2期分のみの場合は11月1日〜11月15日までです。提出先は管轄の税務署になりますが、期限日が土日祝日の場合は翌営業日になります。
減税申請書の提出を忘れると不要な税金の支払いを行う可能性もあるため、注意が必要です。
個人事業主の廃業届の書き方
廃業を決定してから1カ月以内に提出が必要な廃業届は、正確に記入しなければなりません。ここでは、廃業届に記載する主な内容を説明します。
| 記載する情報 | 詳しい記載内容 |
| 税務署の情報 |
|
| 個人情報 |
|
| 廃業の情報 |
|
| 法人成りの情報 | 廃業後に法人を設立する場合
|
| その他 |
|
個人事業主が廃業するときにかかる費用
通常、法人の廃業には多くの費用が発生しますが、個人事業主の廃業でも以下のような費用がかかります。
- 設備処分
- 店舗の原状回復
- 在庫処分
廃業届の提出に費用はかかりませんが、設備処分などに費用がかかります。
設備処分
個人事業主が廃業するときには、事業で使用していた設備を廃棄または売却する必要があります。事業規模に応じて処分が必要な設備の量は異なりますが、一般的には規模が大きくなればなるほど処分が必要な設備も増えていきます。
一部の設備は売却して利益を得ることも可能ですが、古くなって買い手が見つからないものや、正常に稼働しないものなどは廃棄処分が必要です。業者に廃棄処分を依頼する場合は、少量でも数万円かかるケースがあるので注意が必要です。
個人事業主が事業で使用していた設備は、何らかの方法で処分しなければならないため、事前に検討しておくことが重要です。
店舗の原状回復
工場や倉庫、店舗などの物件を借りて事業を営んでいた個人事業主は、廃業の際に原状回復をしなければなりません。原状回復とは、借りていた物件から退去する際に、入居前の状態に戻すことを指します。
通常、経年劣化や一般的な使用による損耗は貸主が負担しますが、故意や過失による損傷は個人事業主が原状回復費用を負担する必要があります。原状回復には費用がかかるため、廃業時の費用の中でも重要な要素となります。
個人事業主が廃業する際には、原状回復費用についても十分に理解し、事前に貸主との契約内容を確認することが重要です。
在庫処分
個人事業主が物品の販売を行っていた場合は、廃業後に売れ残った在庫を処分しなければなりません。処分方法によっては費用が発生するため、慎重に対処する必要があります。
在庫の処分方法としては、以下のような選択肢があります。
- 大幅に値引きして販売する
- 廃業前に発注を徐々に減らす
- 全て販売してから廃業する
すべての在庫を売り切った場合は問題ありませんが、少しでも残っていると費用が発生する可能性があるため、注意が必要です。
従業員への退職金
個人事業主が退職金制度を設定して従業員を雇っていた場合、廃業の際には従業員への退職金支払い義務が発生します。従業員への退職金の支払いも、個人事業主が廃業の際に発生する費用の一部です。
個人事業主の中には、退職金の支払いに備え、中小企業退職金共済制度に加入している方もいると思いますが、その場合は費用は発生しません。非課税枠がある退職金の支払いは、金額が高くなる場合があるので注意が必要です。
従業員がいる個人事業主は、廃業の際に退職金制度の設定や共済制度の活用を確認し、適切な対応を行うことが重要です。
個人事業主が廃業した年の確定申告は?
個人事業主が廃業した場合、確定申告を行う必要があるかどうかは、いくつかの条件により異なります。
まず、廃業した年に所得があった場合は確定申告が必要です。ただし、所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。また、廃業した年の所得が赤字であった場合も確定申告は必要ありません。
青色申告を利用していた場合は、廃業した年でも確定申告が必要です。なぜなら、青色申告の特別控除を受けるためには確定申告が必須であるからです。
確定申告の期限は、廃業した年の翌年の2月16日から3月15日までとなります。ただし、申告漏れを防ぐためには早めの手続きが望ましいです。
廃業した個人事業主の確定申告は、所得状況や利用していた申告方法によって異なるため、個別に注意が必要です。
確定申告で利用可能な必要経費の特例
個人事業主が廃業した場合、廃業後にかかった経費を特例として認められるケースがあります。通常、経費は事業を継続しているときに発生するものですが、廃業後にかかる費用も珍しくありません。例えば、商品の在庫処分費用や、物件を借りて事業を行っていた場合の原状回復費などが挙げられます。
廃業後の経費が認められるのは、個人事業主が以下に当てはまる場合です。
- 製造業や卸売業等で事業所得を得ていた者
- 山林所得や不動産所得を得ていた者
また、特例として認められるための条件は以下の通りです。
- 廃業せずに事業を続けた場合、必要経費として計上できたもの
- 事業所得や山林所得、不動産所得などの自身が営む事業の経費
これらの条件を満たす場合、廃業にかかる経費として確定申告時に計上できます。経費が認められた場合、納税額を抑えられるため、費用計上を忘れないようにしましょう。
廃業後の確定申告における減価償却
個人事業主が廃業した場合、その年の減価償却は廃業日までの分を行います。例えば、6月30日に廃業した場合、その年の1月1日から6月30日までが減価償却の対象時期になります。
廃業後に残った減価償却資産の処分方法によって、会計処理が異なります。一般的には、以下の2つの扱い方があります。
- 資産を廃棄した場合は「固定資産除却損」として処理
- 資産を売却した場合は残った減価償却分を「譲渡所得の取得費」として処理
固定資産除却損と譲渡所得の取得費は、どちらも費用計上できるため確定申告時に算入が必要です。また、個人事業主が廃業後に減価償却資産を再利用する場合は、会計処理は必要なく確定申告への影響もありません。
減価償却資産の処分方法によって会計処理が変わるため、廃業時には適切な処理を行うように注意しましょう。
廃業後の確定申告の在庫処理方法
物品の売買を行っていた個人事業主は、廃業後に在庫が発生するケースがありますが、確定申告時の扱いは前年度の会計処理方法により異なります。在庫を処分した場合の会計処理は以下の2通りです。
- 在庫を前年度に資産計上していたときは廃棄物になるため費用計上
- 在庫を前年度に費用計上していたときは会計処理の必要なし
(ただし、在庫は本来前年度に資産計上することが正しく、前年度に費用計上したままとなっている場合、前年度の修正申告が必要になる場合もあります)
また、在庫を売却して処分した場合は売上になるため、確定申告時に計上する必要があります。特に在庫を資産にしていたときは費用として計上できるため、確定申告時に忘れずに申告すると節税効果が見込めます。
廃業後に在庫の処分や売却を行う場合は、前年度の会計処理方法や税務上の規定に基づいて適切な会計処理と確定申告を行うことが重要です。
個人事業主が廃業する際の注意点
個人事業主が廃業する場合は、さまざまな注意点が存在するため、事前に把握しておくことをおすすめします。
- タイミングの選定
- 廃業費用・手間を把握する
- 廃業手続きを行う
廃業は突然行うものではなく、事前の計画が重要です。個人事業主が廃業する場合は、慌てずに必要な項目を確認しましょう。
タイミングの選定
個人事業主が事業の継続を断念し廃業を決めた場合は、焦らずにタイミングを見極めることが重要です。個人事業主は廃業日に関する規定がないため、自分の好きなタイミングで廃業届を提出できるためです。
可能であれば、個人事業主の廃業は年末に合わせるのが良いでしょう。廃業にかかる費用を経費として扱えるため、1年間の売上から差し引くことで税金の支払いを抑えられます。また、廃業を翌年に行ってしまうと、次の年も確定申告をする必要が出てくるため、無駄な手間がかかってしまいます。
個人事業主が廃業する際は、最適なタイミングを選んで行うようにしてください。
廃業費用・手間を把握する
個人事業主が廃業する際には、費用や必要になる時間などを事前に確認しておくと、廃業手続きがスムーズに進みます。
一見すると個人事業主の廃業は法人に比べると簡単に思えますが、実際は意外と手間がかかります。特に廃業に関する費用は、思わぬ形での発生が少なくありません。例えば、書類の手続きを個人事業主自ら行えば費用は発生しませんが、代行業者に依頼すると手数料がかかります。また、設備や在庫の処分は費用も手間もかかるので、計画的に進める必要があります。
廃業に関する作業を進める際は、しっかりとスケジュールを立てて実行してください。
廃業手続きを行う
個人事業主の事業は規模が小さいケースも多々あるため、人によっては廃業の手続きを行わない場合もあります。しかし、個人事業主が廃業手続きを行わないと、税務署は事業を続けていると見なすため、確定申告の書類を送付します。
税務署から送られる確定申告の書類を放置していると、場合によっては「無申告加算税」が課せられるケースもあるため、注意が必要です。
個人事業主でも廃業の際は廃業届を提出し、事業を継続しないという意思表示をすることを忘れないようにしましょう。
廃業以外の別の道を模索する
さまざまな理由から事業に行き詰まりを感じ、廃業を考える個人事業主も少なくありませんが、他の方法も検討が必要です。
個人事業を手放す方法は、廃業の他にM&Aという選択肢もあります。他の会社に売却することにより、自らが育てた事業を存続させるだけではなく、従業員を雇っていた場合は彼らの再雇用も期待できるかもしれません。また、廃業はさまざまな費用が発生しますが、M&Aで売却すると個人事業主の利益にもつながります。
廃業は一つの手段ですが、個人事業主は他の方法での事業の存続も検討してみてください。
個人事業主が廃業以外に検討できる選択肢
個人事業主が事業を終えるときは、廃業以外にもいくつかの選択肢が存在します。
- 個人事業主でもM&Aは可能
- M&Aに適した個人事業の特徴
廃業を選択すると、育てた事業が消滅してしまったり、費用が発生したりするデメリットがありますが、M&Aでは個人事業主の負担が少ない形で事業承継が行えます。廃業を検討している個人事業主の方は、さまざまな視点から自身の事業を見つめ直してください。
個人事業主でもM&Aは可能
M&Aと聞くと、企業同士の買収や合併をイメージしやすいですが、個人事業でもM&Aは行われています。
最近は副業を行う会社員が増えていますが、M&Aにより個人事業を買収しようと考えているケースも少なくありません。自分でイチから副業をスタートさせるのは労力が必要であることから、すでに事業として成り立っている個人事業を買収して、すぐに利益を得たいと考える方は多いためです。
また、M&Aにより事業売却することで、個人事業主には売却益が入ります。通常、廃業ではさまざまな費用が発生しますが、M&Aをすると無駄な出費を抑えられます。
個人事業主は、事業を辞める際に廃業を考えるケースが多いですが、M&Aでの事業売却も検討してみると良いでしょう。
M&Aに適した個人事業の特徴
個人事業の売却においては、買い手がつきやすい事業が存在します。
- 伝統技術や専門知識がある事業
- 設備や施設がある事業
- 許認可が必要な事業
代わりの利かない事業や、必要な設備や認可が揃っている事業は、M&Aの際に有利に働きます。個人事業主の方は、自身の事業の強みを確認し、M&Aも選択肢に入れてみましょう。
伝統技術や専門知識がある事業
代々継承されてきた技術や、他社にはない強みがある事業は、M&Aに適しているといえるでしょう。
独自色の強い事業は、競争相手が少ないことから利益が安定しやすく、買い手にとっては魅力的な事業です。また、伝統を引き継いで行っている事業も、すぐに真似できるものではないため、求める買い手は少なくありません。
独自の知識や長年かけて築いた技術がある事業は、M&Aで引き継ぎを検討してみましょう。
設備や施設がある事業
事業を行うためには場所や設備が必要になるケースが多いですが、これらをすでに揃えている事業はM&Aに向いています。
新たに事業を始める際は、設備や施設への投資が必要になり、費用負担が大きくなってしまいます。M&Aですでに基盤が完成されている事業を買収することで、すぐに営業できるようになり、買い手にとってはメリットが大きいです。
さまざまな設備を整えて事業を行っている個人事業主は、M&Aでの事業売却を検討してみましょう。
許認可が必要な事業
業種によっては、行政機関から許認可を得る必要がありますが、すでに許認可を得ている事業はM&Aに適しています。
許認可が必要な事業はさまざまありますが、多くの場合、審査に数カ月かかります。M&Aで事業を買収することで、許認可の審査を待たずに事業を開始できるため、買い手にとっては大きなメリットとなります。
しかし、個人事業主の場合は、引き継ぎができる許認可事業が限られているため注意が必要です。
- 建設業
- 旅館業
- 一般ガス導管事業
- 一般旅客自動車運送事業
- 一般貨物自動車運送事業
- 火薬類製造業・火薬類販売業
以上の業種では、許認可の承継が可能です。
許認可の取得は手間も時間もかかるため、すでに取得している事業を行っているのであれば、M&Aを検討してみると良いでしょう。
まとめ
個人事業主の廃業は、多くの手間や費用が発生するため注意が必要です。
- 個人事業主の廃業にはさまざまな書類の提出が必要
- 従業員の解雇や事業消滅のデメリットがある
- 設備や在庫の処分などで費用が発生する
- 廃業年に税金が発生していれば確定申告が必要
- 廃業以外にもM&Aという選択肢もある
廃業は労力がかかり、従業員の解雇やさまざまな書類の提出など、精神的にも負担の大きい行為です。M&Aなど廃業以外の選択肢も検討すると、愛着のある事業を消滅させずに済む可能性もあります。
個人事業主の方は廃業を決める前に、さまざまな可能性を探ってみてください。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


