ガソリンスタンド廃業の流れ|廃業後なぜ放置されている?廃業以外の選択肢
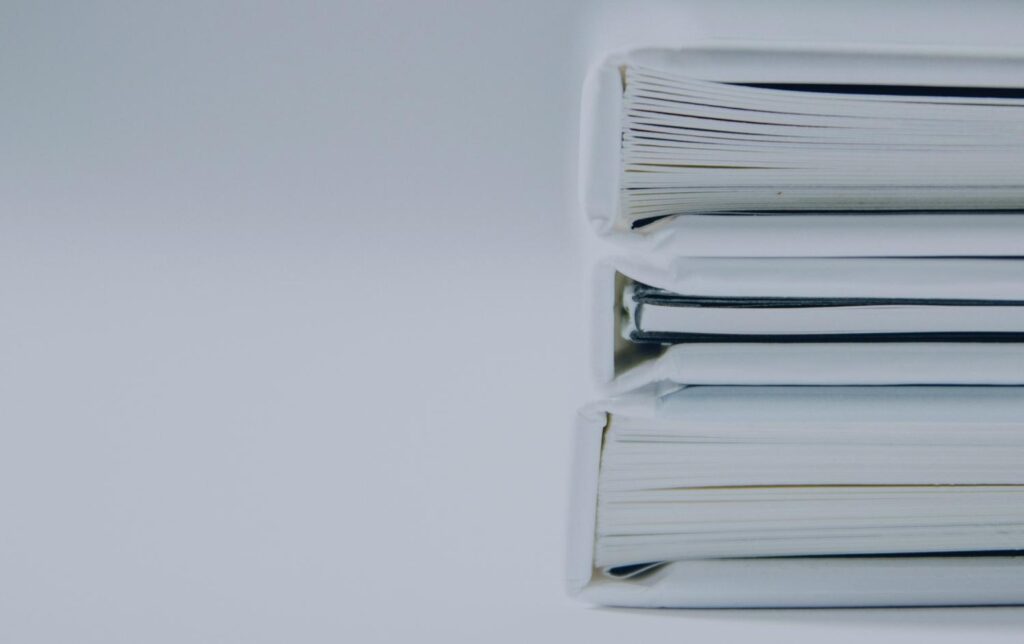
目次
はじめに
ガソリンスタンドの廃業は、役所での手続きや設備の解体・撤去など、さまざまな面で手間と費用がかかります。廃業を検討しているものの、どのような流れで手続きをすべきか迷っている方も多いでしょう。この記事では、ガソリンスタンド廃業の流れや廃業以外の選択肢などについて解説します。ガソリンスタンドの廃業を検討している方や廃業を回避したい方に役立つ情報を紹介しますので、ぜひご参考ください。
ガソリンスタンドにおける廃業手続きの流れ
1.ガソリンスタンド廃業までのスケジュールを立てる
ガソリンスタンドは危険物を取り扱っているため、廃業の際は一般的な廃業手続き以外にもさまざまな作業がともないます。例えば、ガソリンタンクは撤去もしくはタンクにコンクリートを流して使用できないようにすることなどです。
また、土壌汚染調査などの実施も求められており、全作業を終えるためには業者と連携を取りながら進めていくことが大切です。遅くとも2年前には廃業に向けたスケジュールを立て、遅滞なく手続きを終えるための体制を整える必要があります。
2.ガソリンスタンドの資産や債務を整理する
次に、資産や債務の整理を行います。債務に関しては、金融機関からの借り入れが大半を占める場合がほとんどです。資産としては洗車台や給油機などが挙げられますが、他業種では需要が低いため、専門の業者に売却することになります。
また、ガソリンスタンドがあった土地をほかの用途で使う場合は、地下タンクを撤去しなくてはなりません。タンクを撤去せずに放置していると、土地の売却額が下がったり、ガソリンにより土地が汚染されたりするおそれがあります。
たとえ資産と債務を整理した後に資産が余っていることがわかっても、タンクの撤去や汚染の浄化などで多額のコストが発生する場合もあります。
3.ガソリンスタンド廃業手続きを行う
ガソリンスタンドを廃業する際には「指定作業所等廃業届出」のほか、「揮発油販売業廃止届書」や「石油販売業廃止届書」などを指定の期間に提出します。
指定作業所等廃業届出書は、廃業から30日以内にガソリンスタンドが所在する自治体に提出します。届出の前に土壌汚染調査を必要とする場合があるため、廃業の計画を立てる際には事前に各自治体に問い合わせてください。
揮発油販売業廃止届書は、ガソリンスタンドを完全に廃業する際に遅滞なく経済産業大臣に提出する必要がある届出です。備蓄法にもとづいて、石油販売業廃止届出書も一緒に提出することになります。ガソリンスタンドの所在地を管轄する経済産業局にて手続きを行いましょう。
4.確定申告などの法的手続きを行う
法人の場合、廃業する際には株主総会での解散決議や清算人の選任決議が必要です。決議後、会社が解散する日から2週間以内に解散と清算人選任の登記を行います。登記を終えたら、自治体や社会保険事務所、税務署などに会社解散の届出をするのが基本的な流れです。
また、解散確定申告と清算確定申告も行う必要があります。解散確定申告とは、事業年度が始まる日から解散日までを1事業年度と捉え、税務署に対して確定申告を行う手続きのことです。解散日から2カ月以内に届出をします。
清算確定申告は、資産と債務の整理を行い、残余財産が決まった後に行う確定申告です。清算期間に所得が生じた場合は、税金を納める必要があるため注意しましょう。
ガソリンスタンド廃業にかかる費用
ガソリンスタンドの規模によって変動しますが、廃業にかかる費用は300万円~1000万円が目安です。ただし、土壌が汚染されていることが確認された場合は、数千万円単位の費用が発生する可能性もあります。
また、地下にあるガソリンタンクの撤去方法も、廃業にかかる費用を左右する要素のひとつです。地下から完全に取り除く方法は埋め立てよりも手間がかかるため、高額になる傾向にあります。
想定以上の費用がかかるときは「一般社団法人 全国石油協会」の補助金制度を活用することも一案です。補助金を受けるためには一定の条件や審査をクリアしなければならないため、事前にご確認ください。
ガソリンスタンド跡地が放置されている理由
ガソリンスタンド跡地が放置される理由として、簡単に売却できない点が挙げられます。
ガソリンスタンド跡地の場合、地盤の問題や土壌汚染が予想されるため、調査や対策などを行わない限り、基本的には売却できません。
現在のガソリンには、土壌汚染の原因となる特定有害物質はほとんど含有されていないものの、30年、40年と長期にわたってガソリンスタンドを運営していた跡地では有害物質が発見される可能性があります。有害物質は自然に消えることはないため、浄化作業を行わなければ跡地を利用できません。また、地下タンクを撤去する際に適切な対応が取られなかった場合、地盤の安定性が低下しているリスクがあることも跡地が放置される原因のひとつです。
ガソリンスタンド跡地の活用方法
ガソリンスタンド跡地を売却する
跡地の活用には、建物を解体して更地の状態にしてから売却する方法や居抜き物件として売却する方法があります。ただし、ガソリンスタンドの跡地は通常の土地とは異なり、事前に地盤改良や土壌汚染の浄化作業が必要となる場合も珍しくありません。そのため、売却する際は、事前に跡地の状況を確認することが大切です。
ガソリンスタンドは車通りの多い場所に設置されていることが多いため、立地条件は優れています。実際に、携帯ショップやコンビニ、飲食店などに跡地が活用されているケースも多く、売却できる可能性は十分にあります。
ガソリンスタンド跡地を再利用する
周囲に競合がいない場合は、セルフガソリンスタンドとして再利用する方法があります。既存の設備を活用できることに加え、セルフ形式によって人件費も抑えられるため、従来より高い利益を得られる可能性があります。
また、広々とした敷地を活用し、トランクルームを経営するのも選択肢のひとつです。車がアクセスしやすい立地を活かしてロードサイド店としてカフェを経営したり、遊休地として物置き場や趣味を楽しむ場にするといった方法も考えられます。
ガソリンスタンドにおける廃業・跡地売却以外の選択肢「M&A」
M&Aとは、企業の合併・買収を表す言葉であり、企業や事業のすべて、もしくは一部の売却を伴う取引を指します。ガソリンスタンドに関しては、以下のいずれかによって買収を行うのが一般的です。
・事業譲渡
・株式譲渡
事業譲渡
事業譲渡とは、社内にある事業のすべて、または一部を買い手側に売却する手法です。例えば、会社Aがガソリン事業を手掛ける「事業C」を手放したいと考えている場合、会社Bに対して「事業C」を売却して対価を得る、という流れになります。経営権は会社Aに残るため、事業のみを売却したい場合におすすめです。
ただし、ガソリンスタンド事業者(揮発油販売業者)が全事業を買い手側に譲渡しない限り、揮発油販売業者の地位が引き継がれることはありません。給油所の一部を譲渡する際は、事業者の交代による変更登録手続きを行うことになります。
また、手続きが複雑になりやすい点にも注意が必要です。どの範囲まで事業を譲渡するのかしっかり検討し、手続き方法も事前に確認するようにしてください。
株式譲渡
株式譲渡とは、自社株の売買を通じて買い手側に経営権を譲渡し、対価を得る手法のことを指します。事業譲渡と比べ、簡単な手続きでM&Aを行えます。
譲渡後は、売り手側が持つすべての権利義務を買い手側が受け継ぐことになります。ガソリンスタンドを運営している会社の場合、揮発油販売業者の地位も引き継がれるのが基本です。
ただし、株式譲渡では買い手側に経営権が移るため、法人の代表者が変わることが一般的です。代表者が変わった場合、変更届を経済産業大臣に出さなければならない点には注意してください。
また、買い手側が受け継ぐ権利義務の中には、資産だけでなく負債も含まれます。会社の財務状況によっては、買い手が見つかりにくい場合があるので注意しましょう。
ガソリンスタンドのM&Aにおける譲渡相場
ガソリンスタンドのM&Aにおける譲渡相場は、規模や立地などさまざまな要素で変動します。ただし、以下で解説する譲渡価格に反映される要素と譲渡価格の算出方法をもとにすれば、自身が運営するガソリンスタンドの譲渡価格の相場感を掴めます。
ガソリンスタンドにおける譲渡価格の決定要素
まずは、譲渡価格の決定要素について解説します。
ガソリンスタンドの利用者数
日頃から利用者数が安定しているガソリンスタンドは利益も安定しやすいため、高い評価を得られます。一方で、たとえ車通りの多い街の中心部や幹線道路沿いに店舗があったとしても、利用者数が少ないのであれば安定した収益は見込めません。M&Aの評価で「継続的な経営は難しい」と判断される可能性があります。
ガソリンスタンドの立地
好立地のガソリンスタンドは、譲渡価格が高くなる場合があります。例えば、周囲に競合となる店舗がない、車が多数通る幹線道路沿いに位置している、人口の多い街にある、といった要素が好立地の条件として挙げられます。
また、公共交通機関が乏しく車以外に移動手段がない地域もガソリンスタンドの需要が高いため、立地がよいと判断されます。
ガソリンスタンドの財務情報
財務情報から「安定した黒字経営が継続されている」と判断された場合、買収後も一定の利益を期待できるため、M&Aでの評価も高くなります。一方で、安定した利用者数を得ていたとしても、赤字経営が何年も続いている状態の場合は評価が下がってしまいます。また、多額の債務がある場合も低い評価を受けてしまいます。
ガソリンスタンドの従業員数
従業員数の多さは、買い手側からの高評価に影響します。従業員数が不足している場合、新たに雇うための時間や労力、コストが生じるだけでなく、1から業務を教える手間をかけなければなりません。
業務を熟知し、即戦力となる従業員がいれば余計な手間をかけることはなくなります。少しでも高額で売却するのであれば、従業員の充実度を高めておくとよいでしょう。
ガソリンスタンドの譲渡価格の算出方法
次に、ガソリンスタンドの譲渡価格の算出方法について解説します。
年倍法
年倍法(年買法)とは、会社が有する時価純資産に数年分の営業利益を加え、会社の価値(≒買収額)がどの程度になるのか算出する方法です。一般的に、3〜5年分の営業利益を加算します。計算式は以下の通りです。
・時価純資産+営業利益×3~5年分=企業価値
例えば、時価純資産3000万円、過去5年の平均営業利益が2000万円だった場合は以下のように算出できます。
・3000万円+2000万円×5=1億3000万円
時価純資産と営業利益がわかれば、すぐに価値の目安を算出できるところが利点です。ただし、過去の利益を基準としているため、将来的に期待できる利益を保証する数値ではない点には注意してください。
類似会社比準法
類似会社比準法とは、同様の事業を手掛けている上場企業の株価をベースに自社の株価を計算する方法のことです。1株あたりの利益や配当金、純資産から上場会社との比較を行い、自社の株価を算出します。
事業内容が似通った会社の指標を用いるため、高い客観性を保ちながら会社の価値を計算できるのが特徴です。一般的に、事業の規模が大きい会社ほど類似業種比準法による評価の比重が大きくなります。
ただし、売り手側の会社が独自に有している価値を反映できない点や、類似事業を手掛ける上場企業が見つからない場合がある点については注意が必要です。
ガソリンスタンドをM&Aで譲渡するメリット
従業員の雇用維持
廃業を選択した場合、従業員は職を失うことになります。今まで一緒に働いてきた従業員を解雇するのは、経営者として心苦しいものがあるでしょう。
M&Aを行えば、買い手側に対して従業員の雇用を引き継げます。事業譲渡で事業のみを買い手側に譲渡したとしても、従業員の再雇用契約を条件にすることで雇用関係の継続が可能です。
後継者不足問題の解消
近年は、後継者不足や、後継者の候補はいるものの株式の取得に十分な費用を用意できないなどの理由で後継者を獲得できず、廃業するケースも少なくありません。たとえ業績が好調でも、後継者がいなければ廃業することになるでしょう。
M&Aによって第三者への事業継承を選択すれば、後継者の有無にかかわらず、廃業せずに事業を続けられます。
個人保証・担保の解消
事業継承によって家族や従業員に事業を引き継いでもらっても、個人保証や担保の継承は拒否される場合も少なくありません。M&Aの譲渡契約で個人保証や担保の解消を条件に含め、金融機関と交渉した上で買い手側に引き継げれば、売り手側は負担から開放されます。
事業を引き継いだ後に個人保証や担保による経済的・心理的な重荷を背負わないようにできることも、M&Aのメリットです。
まとめ
ガソリンスタンドを廃業する際には、他業種とは異なる手続きを踏まなければならないため、スケジュールを立てた上で計画的に進めていくことが大切です。廃業の際には解体や撤去に多額の費用がかかる場合がある点にも注意しましょう。
ガソリンスタンドの跡地を売却したり、再利用したりする方法もありますが、事業の継続を望むのであればM&Aを選択することも一案です。M&Aなら従業員の雇用が維持され、個人保証や担保を解消できる可能性もあります。M&Aには専門的な知識が必要であるため、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。


