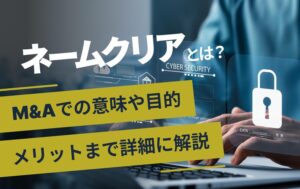飲食店の廃業手続きとは?個人事業主・法人別に必要な手続きや届出を紹介

目次
はじめに
資金繰りの悪化などで廃業を検討する飲食店オーナーは少なくありません。この記事では、飲食店の廃業手続きを個人事業主・法人別に解説します。また、飲食店の廃業方法以外に、廃業を回避する方法についても触れているので、ぜひご参考ください。
【個人事業主】飲食店の廃業手続き方法
1.廃業に関する事前準備を行う
まずは、廃業までのスケジュールを決めることが大切です。金融機関への相談や物件の解約通知など、廃業の際にしなくてはならないことは多数あります。また、財産を整理して廃業後に残る現金を算出する必要もあるため、余裕を持って計画を立てていきましょう。
金融機関に相談する(借り入れがある場合)
借り入れの完済前に廃業する場合でも、金融機関に対する毎月の返済義務はなくなりません。何も申し送りしないまま返済を続けるのではなく、金融機関に廃業したことを伝えましょう。金融機関側から見ると融資の対象が失われたことになり、追加融資や返済期限を変更する必要があるためです。
ただし、廃業したとしても、残りの額を一括で返済する必要はありません。また、毎月の返済でしっかり完済しておけば、将来再び店舗を開く際に融資を受けやすくなります。
リース契約の残債を清算する(リース品がある場合)
店舗の設備をリースで借りていた場合は、リース会社に連絡して廃業の旨を伝えましょう。リースされた設備はリース会社の所有物に該当するため、返却の手続きをして残債を返済することになります。
廃業のタイミングによっては、多額の残債があり一括での返済が困難なケースも少なくありません。そのような時は、返済方法についてリース会社に相談しましょう。
不動産管理会社へ解約を通知する(テナント契約の場合)
賃貸物件で店舗を運営していた場合は、物件の所有者や不動産会社に賃貸借契約の解約通知を行います。通常、廃業したからといってすぐに賃貸借契約を解約することはできず、事前の通知が必要です。飲食店の場合、3〜8ヵ月前には通知をするのが一般的ですが、契約内容によるため確認しておきましょう。
2.従業員や取引先に廃業することを通達する
従業員を雇っている場合は、解雇の30日以上前に廃業による解雇通知をします。正当な手順で解雇通知を行わないと、不当解雇として訴えられるリスクがあるため注意が必要です。
解雇通知をする際に、従業員の混乱を防ぐために説明会を開くことも有効な手段です。廃業についてしっかり説明をすることで、従業員の理解を促し、店舗を閉鎖するまでのモチベーションを維持しやすくなります。
また、取引先にも廃業の通知が必要です。取引の有効期間や廃業日を伝えるようにしてください。
3.各行政機関へ届出する
飲食店はさまざまな行政機関から認可を受けて営業しているため、廃業する時も各機関での手続きが必要です。届出をする先は、消防署や保健所、税務署など多岐にわたるため、事前に整理しておかないと、手続き漏れが発生する可能性があります。
提出先や提出物の種類については後述しますので、参考にしてみてください。
4.リース品の返却やライフライン・保険の解約を行う
リース品はリース会社の所有物であるため、必ず返却の手続きを行います。また、ガスや電気、水道の解約のほか、加入している保険がある場合も解約手続きを忘れないようにしましょう。
さらに、店内を入居前と同じ状態にする「原状回復工事」も行わなければなりません。クロスや床の張り替え、クリーニングなどを実施し、きちんと復元してから退去するのが原則です。なお、居抜きによって店舗を売るのであれば、原状回復工事は必要なくなります。
【法人名義】飲食店の廃業手続き方法
1.飲食店の営業を終了する
廃業の手続きを始める前に、店舗の営業を終了する必要があります。店舗の解約予告期間や原状回復工事の期間などを踏まえた上でスケジュールを組み、営業を終了する時期を決めましょう。
例えば、解約予告期間が6ヵ月と定められているのであれば、予告からも6ヵ月は家賃を払い続けることになります。その点を踏まえて、営業を終了するのに適した時期を検討しましょう。
2.解散決議と清算人を選任する
法人の場合、株主総会で解散の決定と清算人選任の決議を行うことになります。清算人とは、法人が解散した後の清算行為を担当する立場のことであり、経営者が担うケースが大半です。具体的には、不動産の解約や名義の変更、債務の整理、債権の回収などを行います。
解散と清算人選任の決議を行った後は、法務局で解散と清算人選任に関する登記をするのが基本です。また、行政機関に対する手続きも行うことになります。
3.通知・官報公告を行う
法人を解散する際には、全債権者に対して債権を主張する機会を設けるために、解散の通知と官報公告を実施します。基本的に、2ヵ月以上の公告期間を設けなければなりません。また、解散時の貸借対照表と財産目録を作り、株主総会で承認を受ける必要もあります。
4.財産・債務の整理を行う
2ヵ月以上の公告を終えると、債務の弁済が可能になります。債務の整理や債権の回収が終わっていないと廃業できないため、すべての手続きを終わらせましょう。借入金の一括返済が難しい場合は、分割払いが可能であるか債権者と交渉することになります。
清算後、財産が残っている場合は株主に分配します。経営者が全株式を持っているのであれば、残った財産は経営者のものになるのが原則です。
5.会社清算に必要な手続きを行う
会社清算では、解散事業年度の確定申告と清算事業年度の確定申告を行うことになります。解散事業年度とは、事業年度が始まった日から解散日までの期間であり、解散日の翌日から2ヵ月以内に確定申告を行って税金を納める必要があります。
清算事業年度は、解散日の翌日から1年ごとの年度を指します。事業年度が終わった日の翌日から2ヵ月以内に確定申告と納税を行うのが基本です。なお、債務を返した後に残った財産の確定日を含む清算事業年度では、確定日から1か月以内に「残余財産確定事業年度の確定申告書」を提出します。
6.清算結了の登記を行う
清算結了の登記とは、解散後に清算手続きを行い、会社がなくなったことを表すものです。株主総会で清算事務報告を認められてから、2週間以内に登記をする必要があります。
手続き後、会社の登記は閉鎖扱いになるため、再び会社を復活させることはできません。清算結了の登記を終えたら、遅滞なく市区町村の役場や都道府県税事務所、税務署などに届出を行います。
【行政機関別】飲食店を廃業する場合に必要な届出
消防署
消防法第8条では、防火管理者を解任した時に「防火管理者解任届出書」の提出が求められています。届出の際には、原則として防火管理者の有資格者であることを証明する書類も一緒に提出するため、経歴証明書の写しや防火管理講習修了証の写しなどを用意しましょう。
届出に記載する解任日は、廃業をした日です。建物が所在する住所を管轄する消防署に提出をしてください。
警察署
店舗で深夜0時以降に酒類を提供しており、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出していた場合は、「廃止届出書」の提出が必要です。店舗の所在地を管轄する警察署の公式サイトで届出書をダウンロードし、必要事項を記入した上で出しましょう。
また、風俗営業許可を得てキャバレーやスナックなどを運営していた場合は「風俗営業許可証」の返納が必要です。「返納理由書」を添えて管轄の警察署へ提出します。
どちらの届出も店舗の営業を終えてから10日以内に提出が求められています。風俗営業許可証の返納は、期限に遅れると罰金が課せられることもあるため忘れずに手続きを行ってください。
保健所
保健所には「廃業届」を提出します。店舗の営業を終えてから10日以内に提出するのが一般的ですが、自治体によって異なるため事前に確認しておきましょう。
また、「飲食店営業許可書」の返納も必要です。許可書は店舗を開く際に受け取るものですが、失くしてしまった場合は「紛失届」を出すことで対処できます。
税務署
税務署に提出する書類は、状況によって異なります。主な提出書類は以下の通りです。
・個人事業の開業・廃業等届出書
事業をやめるのが個人事業主の場合、廃業をしてから1ヵ月以内に提出
・給与支払事務所等の廃止の届出
従業員を雇っていた場合、廃業をしてから1ヵ月以内に提出
・事業廃止届出書
消費税の課税事業者である場合、廃業後遅滞なく提出
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告をしていた場合、廃業した年の翌年3月15日までに提出
それぞれ提出期限などに違いがあるため、遅れないように注意しましょう。
その他
従業員を雇っていた場合は、廃業日の翌日から10日以内に、管轄の労働局へ「雇用保険適用事業所廃止届」の提出が必要です。日本年金機構に対しては「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」や、「雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)」の写しを提出します。こちらは廃業から5日以内に提出しなければなりません。期限が過ぎないよう、スケジュール管理に気を付けましょう。
ガスや電気、水道といったインフラは、使用していなくても基本料金が発生します。解約をせずにいると店舗の営業を終えた後に請求が届いたり、追徴金が課せられたりする可能性があるため、必ず解約の手続きを行いましょう。
飲食店廃業に関する統計と実態
中小企業庁が公表した調査によると、2021年度における宿泊業・飲食サービス業の廃業率は5.6%であり、他業種と比べても高い数値であることがわかりました。また、開業率は17.0%と業種別の中で最も高い数値となっており、飲食業界は入れ替わりが激しい状況にあると考えられます。
(参照元:2022年版 小規模企業白書(HTML版)第2節
中小企業・小規模事業者の現状(第1-1-37図:業種別の開廃業率)|中小企業庁
※Excel形式ファイル:シート1「B13」、シート2「B13」
URL:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/shokibo/b1_1_2.html
一般的に、開業から3年以内に廃業する飲食店の割合は、半数を超えるといわれています。長期間の営業が難しいのは、食のトレンドに左右されやすい飲食業特有の事情や、仕事の内容がハードになりやすいことなどが要因として挙げられます。
飲食店が廃業になる主な理由
飲食店が廃業しやすい理由のひとつが初期投資の負担です。厨房設備や店内のインテリア、店舗の賃貸借契約など、飲食店開業にあたってはさまざまな面でコストがかかるため、店舗をオープンしてから数年は初期投資の回収に注力しなければなりません。想定していた利益が出ない場合、初期投資の返済ばかりに追われて赤字が続き、経営が苦しくなる可能性があります。
また、経営の悪化や環境の変化によって業態を変更したくても、やり直しが難しい点も廃業につながる要因です。業態の変更には、計画を立てる労力だけでなく時間とコストを要します。現状では利益を出しにくいと理解しているものの、手元資金に余裕がなく、業態変更ができない飲食店は少なくありません。無理に営業を続けることで、さらに経営状況が悪くなり廃業に至ることになります。
薄利で店舗を運営している飲食店の場合、運転資金不足に陥って廃業を選択せざるを得なくなるケースもあります。こうしたことから、飲食店を開く際には業界の状況を踏まえた事業計画の構築や余剰金の確保など、さまざまなリスクを考慮に入れた上で経営をすべきです。
飲食店廃業を回避するためにM&Aも検討
飲食店の廃業にあたっては、従業員を解雇しなければならなかったり、初期投資の借金のみが残ったりと、多くの困難に直面することも珍しくありません。そのため、廃業を回避する手段としてM&Aを検討することをおすすめします。
売り手側にとってのM&Aのメリットは、店舗の売却によって譲渡益を得られることです。また、いくつかの要件を満たせば個人保証や担保を解除できる場合もあります。信頼できる企業に店舗を継承することで、従業員の雇用を維持できるのもM&Aの利点です。
買い手側も、エリアやターゲット選定ミスのリスクが低い、他業種よりもM&Aの相場が安価であるなど、さまざまなメリットを得られます。そのため、飲食業界においてM&Aは高い人気があり、個人の店舗にも一定の需要が期待できます。廃業することのみを考えるのではなく、M&Aも選択肢のひとつとして検討する価値があります。
まとめ
飲食店を廃業する場合は、事前に廃業の流れを確認し、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。消防署や警察署など、各役所への手続きも遅滞なく行うようにしましょう。
しかし、経営が立ち行かなくなった際の選択肢は廃業だけではありません。M&Aによって店舗を売却するのもひとつの方法です。譲渡益の獲得や、個人保証や担保の解除、従業員の雇用維持といったメリットが期待できます。M&Aには専門的な知識が求められるため、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。