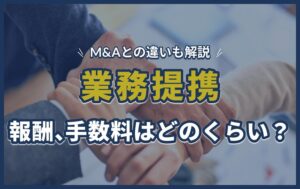未払賃金立替払制度の活用法とは?要件と注意点についても解説
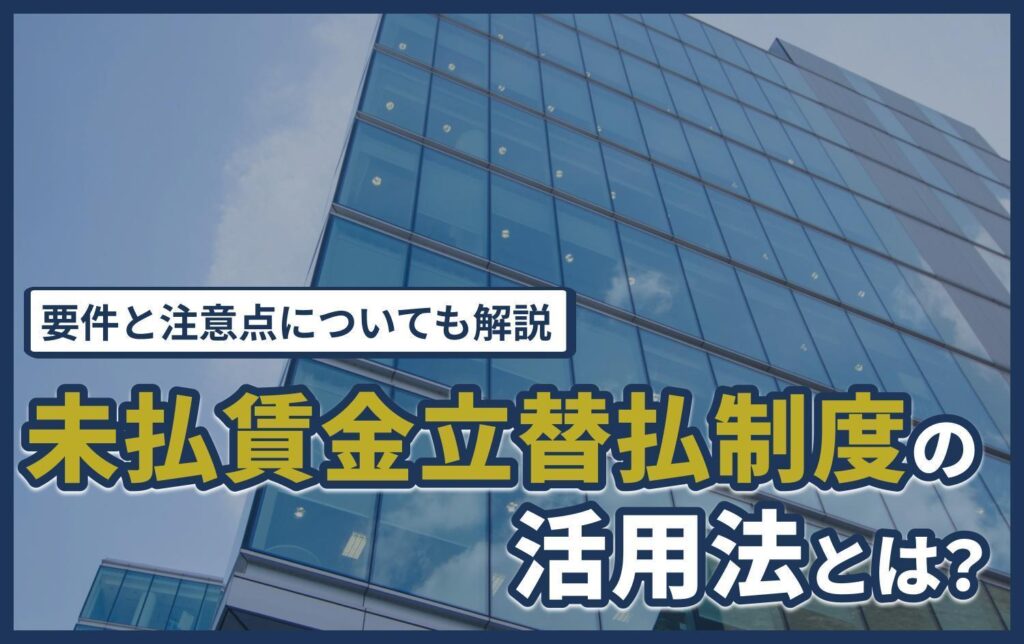
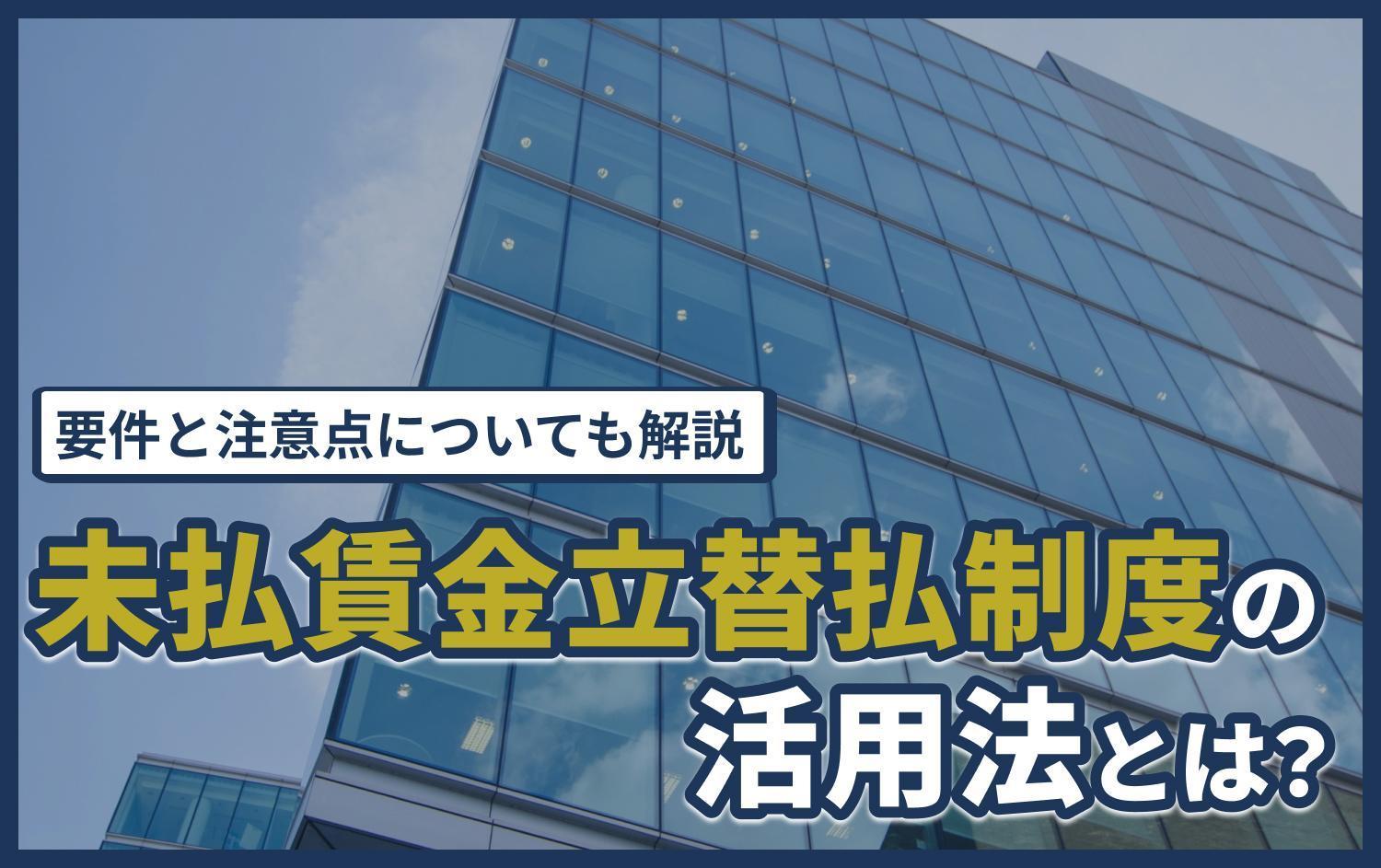
中小企業の経営者の皆様、会社の倒産リスクについて悩んだことはありませんか?
特に、未払賃金の問題は、従業員の生活に直結する重大な問題です。会社の危機に直面した時、従業員の未払賃金をどのように確保すればよいのか…。
そんな疑問や不安を抱えている経営者も多いのではないでしょうか。
実は、そんな時に頼りになるのが「未払賃金立替払制度」です。この制度を活用すれば、会社が倒産した際も、従業員の未払賃金を国が立て替えて支払ってくれるのです。従業員の生活を守りつつ、会社の円滑な清算にもつながる、頼もしい制度と言えるでしょう。
本記事では、未払賃金立替払制度の概要から、適用条件、手続き方法、よくある質問まで、詳しく解説していきます。
目次
未払賃金立替払制度とは何か?
企業が倒産した際、従業員は未払賃金の支払いを受けられなくなるリスクがあります。そんな時、従業員を救済するための制度が「未払賃金立替払制度」です。この制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が、倒産した企業に代わって、従業員に未払賃金を立て替えて支払うというものです。
例えば、Aさんが働いていた会社が倒産し、2ヶ月分の給料が未払いのままだったとします。この場合、未払賃金立替払制度を利用することで、Aさんは労働者健康安全機構から2ヶ月分の給料を受け取ることができるのです。
未払賃金が発生するリスクは、業種によって異なります。特に、建設業、製造業、小売業などは、倒産のリスクが比較的高い業種と言えるでしょう。
また、資金繰りの悪化や売上の減少が続く企業、債務超過に陥っている企業なども、未払賃金のリスクが高くなります。
こうしたリスクが顕在化した場合、従業員の生活に与える影響は計り知れません。例えば、未払賃金が続けば、従業員は家賃の支払いにも困ってしまうかもしれません。従業員の生活を守ることは、経営者の重大な責務と言えるでしょう。
未払賃金立替払制度は、こうした事態を防ぐためのセーフティネットとして機能します。従業員の生活の安定を図り、労働者の保護を図ることを目的としており、1976年に施行された「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて運営されています。
立替払制度の適用条件

では、未払賃金立替払制度は、どのような場合に適用されるのでしょうか。
まず、この制度の適用を受けるには、会社が倒産していることが条件となります。ここでいう倒産とは、法的な手続きの有無に関わらず、事実上の倒産状態を指します。具体的には次のようなケースが該当します。
-
- 事業活動が停止し、再開の見込みがない状態
- 破産手続の開始決定を受けた状態
- 特別清算・会社更生・民事再生の手続き開始決定を受けた状態
倒産に至るプロセスは、企業によって様々です。
例えば、資金繰りの悪化が続き、取引先からの信用を失って事業継続が困難になるケースがあります。あるいは、主要取引先の倒産や不渡りの発生により、連鎖的に倒産に追い込まれるケースもあるでしょう。
こうした状況に陥った企業は、法的な倒産手続きを取ることになります。
破産手続きでは、裁判所が管財人を選任し、管財人が債権者への配当を行います。一方、特別清算や会社更生、民事再生は、再建を目指した倒産処理の手続きです。
いずれの手続きでも、裁判所の監督の下、公平な債権処理が行われることになります。
また、倒産前の6ヶ月以内に退職した労働者も、未払賃金立替払制度の対象となります。
立替払いの対象となる賃金の種類は、次の3つです。
-
- 退職前の6ヶ月以内に支払期日が到来した賃金
- 退職手当(会社が倒産した日以前1年間に退職した人が対象)
ただし、これらの賃金は、労働基準法に定める賃金に限られます。例えば、遅刻や欠勤による賃金カットは、労働基準法上、認められた控除なので、立替払いの対象にはなりません。
また、経営者の一方的な賃金カットも、労働基準法に反するため、立替払いの対象となる賃金額の計算には含まれません。
立替払いの対象期間は、原則として、裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方が対象となります。
立替払いの手続き方法
未払賃金の立替払いを受けるためには、所定の手続きが必要です。大まかな流れは以下の通りです。
1.労働基準監督署への認定申請
労働者は、未払賃金について、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。必要書類を揃えて、労働基準監督署に申請します。
申請の際は、未払賃金の額を正確に把握しておくことが重要です。賃金台帳や給与明細書など、未払賃金の額を証明する書類を用意しましょう。また、会社の倒産状況を示す書類(破産手続開始決定通知書など)も必要となります。
2.労働者健康安全機構への立替払申請
労働基準監督署長の認定を受けたら、労働者健康安全機構に立替払の申請を行います。必要書類を添えて、申請書を提出します。
労働者健康安全機構への申請は、原則として、労働基準監督署長の認定を受けた日から2ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると、立替払いを受けられなくなってしまうので注意が必要です。
申請書の提出は、郵送でも可能です。また、一部の労働者健康安全機構では、オンラインでの申請も受け付けています。最寄りの労働者健康安全機構に、申請方法を確認してみると良いでしょう。
3.労働者健康安全機構による審査・立替払
労働者健康安全機構は、申請内容を審査し、立替払いの可否を決定します。認められれば、申請者の口座に未払賃金が振り込まれます。
審査では、労働基準監督署長の認定内容と、申請内容に相違がないかがチェックされます。また、立替払いの限度額を超えていないかも確認されます。不備がなければ、通常、申請から1~2ヶ月程度で、立替払いが実行されます。
4: 立替払いの限度額と求償権
未払賃金立替払制度では、立替払いの限度額が定められています。退職時の年齢に応じて、以下のような上限額が設定されています。
-
- 45歳以上 370万円
- 30歳以上45歳未満 220万円
- 30歳未満 110万円
ただし、未払賃金の総額がこの限度額を下回る場合は、未払賃金の8割が立替払いの上限となります。
なお、未払賃金には、支払期日から支払日までの遅延利息も含まれます。遅延利息は、年率14.6%で計算されます。ただし、遅延利息の計算期間は、賃金の支払期日から2年を経過する日までとなっています。
また、労働者健康安全機構は、立替払いを行った後、倒産した企業や経営者に対して求償権を行使します。つまり、立て替えた未払賃金について、後日、企業や経営者に返済を求めるのです。
求償権の行使は、労働者健康安全機構から企業・経営者への支払い督促から始まります。それでも支払いがなされない場合は、裁判所に訴えを提起し、強制執行を行うことになります。企業の資産や経営者の個人資産から、立替払い額に相当する金額を回収するのです。
求償権の行使により、労働者健康安全機構は、制度の財源を確保しています。ただ、倒産企業の資産状況によっては、求償権の行使が困難なケースもあります。その場合、国庫からの補填で制度の運営費用を賄うことになります。
未払賃金立替払制度と他の法的手続きの関係

未払賃金立替払制度は、倒産処理手続きとは独立した制度です。したがって、破産手続きや民事再生手続きとは別に、立替払いの申請を行うことができます。
ただし、これらの手続きにおいても、未払賃金は優先的に弁済されるべき債権とされています。そのため、破産手続きにおける配当や、再生計画における弁済により、未払賃金が支払われる可能性があります。
その場合、立替払制度との調整が必要になります。具体的には、破産手続きや再生手続きで弁済を受けた場合、その金額は立替払額から控除されます。また、立替払いを受けた後に、これらの手続きで配当等を受けた場合は、その金額を労働者健康安全機構に返還しなければなりません。
このように、未払賃金立替払制度は、あくまで未払賃金の迅速な支払いを目的とした制度であり、破産手続き等における配当を代替するものではありません。法的手続きにおける債権の回収と、立替払制度とは、別個に進められることになります。
未払賃金立替払制度を利用する際の注意点
未払賃金立替払制度を利用する際には、いくつかの注意点があることを理解しておく必要があります。ここでは、3つの注意点を取り上げます。
2年の制限期間がある
未払賃金立替払制度には、2年の制限期間があります。これは破産等法律上の倒産の場合は裁判所の破産手続の開始等の決定日又は命令日の翌日から起算して2年以内、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が倒産の認定をした日の翌日から起算して2年以内、でなければ立替払を受けられないという規定です。
不正受給した場合には罰則がある
未払賃金立替払制度を利用する際は、不正受給を行わないよう注意が必要です。虚偽の申請を行ったり、立替払を受けた賃金を不正に使用したりした場合、罰則の対象となる可能性があります。
例えば、実際には未払い賃金が発生していないにもかかわらず、虚偽の申請を行って立替払を受けた場合などが該当します。不正受給が発覚した場合、詐欺罪などの刑事罰に問われる可能性もあります。
立替払された未払い賃金には税金がかかる
立替払された未払い賃金は、所得税の対象となります。つまり、立替払を受けた労働者は、受け取った賃金について所得税を納める義務があります。
立替払を受けた際は、税務署から源泉徴収票が送られてきます。この源泉徴収票をもとに、確定申告を行う必要があります。未払い賃金であっても、税金の納付義務があることを忘れないでください。
なお、立替払を受けた賃金については、社会保険料が控除されることはありません。
立替払制度は、あくまでも賃金の一部を立て替えるものであり、社会保険料の立替払は行われません。
中小企業経営者が備えるべき未払賃金対策
未払賃金の発生を防ぐには、日頃からの財務管理が重要です。具体的には、以下のような対策が考えられます。
-
- 資金繰り表を作成し、常に資金の状況を把握する。
- 売掛金の回収を迅速に行い、資金化を図る。
- 不要な経費を削減し、固定費を抑える。
- 金融機関との関係を良好に保ち、必要な時に融資を受けられるようにしておく。
特に、資金繰り表の作成は、経営者の必須スキルと言えるでしょう。毎月の収支を予測し、資金不足が見込まれる場合は、早めの対策を打つことが大切です。
また、従業員とのコミュニケーションも欠かせません。賃金の支払いが遅れそうな場合は、その旨を従業員に説明し、理解を求めることが重要です。従業員の信頼を得ることで、一時的な賃金の遅配にも柔軟に対応してもらえるはずです。
加えて、経営が悪化した場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。弁護士や公認会計士、税理士などの専門家は、法的な手続きや資金繰りの改善策について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
未払賃金立替払制度の活用する際は、専門家に相談しましょう
未払賃金立替払制度の活用には、専門的な知識が必要です。制度の適用条件や手続きの方法など、詳細な規定があるため、素人判断では見落としてしまうポイントもあるでしょう。
こうした場合、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談するのが得策です。社会保険労務士は、労働基準法や社会保険関連法規に精通しており、未払賃金立替払制度の適用条件や手続きについて、的確なアドバイスが得られるはずです。
一方、弁護士は、倒産法制に詳しく、破産手続きや民事再生手続きにおける未払賃金の取り扱いについて、詳しく説明してくれるでしょう。また、労働者健康安全機構への申請代行も行ってくれる場合があります。
専門家に相談するメリットは、何よりも手続きの正確性が担保されることです。書類の不備や申請の遅れにより、立替払いを受けられないというトラブルを防ぐことができます。また、立替払い額の計算についても、専門家のチェックを受けることで、適正な金額を請求できるでしょう。
加えて、経営者の精神的な負担を軽減できる点も見逃せません。未払賃金問題は、経営者にとって大きなストレスとなります。専門家に相談することで、問題解決の道筋が見えてくれば、不安も和らぐはずです。
▼監修者プロフィール

岩下 岳(S&G株式会社 代表取締役) S&G株式会社
新卒で日立Gr.に入社。同社の海外拠点立上げ業務等に従事。
その後、東証一部上場のM&A仲介業界最大手の日本M&Aセンターへ入社ディールマネージャーとして、複数社のM&A(株式譲渡・事業譲渡・業務提携等)支援に関与。IT、製造業、人材、小売、エンタメ、建設、飲食、ホテル、物流、不動産、サービス業、アパレル、産業廃棄物処分業等、様々な業界・業種でM&Aの支援実績を有する。現在はS&G代表として、M&Aアドバイザー、及び企業顧問に従事している。